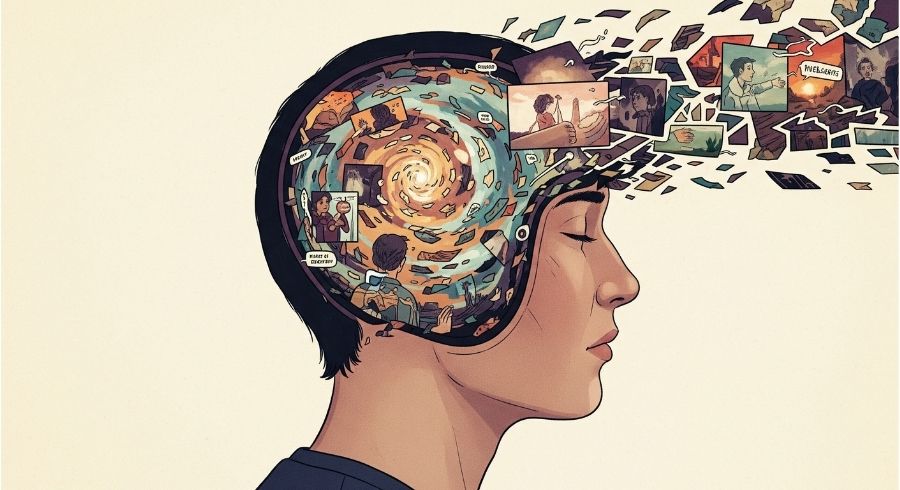
「統合失調症」という病名に、少し怖いイメージや、複雑で分かりにくいという印象をお持ちの方もいらっしゃるかもしれません。しかし、統合失調症は、約100人に1人がかかると言われている、決して珍しくない精神疾患の一つです。そして、適切な治療と周囲のサポートによって、十分に回復し、その人らしい生活を送ることが可能な病気です。
この記事では、統合失調症とはどのような病気か、その主な症状、原因、そして中心となる治療法までを、できるだけ分かりやすく、そして丁寧にご紹介します。ご本人やご家族、周りの方々が病気について正しく理解し、希望を持って回復への道を歩むための一助となれば幸いです。
統合失調症とは|考えや気持ちがまとまりにくくなる脳の病気
統合失調症とは、脳の様々な働きを一つにまとめる(統合する)機能が、一時的に不調になることで、考えや気持ちがまとまりにくくなり、現実を正しく認識することが難しくなる病気です。その結果、感情や思考、行動、人との関わりなど、様々な側面に影響が及びます。
よく「人格が多重に分裂する病気」と誤解されがちですが、そうではありません。脳内の神経伝達物質(ドーパミンなど)のバランスが崩れることなどが原因で、考えや感情に一貫性がなくなり、まるで頭の中にたくさんの情報が溢れかえって、整理がつかなくなってしまったような状態になる、とイメージすると分かりやすいかもしれません。
これは決して特別な病気ではなく、約100人に1人が生涯のうちにかかると言われています。性別による差はなく、多くは思春期から青年期(10代後半~30代)に発症します。早期に発見し、適切な治療を継続することが、症状の安定と回復のために非常に重要です。
統合失調症の主な症状|陽性症状・陰性症状・認知機能障害
統合失調症の症状は、多岐にわたりますが、大きく「陽性症状」「陰性症状」、そして「認知機能障害」の3つのタイプに分けられます。これらの症状は、時期によって強く出たり、目立たなくなったりします。
陽性症状:幻覚や妄想など、通常はないものが出現する
陽性症状とは、健康な時にはなかった状態が、新たに出現する症状のことです。周囲から見ても分かりやすく、病気の急性期に目立ちやすいのが特徴です。本人にとっては現実そのものであり、強い苦痛や恐怖を伴います。
- 幻覚
- 現実にはないものをあるように感じる。最も多いのが、悪口や噂、命令、会話などが聞こえてくる「幻聴」です。周囲には誰もいないのに、はっきりと生々しい声が聞こえるため、ご本人は強い不安や恐怖を感じ、時にその声に返事をしたり、従ったりすることもあります。その他、実在しないものが見える「幻視」や、変な匂いがする「幻嗅」などもあります。
- 妄想
- 非現実的なことを強く信じ込む。明らかに事実とは異なる内容を、周りがどんなに説得しても訂正不可能なほど固く信じ込んでしまう状態です。「誰かに監視されている、盗聴されている」「街中の人が自分の悪口を言っている」といった被害妄想や、「自分は神から特別な使命を与えられた救世主だ」といった誇大妄想、「テレビで自分のことが報道されている」といった関係妄想など、様々な種類があります。
- 思考や行動の障害(まとまりのなさ)
- 思考に一貫性がなくなるため、話が次々と飛んで支離滅裂になったり(連合弛緩)、会話が成り立たなくなったりします。また、目的の分からない行動を繰り返したり、突然興奮して大声をあげたり、逆に無言で固まってしまったり(緊張病症状)と、奇異な振る舞いが見られることもあります。
陰性症状:意欲の低下など、本来あるべきものが失われる
陰性症状とは、これまで持っていた感情や意欲などが、失われたり、乏しくなったりする症状です。陽性症状に比べて目立ちにくいため、周囲からは「怠けている」「やる気がない」「だらしなくなった」と誤解されやすい、ご本人にとってもつらい症状です。
-
- 感情の平板化:喜怒哀楽の表現が乏しくなり、表情が硬く、声のトーンも一本調子になります。周りで起きていることに関心を示さなくなります。
- 意欲の低下:何事にも興味や関心がわかず、身の回りのこと(入浴や着替え、部屋の掃除など)にも無頓着になり、一日中ぼんやりと過ごすことが多くなります。
- 思考の貧困:会話の数が少なくなったり、質問に対して「はい」「いいえ」といった短い返事しかできなくなったりします。
- 社会的引きこもり:人と関わることを避け、自室に引きこもりがちになります。
認知機能障害:記憶力や集中力などが低下する
上記の症状に加え、記憶力、注意力、集中力、物事を計画して実行する能力といった、社会生活を送る上で基盤となる知的な機能が低下する症状です。
-
- 記憶力の低下:新しいことを覚えられない、約束を忘れてしまう。
- 注意・集中力の低下:本を読んでも内容が頭に入らない、人の話に集中できない。
- 遂行機能の低下:料理の手順が分からない、仕事の段取りが組めないなど、計画的な行動が難しくなる。
この認知機能障害は、ご本人が仕事や学業、対人関係などで困難を感じる直接的な原因となり、生活の質に大きく影響します。
統合失調症の原因は?「ストレス脆弱性モデル」が有力
統合失調症は、親の育て方や、本人の性格、あるいは特定の出来事だけが原因で発症するわけではありません。現在、その原因として最も有力視されているのが「ストレス脆弱性モデル」という考え方です。
これは、発症のメカニズムを、コップと水に例えて説明するモデルです。
- 脆弱性(ぜいじゃくせい)=コップの大きさ
- ご本人がもともと持っている、脳の機能的な問題や、遺伝的な要因といった、ストレスに対する「もろさ」や「過敏さ」を指します。コップの大きさが人によって違うように、脆弱性にも個人差があります。
- ストレス=注がれる水
- 進学や就職、人間関係のトラブル、仕事のプレッシャー、あるいは睡眠不足や不規則な生活といった、人生における様々な外部からの「ストレス」を指します。
この2つの要因が組み合わさり、ストレスという水が、その人の持つ脆弱性というコップの許容量を超えて溢れ出してしまった時に、発症するという考え方です。つまり、もともと発症しやすい「脆弱性」を持った人が、人生の様々な「ストレス」にさらされることが引き金となって、発症に至ると考えられています。誰か一人の責任ではなく、様々な要因が複雑に絡み合って起こる病気なのです。
統合失調症の主な治療方法
統合失調症は、早期に発見し、適切な治療を根気強く続けることで、症状をコントロールし、その人らしい生活を送ることが十分に可能な病気です。治療は、主に「薬物療法」と「心理社会的療法」を組み合わせて行われます。
症状を抑え、再発を防ぐ「薬物療法」
薬物療法は、統合失調症の治療の土台となる、最も重要な治療法です。主に、脳内の神経伝達物質(特にドーパミン)の過剰な働きを調整する「抗精神病薬」が用いられます。
この薬は、幻覚や妄想、興奮といった陽性症状を改善させるのに非常に高い効果があります。また、症状が安定した後も、再発を予防するために不可欠です。最近では、副作用が少なく、陰性症状や認知機能障害にも効果が期待できる新しいタイプの薬も開発されています。
症状が良くなったと感じても、自己判断で薬を中断すると、再発のリスクが非常に高まります。必ず主治医の指示に従って、服薬を継続することが大切です。
社会生活機能を回復させる「心理社会的療法」
薬物療法で症状の土台を安定させると同時に、病気によって損なわれた社会生活機能を回復させるためのリハビリテーション(心理社会的療法)が行われます。
- 心理教育
- ご本人やご家族が、病気について正しく理解し、症状への対処法や再発のサインなどを学びます。病気と前向きに付き合っていくための土台となります。
- 社会生活技能訓練(SST)
- 対人関係やコミュニケーションのスキル、ストレスへの対処法などを、ロールプレイング(役割演技)などを通じて具体的に練習します。
- 作業療法
- 手芸やスポーツ、園芸、料理といった具体的な作業活動を通じて、集中力や持続力、対人関係能力の回復を目指します。
- 認知行動療法(CBT)
- 残ってしまった症状(幻聴など)との付き合い方を学んだり、陰性症状によって生じる悲観的な考え方を修正したりします。
回復の土台となる「十分な休養」と「安心できる環境」
上記の専門的な治療と並行して、心と体をゆっくりと休ませること、そして、安心して過ごせる環境を整えることも、非常に重要な治療の一環です。
特に、症状が激しい急性期には、入院も視野に入れ、刺激の少ない環境で十分な休養をとることが、回復への第一歩となります。ご家族や周囲の方々が、病気を正しく理解し、「本人のせいではない」と受け止め、温かく見守り、サポートする姿勢も、ご本人の安心感と回復に大きく貢献します。
統合失調症の悩みや不安に関する相談先
統合失調症の悩みは、決して一人やご家族だけで抱え込む必要はありません。様々な専門機関が、あなたの力になってくれます。
精神科・心療内科などの医療機関
統合失調症の診断と治療は、精神科や心療内科といった専門の医療機関で行われます。心の不調を感じたら、まずはこれらの医療機関に相談することが、回復への最も確実な道です。
地域の保健所・精神保健福祉センター
各都道府県や市区町村に設置されている公的な相談窓口です。保健師や精神保健福祉士といった専門職が、無料で心の健康に関する様々な相談に応じており、適切な医療機関や福祉サービスを紹介してくれます。ご家族からの相談も可能です。
同じ立場の仲間と繋がる当事者会や家族会
同じ病気を抱える当事者や、その家族が集まり、お互いの経験や悩みを分かち合い、支え合う場です。同じ立場だからこそ分かり合える仲間と繋がることは、孤立感を和らげ、回復への大きな力となります。
統合失調症と向き合いながら働きたいあなたへ|就労継続支援B型事業所オリーブ
治療によって症状が安定し、再び「働きたい」という気持ちが湧いてきたとき、「いきなり一般企業で働くのは、まだ不安が大きい」「まずは、安心できる環境で、働くことに慣れたい」と感じるかもしれません。
そんなあなたにとって、就労継続支援B型事業所オリーブは、心強い味方となることができます。
オリーブは、雇用契約を結ばず、あなたの体調や症状の波を最優先に考えながら、自分のペースで働ける場所です。統合失調症の特性に深い理解を持つスタッフが、あなたが安心して能力を発揮できるよう、きめ細やかにサポートします。
-
- 静かで落ち着いた環境:陽性症状や認知機能障害があっても、集中して作業に取り組めるよう、ストレスの少ない環境を整えています。
- 柔軟な働き方:陰性症状で意欲がわかない日も、週に1日、1日2時間といったごく短い時間から、無理なく利用を始められます。
- 安心できる居場所:同じような悩みを持つ仲間や、あなたのつらさを理解してくれるスタッフがいる、温かいコミュニティがあります。
まずはオリーブで、生活リズムを整え、働くことへの自信を少しずつ取り戻すことから、社会復帰への準備を始めてみませんか。関西エリア(大阪、兵庫、京都、奈良)で、あなたらしい働き方の第一歩を踏み出したいとお考えなら、ぜひ一度、オリーブにご相談ください。
