お役立ち情報 コミュニケーションの工夫 その他(失語症、慢性疲労症候群、難病など)
失語症とは?種類別の症状や原因・コミュニケーションの悩みとリハビリを解説
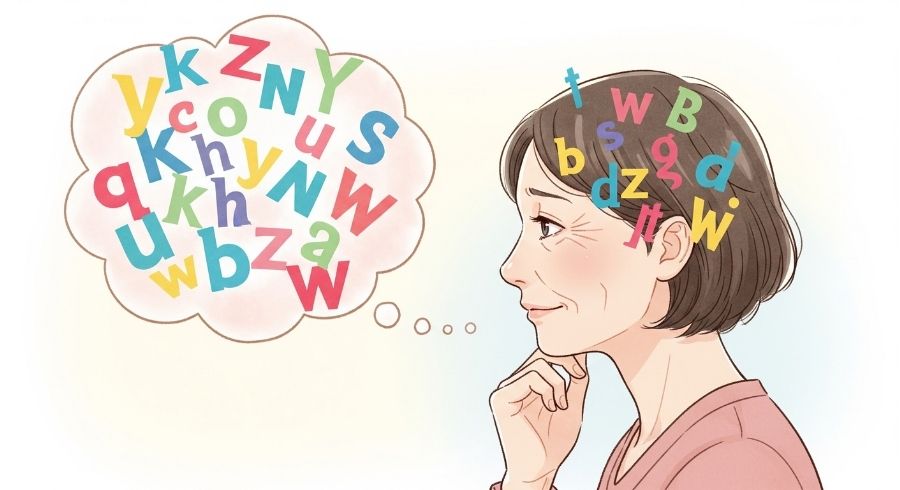
脳卒中や事故の後、「言いたい言葉がうまく出てこない」「相手の話がすんなりと理解できなくなった」といった経験はありませんか。それは「失語症」という、脳の損傷によって言葉を操る能力が損なわれる障害かもしれません。
失語症は、それまで当たり前にできていた「話す・聞く・読む・書く」というコミュニケーションの根幹を揺るがす、非常にもどかしい障害です。しかし、ここで最も大切なのは、知的な能力やその人の人格、経験までが変わってしまったわけではない、ということです。頭の中には豊かな思考や感情がありながら、それを表現するための「言葉」という道具がうまく使えなくなっている状態なのです。
この記事では、失語症の基本的な知識から、症状による種類の違い、主な原因とストレスとの関係、そして回復に向けたリハビリや職場でのコミュニケーションの工夫まで、幅広く解説します。ご本人やご家族が正しい知識を持ち、前向きに社会生活を送るための一助となれば幸いです。
失語症とは?|知的能力は保たれた「言葉の障害」
失語症は、私たちの生活に欠かせない「言葉」の機能に影響を及ぼす障害です。まずは、その基本的な定義や、似ている他の障害との違い、そして原因について正しく理解することから始めましょう。
脳の損傷により言葉を扱う能力が損なわれる障害
失語症とは、病気や事故による脳の損傷が原因で、一度獲得した言語機能、すなわち「話す(表出)」「聞く(理解)」「読む(読解)」「書く(書字)」という4つの能力すべてが、何らかの形で障害される状態を指します。重要なのは、失語症はあくまで「言葉の障害」であり、思考力や判断力、記憶力、専門的な知識といった知的な能力そのものが失われたわけではないという点です。ご本人の人格や経験、個性も、以前と変わらず保たれています。
そのため、周囲が「何も分からなくなったのだろう」と誤解して子ども扱いをしたり、話しかけるのをやめてしまったりすると、ご本人の自尊心を深く傷つけてしまいます。言葉をうまく操れないもどかしさを抱えながらも、思考や感情は豊かに存在していることを理解し、一人の大人として尊重することが、コミュニケーションの第一歩となります。
構音障害や失声症、認知症との違い
言葉や声に関わる障害には、失語症と混同されやすいものがいくつかあります。しかし、原因や障害の核心が異なるため、適切に対応するためにも違いを理解しておくことが重要です。
| 障害名 | 障害の核心 | 主な症状 | 主な原因 |
|---|---|---|---|
| 失語症 | 言語機能そのもの | 話す・聞く・読む・書く能力の低下 | 脳の言語野の損傷(脳卒中など) |
| 構音障害 | 発音・発声の運動 | ろれつが回らない、発音が不明瞭になる | 口や舌など発声発語器官の麻痺 |
| 失声症 (心因性失声) |
声を出すこと | 声が出なくなる、ささやき声しか出ない | 強い心理的ストレス |
| 認知症に伴う言語障害 | 記憶など認知機能全般 | 記憶障害などと共に言葉の障害が現れる | 脳の変性疾患など |
例えば「構音障害」は、唇や舌の動きが悪くなることで「らっぱ」を「だっぱ」のように発音してしまうなど、発音の運動面の問題が中心です。言葉の理解や読み書き能力は基本的に保たれています。一方で「失声症」は、強いストレスが原因で声が出なくなる状態で、筆談など声を使わないコミュニケーションは可能です。このように、似ているようで全く異なる障害であるため、専門家による正確な診断が不可欠です。
失語症とは?|知的能力は保たれた「言葉の障害」
失語症は、私たちの生活に欠かせない「言葉」の機能に影響を及ぼす障害です。まずは、その基本的な定義や、似ている他の障害との違い、そして原因について正しく理解することから始めましょう。
脳の損傷により言葉を扱う能力が損なわれる障害
失語症とは、病気や事故による脳の損傷が原因で、一度獲得した言語機能、すなわち「話す(表出)」「聞く(理解)」「読む(読解)」「書く(書字)」という4つの能力すべてが、何らかの形で障害される状態を指します。重要なのは、失語症はあくまで「言葉の障害」であり、思考力や判断力、記憶力、専門的な知識といった知的な能力そのものが失われたわけではないという点です。ご本人の人格や経験、個性も、以前と変わらず保たれています。
そのため、周囲が「何も分からなくなったのだろう」と誤解して子ども扱いをしたり、話しかけるのをやめてしまったりすると、ご本人の自尊心を深く傷つけてしまいます。言葉をうまく操れないもどかしさを抱えながらも、思考や感情は豊かに存在していることを理解し、一人の大人として尊重することが、コミュニケーションの第一歩となります。
構音障害や失声症、認知症との違い
言葉や声に関わる障害には、失語症と混同されやすいものがいくつかあります。しかし、原因や障害の核心が異なるため、適切に対応するためにも違いを理解しておくことが重要です。
| 障害名 | 障害の核心 | 主な症状 | 主な原因 |
|---|---|---|---|
| 失語症 | 言語機能そのもの | 話す・聞く・読む・書く能力の低下 | 脳の言語野の損傷(脳卒中など) |
| 構音障害 | 発音・発声の運動 | ろれつが回らない、発音が不明瞭になる | 口や舌など発声発語器官の麻痺 |
| 失声症 (心因性失声) |
声を出すこと | 声が出なくなる、ささやき声しか出ない | 強い心理的ストレス |
| 認知症に伴う言語障害 | 記憶など認知機能全般 | 記憶障害などと共に言葉の障害が現れる | 脳の変性疾患など |
例えば「構音障害」は、唇や舌の動きが悪くなることで「らっぱ」を「だっぱ」のように発音してしまうなど、発音の運動面の問題が中心です。言葉の理解や読み書き能力は基本的に保たれています。一方で「失声症」は、強いストレスが原因で声が出なくなる状態で、筆談など声を使わないコミュニケーションは可能です。このように、似ているようで全く異なる障害であるため、専門家による正確な診断が不可欠です。
失語症の主な原因とストレスとの関係
【失語症の主な原因】
失語症は、大脳の言葉を司る領域である「言語野」が物理的に損傷を受けることで発症します。その原因となる代表的な疾患は以下の通りです。
- 脳血管障害(脳卒中):
- 脳の血管が詰まる「脳梗塞」や、血管が破れる「脳出血」「くも膜下出血」が最も多い原因で、全体の約9割を占めるとも言われています。
- 頭部外傷:
- 交通事故や転落事故などで頭を強く打ち、脳が損傷した場合です。
- 脳腫瘍:
- 脳にできた腫瘍が言語野を圧迫したり破壊したりすることで起こります。
- その他:
- 脳炎や若年性アルツハイマー病などの変性疾患が原因となることもあります。
【ストレスとの関係】
ここで注意したいのは、精神的なストレスが失語症の直接的な原因になることはない、という点です。失語症は、あくまで脳の物理的な損傷によって引き起こされます。
しかし、失語症になった後のストレスは、症状の回復に大きく影響します。
- コミュニケーションへのストレス:
- 「言いたいことが伝わらない」「相手の話が理解できない」というもどかしさや焦りは、大きな精神的負担となります。
- 周囲の無理解によるストレス:
- 周囲から「わざと話さない」「ぼーっとしている」などと誤解されることも、強いストレスの原因です。
- 将来への不安:
- 仕事や家庭生活など、将来への不安からストレスを感じ、リハビリへの意欲が低下してしまうことも少なくありません。
これらのストレスが積み重なると、うつ状態になったり、人と話すことを避けるようになったりして、結果的に言語機能の回復を妨げてしまう可能性があります。ご本人のストレスを軽減するためには、リハビリテーションと並行して、心理的なサポートや周囲の人の温かい理解が非常に重要になります。
>失語症の主な種類と症状
失語症は、脳のどの部分が損傷されたかによって、症状の現れ方が異なります。そのため、いくつかのタイプに分類されます。ここでは代表的な4つのタイプをご紹介します。実際には、これらの特徴が複合的に現れることも多くあります。
ブローカ失語(運動性失語)
主に、言葉を話すための運動プログラムを司る「ブローカ野」(前頭葉)の損傷によって起こります。「話す」ことの困難さが特徴的で、「言いたいことはあるのに、言葉が出てこない」という状態です。
【主な症状】
- 非流暢な発話:
- 言いたいことは頭に浮かんでいますが、それを言葉にして口に出すことが困難です。話し方は努力的で、たどたどしく、単語を探しながら話す様子が見られます。
- 喚語困難:
- 物の名前など、言いたい単語がなかなか出てきません。
- 失文法(電文体):
- 「わたし、きのう、スーパー、いく」のように、助詞(「て」「に」「を」「は」など)が抜けた、単語を並べただけの話し方になることがあります。
- 理解は比較的良好:
- 相手の言っていることは比較的よく理解できます。そのため、自分がうまく話せないことへの自覚が強く、もどかしさやいらだちを感じやすい傾向があります。
ウェルニッケ失語(感覚性失語)
主に、言葉の理解を司る「ウェルニッケ野」(側頭葉)の損傷によって起こります。「聞く(理解する)」ことの困難さが特徴的で、「言葉のシャワーを浴びているよう」とも表現されます。
【主な症状】
- 流暢な発話:
- 発話自体は滑らかで、むしろ多弁になることもあります。しかし、内容が伴わないことが多いです。
- 錯語(さくご):
- 言葉の言い間違いが頻繁に起こります。「りんご」を「みかん」と言う(意味性錯語)、「時計」を「とけつ」と言う(音韻性錯語)などが見られます。
- ジャルゴン:
- 意味をなさない新造語や、存在しない言葉を話すことがあります。
- 聴覚的理解の障害:
- 相手の話している言葉の意味を理解することが困難です。そのため、会話が噛み合わなくなり、ちぐはぐな応答になります。
- 病識の欠如:
- 自分が話している内容がおかしいことや、相手の話を理解できていないことへの自覚がないことが多いです。
伝導失語
ブローカ野とウェルニッケ野をつなぐ神経線維(弓状束)の損傷が原因とされています。言葉の理解と表出をつなぐ中継地点の障害とイメージすると分かりやすいでしょう。
【主な症状】
- 復唱の困難:
- 聞いた言葉を繰り返す(復唱する)ことが特に難しくなります。例えば「さくらんぼ」と言われても、「さ…さかんぼ」のようにうまく言い直せないことがあります。
- 錯語:
- ウェルニッケ失語と同様に、言い間違い(錯語)が多く見られますが、自分の間違いに気づいて言い直そうとする姿勢があります。
- 理解と発話は比較的良好:
- 言葉の理解力や、自発的な発話の能力は比較的保たれているため、会話のやりとりはある程度スムーズにできます。
全失語(グローバル失語)
脳の広範囲にわたって損傷がある場合に起こり、「話す・聞く・読む・書く」のすべての能力が大きく障害されます。失語症の中でも最も重度なタイプとされています。
【主な症状】
- 言葉の理解と表出の両方が困難:
- 話しかけられても反応が乏しい、短い単語しか発せない、などの症状が見られます。
- コミュニケーション全般に強い制限:
- 日常会話がほとんど成立せず、身振りや表情に頼った意思疎通が中心になります。
- 回復には時間がかかる:
- リハビリによってある程度の改善は期待できますが、長期的なサポートが必要になるケースが多いです。
失語症の回復とリハビリの進め方
失語症の回復は、脳の自然な回復力とリハビリテーションによる機能改善によって進みます。症状の重さや発症からの時間によって回復の程度やスピードは異なりますが、適切な支援によって多くの方が改善を実感しています。
リハビリは、言語聴覚士(ST)と呼ばれる専門家が中心となって行われ、「話す」「聞く」「読む」「書く」といった機能ごとに訓練が行われます。加えて、実際の会話場面を想定した訓練や、身振り・表情・筆談など他の手段を活用したコミュニケーション方法の習得も含まれます。
職場復帰とコミュニケーションの工夫
失語症を抱えながらも仕事に復帰することは可能です。実際に多くの方が、周囲の理解と支援を得ながら職場に戻り、自分らしい働き方を実現しています。そのためには、ご本人と職場の双方が、失語症に対する正しい知識を持ち、柔軟な対応を行うことが大切です。
失語症のある方が職場復帰するために必要なこと
まず、ご本人の「どのような症状があるのか(話す、聞く、読む、書くのうち、どれがどの程度困難か)」「どんなときに困るのか」「どのような配慮や工夫があると働きやすいか」といった情報を整理しておくことが大切です。これは、ご本人自身が把握しておくことも重要ですが、復職前に産業医や職場の上司、人事担当者と共有しておくと、職場での受け入れ態勢が整いやすくなります。
加えて、業務内容の調整や、就労支援制度の活用も有効です。例えば、通院やリハビリに配慮した勤務時間の設定、読み書きの補助ツールの導入、会議でのメモや資料の事前共有など、さまざまな工夫が考えられます。
周囲の理解と協力が回復の支えに
失語症の方とのコミュニケーションでは、以下のような工夫が役立ちます。
-
- ゆっくり、はっきりと話す
- 一度に多くのことを言わず、要点を簡潔に伝える
- 身振りや表情、指差しなどの非言語的手段も使う
- 筆談や図を使う、選択肢を示すなどの工夫をする
- 発話に時間がかかっても待つ姿勢を持つ
- 「伝えようとしていること」を汲み取るように努める
また、「失語症=話せない・理解できない」という誤解を解くためにも、職場全体で失語症について学ぶ機会を設けることも有効です。
まとめ|失語症の理解と支援の輪を広げよう
失語症は、誰にでも突然起こり得る障害であり、決して珍しいものではありません。「話す・聞く・読む・書く」といった言葉の力に影響はあっても、その人自身の価値や思考力、人間性が失われたわけではないことを、私たちは決して忘れてはいけません。
ご本人が前向きにリハビリに取り組み、自分らしい生活や仕事を取り戻していくためには、周囲の理解とサポートが欠かせません。一人ひとりが失語症について正しく理解し、思いやりを持って接することで、誰もが安心して自分らしく暮らせる社会に近づいていくことでしょう。
