うつ病 お役立ち情報 その他(てんかん、気分変調症など) 治療法・リハビリ
気分変調症(持続性抑うつ症)とは?うつ病との違いや症状・治療法を解説
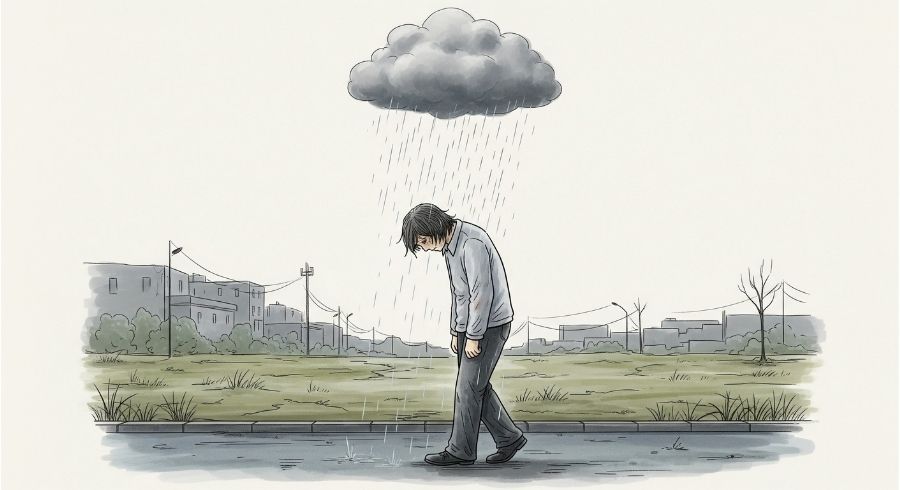
「昔からずっと、なんとなく気分が晴れない」「大きな悩みはないけれど、心から楽しいと感じることも少ない」「周りからは『考えすぎ』『暗い性格』と言われるけれど、自分ではどうしようもできない」
このような、すっきりしない、どんよりとした気分の不調が、何年もの間、当たり前になっていませんか。もしかしたら、その長く続く気分の落ち込みは、あなたの「性格」ではなく、「気分変調症(持続性抑うつ症)」という、治療が可能な心の病気かもしれません。
この記事では、気分変調症とはどのような病気か、よく知られる「うつ病」との違い、そして主な症状や治療法、仕事との付き合い方までを、分かりやすく解説していきます。ご自身の状態を正しく理解し、より軽やかな毎日を送るための一歩として、ぜひお役立てください。
気分変調症(持続性抑うつ症)とは?軽い抑うつ症状が慢性的に続く病気
気分変調症は、現在では持続性抑うつ障害(Persistent Depressive Disorder: PDD)とも呼ばれる、気分障害の一種です。その最大の特徴は、比較的軽い、しかしながら慢性的な抑うつ症状(気分の落ち込みなど)が、非常に長い期間(大人で2年以上)にわたって持続することです。うつ病(大うつ病性障害)のように、日常生活が全く送れなくなるほど症状が重いわけではないため、なんとか仕事や学校に行くことはできます。しかし、常に気分が晴れず、心に薄い灰色の膜がかかったような状態で、喜びや楽しさを感じにくく、ご本人は長期間にわたってつらい思いを抱えています。
「性格の問題」と間違われやすく気づきにくい
気分変調症のもう一つの特徴は、ご本人も周囲も、病気だと気づきにくいという点です。症状が比較的軽く、それが何年にもわたって続くため、「自分はもともと、こういう悲観的で物事をネガティブに考える性格なんだ」「昔からずっとこうだから、これが普通の自分なんだ」と思い込んでしまいがちです。周囲からも、「いつも元気がない人」「付き合いが悪い人」といった「性格」や「人格」の問題として捉えられ、病気として認識されにくい傾向があります。その結果、適切な治療を受けないまま、長年つらい思いを一人で抱え続けてしまうケースが少なくありません。
気分変調症とうつ病の違い
気分変調症は、うつ病と症状が似ている部分もありますが、「症状の重さ」と「期間」に大きな違いがあります。うつ病が「激しい嵐」だとすれば、気分変調症は「延々と続く、冷たい霧雨」に例えられます。
| 気分変調症(持続性抑うつ症) | うつ病(大うつ病性障害) | |
|---|---|---|
| 症状の重さ | 比較的軽度。日常生活は何とか送れる。 | 重度。日常生活に大きな支障が出る。 |
| 期間 | 2年以上、抑うつ気分が続くのが特徴。 | 2週間以上、重い症状が続く。 |
| 気分の波 | 慢性的にずっと気分が優れない。 | 気分が良い時期と、悪い時期の波がある。 |
注意すべき「二重うつ病(ダブルデプレッション)」
気分変調症の方が、その経過中にうつ病のエピソードを併発することがあり、これは「二重うつ病(ダブルデプレッション)」と呼ばれます。慢性的な霧雨の中に、激しい嵐がやってくるような状態で、症状がより重く、深刻になります。気分変調症を放置していると、この二重うつ病に移行するリスクが高まるとも言われており、早期に専門家へ相談し、適切な治療を開始することが重要です。
気分変調症の主な症状
気分変調症の症状は、うつ病と似ていますが、比較的軽いものが長く続くのが特徴です。精神面と身体面の両方に現れます。
精神症状:慢性的な気分の落ち込みや自己評価の低さ
-
- 抑うつ気分:明確な理由はないのに、ほとんど一日中、気分が沈んでいる、空虚な気持ちになる。
- 興味・関心の喪失:以前は楽しめていた趣味や活動に、興味が湧かなくなる。
- 自己評価の低下:「自分は何をやってもダメだ」「自分には価値がない」など、自分を過度に否定的に捉えてしまう。
- 集中力・決断力の低下:仕事や家事などに集中できない、新聞を読んだりテレビを見たりするのも億劫になる、些細なことでも決断ができない。
- 絶望感:将来に対して、悲観的になり、希望が持てなくなる。
- イライラ感:ささいなことで怒りっぽくなったり、焦りを感じたりする。
身体症状:慢性的な疲労感や睡眠・食欲の変化
-
- 慢性的な疲労感・倦怠感:十分に休んでも、疲れが取れない。常に体が重く、だるいと感じる。
- 睡眠障害:夜、なかなか寝付けない(入眠困難)、夜中に何度も目が覚める(中途覚醒)、朝早く目が覚めてしまう(早朝覚醒)、あるいは、逆にいくら寝ても眠い(過眠)といった睡眠の問題を抱える。
- 食欲の変化:食欲がなくなって体重が減る、あるいは、反対に甘いものなどを過剰に食べてしまい体重が増える。
- その他の不調:原因不明の頭痛や肩こり、めまい、動悸、胃の不快感など、様々な身体症状が現れることがある。
もしかして?と思ったら|気分変調症のセルフチェック
以下の項目は、ご自身の状態を客観的に見るための目安です。ご自身の状態に最も近いものを選んでみてください。
【気分変調症セルフチェック】
- この2年間、気分が沈んでいる、または空虚だと感じることが、ない日よりもある日の方が多いですか?
- 気分が落ち込んでいるときに、以下の症状のうち2つ以上が当てはまりますか?
-
-
- 食欲がない、または食べ過ぎてしまう
- 眠れない、または眠りすぎてしまう
- 気力がない、または疲れやすい
- 自分に自信がない、自己評価が低い
- 集中できない、または物事を決めるのが難しい
- 将来に希望が持てない、絶望的だと感じる
-
<結果の見方>
上記の両方の質問に「はい」と答えた方は、気分変調症の可能性があります。
【重要】
このチェックリストは、あくまでご自身の状態に気づくための目安です。気分変調症の診断は、医師による詳しい問診を通して行われます。結果がどうであれ、「長期間つらい」と感じている場合は、自己判断せずに必ず専門の医療機関に相談してください。
気分変調症の原因|様々な要因が複雑に絡み合う
気分変調症のはっきりとした原因は、まだ完全には解明されていません。しかし、うつ病と同様に、単一の原因ではなく、様々な要因が複雑に絡み合って発症すると考えられています。
- 生物学的要因:
- 脳内のセロトニンなどの神経伝達物質のバランスの乱れが、気分の調節に影響を与えると考えられています。また、家族にうつ病や気分変調症の人がいる場合、遺伝的に発症しやすい体質である可能性も指摘されています。
- 心理的・性格的要因:
- もともとの性格として、物事を悲観的に捉えやすい、自己評価が低い、完璧主義で自分に厳しい、といった傾向がある場合、ストレスを溜め込みやすく、発症の一因となることがあります。
- 環境的要因:
- 長期間にわたる過度なストレス(仕事、家庭、人間関係など)や、幼少期のつらい体験(喪失体験やトラウマなど)が、発症の引き金となることがあります。
気分変調症の診断と主な治療方法
「自分は気分変調症かもしれない」と思ったら、どこに相談し、どのような治療が行われるのでしょうか。
精神科・心療内科での診断
気分変調症の診断は、精神科や心療内科の医師によって、国際的な診断基準(DSM-5など)に基づいて行われます。診断で最も重要なポイントは、抑うつ気分が、ほとんど一日中、ない日よりもある日の方が多く、その状態が2年以上(子どもや思春期の場合は1年以上)続いていることです。それに加え、前述のセルフチェックにあるような症状が2つ以上当てはまることなどが基準となります。
精神療法(心理療法)と薬物療法を組み合わせて治療
気分変調症の治療は、精神療法(心理療法)と薬物療法を組み合わせて行うのが一般的で、最も効果的とされています。
- 精神療法:
- 専門家との対話を通じて、ご自身の考え方や行動のパターンを見つめ直し、ストレスへの対処法を身につけていきます。特に、物事の捉え方を修正していく認知行動療法や、対人関係の問題解決に焦点を当てる対人関係療法などが有効とされています。これにより、悲観的な思考の癖を修正し、自己肯定感を高めていくことを目指します。
- 薬物療法:
- 脳内の神経伝達物質のバランスを整えるため、主に抗うつ薬(SSRIなど)が用いられます。薬を服用することで、慢性的な気分の落ち込みや不安を和らげ、精神療法にも取り組みやすくなる効果が期待できます。
治療には時間がかかりますが、根気強く続けることで、症状は着実に改善していきます。
気分変調症と仕事|上手く付き合うための工夫とサポート
気分変調症を抱えながら仕事を続けることは、大きな困難を伴います。無理なく働き続けるためには、いくつかの工夫とサポートの活用が鍵となります。
一人で抱えず、周囲のサポートを得る
慢性的な気分の落ち込みや疲労感を、意志の力だけで乗り越えようとするのは非常に困難です。一人で抱え込まず、信頼できる人に相談することが大切です。もし可能であれば、職場の信頼できる上司や人事担当者、産業医などに相談し、病状について伝えることで、業務量の調整や、頻繁な確認・指示を避けてもらうといった、必要な配慮(合理的配慮)を得られる場合があります。
無理をせず「休職」も大切な選択肢
どうしても仕事に行くのがつらい、症状が悪化していると感じる場合は、無理をせずに休職し、治療に専念することも非常に重要な選択肢です。休職中は、多くの場合、健康保険から「傷病手当金」が支給され、経済的な不安を和らげることができます。仕事のプレッシャーから離れて心と体をしっかりと休ませることが、結果的に、その後のより良い職業人生につながります。
気分変調症の方が利用できる支援や制度
気分変調症と診断された場合、治療や生活を支えるための様々な公的制度を利用できる可能性があります。
- 自立支援医療(精神通院医療):
- 精神科や心療内科への継続的な通院にかかる医療費の自己負担額を、通常3割のところを1割に軽減できる制度です。薬局での薬代も対象となります。
- 精神障害者保健福祉手帳:
- 気分変調症も、症状の程度によっては交付対象となります。手帳を取得すると、税金の控除や公共料金の割引など様々な経済的メリットがあるほか、障害者雇用枠での就職活動が可能になります。
- 就労移行支援・就労継続支援:
- 気分変調症が原因で離職し、再就職に不安がある場合や、働き続けることに困難を感じている場合に利用できる就労支援サービスです。就労移行支援は一般企業への就職を目指す訓練を、就労継続支援はサポートのある環境で働く機会を提供します。
気分変調症と向き合いながら働きたいあなたへ|就労継続支援B型事業所オリーブ
「常に気分が晴れず、働くエネルギーが湧いてこない」「決まった時間に、毎日会社に行くこと自体が大きなプレッシャーだ」「周りに気を遣わせているのではないかと感じて、職場に居づらい」
気分変調症の慢性的なつらさを抱えながら、一般企業で働き続けることに限界を感じていませんか。もしあなたが、もっと自分の心と体のペースを大切にしながら、安心して働ける場所を探しているなら、就労継続支援B型事業所オリーブという選択肢があります。
オリーブは、雇用契約を結ばず、あなたのその日の体調を最優先に、週に1日、1日2時間といったごく短い時間からでも利用できる場所です。気分の波があることを前提に、スタッフがあなたの状態を理解し、温かくサポートします。
まずはオリーブという安心できる環境で、達成感のある軽作業などを通じて、少しずつ自信と生活リズムを取り戻すことから始めてみませんか。関西エリア(大阪、兵庫、京都、奈良)で、あなたらしい働き方の第一歩を踏み出したいとお考えなら、ぜひ一度、オリーブにご相談ください。
