うつ病 お役立ち情報 傷病手当金 双極性障害 発達障害 相談先 精神疾患 精神科デイケア 統合失調症 自立支援医療制度 障害年金 障害者手帳(精神・身体・療育)
精神疾患とは?主な種類や原因・利用できる支援制度をわかりやすく解説
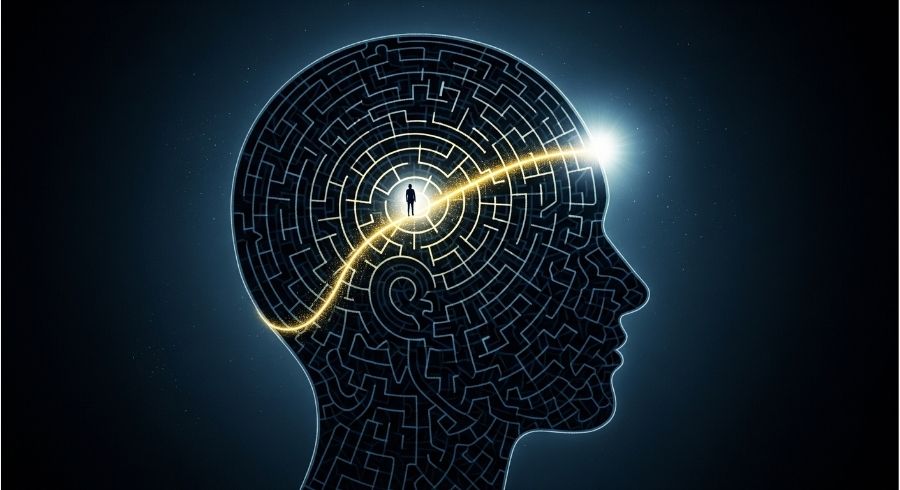
「最近、気分が落ち込んで何もやる気が起きない」「理由もなく、急に強い不安に襲われる」このような心の不調を感じていても、「気の持ちよう」「自分の弱さのせいだ」と一人で抱え込み、誰にも相談できずに苦しんでいる方はいらっしゃいませんか。「精神疾患」という言葉に、少し怖いイメージや、自分とは縁遠いものという印象を持つ方もいるかもしれません。しかし、精神疾患は、決して特別なものではなく、誰もがかかる可能性のある身近な病気です。この記事では、精神疾患とは何か、その主な種類や原因、そして回復を支える治療法や、生活・就労をサポートする公的な支援制度までを、網羅的に、そして分かりやすく解説していきます。正しい知識を身につけることは、あなた自身や、あなたの大切な人を守るための第一歩です。
精神疾患とは?精神障害との違い
まず、よく似た言葉である「精神疾患」と「精神障害」の違いについて理解しておきましょう。
- 精神疾患:
- うつ病や統合失調症、不安障害といった、脳の機能的な問題や、強いストレスなどが原因で、考え方や気分、行動などに影響が現れる「病気(disease)」そのものを指す、医学的な用語です。風邪や糖尿病といった身体の病気と同様に、治療の対象となります。
- 精神障害:
- 精神疾患によって、日常生活や社会生活(仕事、学業、人付き合いなど)を送る上で、継続的な制限や困難が生じている「状態(disability)」を指す、福祉的な用語です。「精神障害者保健福祉手帳」の交付などは、この「障害」の程度に応じて判断されます。
つまり、「精神疾患」という病気があり、その結果として生じる生活上の困難が「精神障害」である、と考えると分かりやすいでしょう。
精神疾患の主な種類と症状
精神疾患には様々な種類があり、それぞれに特徴的な症状があります。ここでは、代表的なものをいくつかご紹介します。
うつ病・双極性障害などの「気分障害」
感情や気分のコントロールがうまくいかなくなる病気の総称です。
- うつ病:
- 強い気分の落ち込み、何事にも興味や喜びを感じられない状態が長く続き、不眠や食欲不振、疲労感などの身体症状も伴います。思考力や集中力の低下も著しく、日常生活に大きな支障をきたします。
- 双極性障害(躁うつ病):
- 気分が異常に高揚し、眠らなくても平気になったり、次々とアイデアが浮かんで過剰に活動的になったりする「躁状態」と、気分がひどく落ち込む「うつ状態」を繰り返す病気です。
統合失調症
考えや気持ちがまとまりにくくなる病気です。その影響で、様々な症状が現れます。
- 陽性症状:
- 本来はないはずのものがあるように感じる症状。悪口や命令などが聞こえる「幻聴」や、事実に反することを固く信じ込む「妄想」などがあります。
- 陰性症状:
- 本来あるはずの機能が失われる症状。意欲の低下、感情表現の減少(感情の平板化)、引きこもりなどが現れます。
不安障害・適応障害などの「ストレス関連障害」
過剰な不安や恐怖、あるいは特定のストレスによって、日常生活に支障が出る病気の総称です。
- 不安障害:
- 電車の中などで突然、動悸や息苦しさに襲われる「パニック障害」や、人前での発言などに強い恐怖を感じる「社交不安障害」など、特定の状況に対して強い恐怖を感じます。
- 適応障害:
- 特定のストレス(仕事や家庭の問題など)が原因で、気分の落ち込みや不安、行動面の変化などが現れる病気です。原因から離れると症状が改善する傾向があります。
発達障害
生まれつきの脳機能の発達の偏りによって、幼少期から行動面や情緒面に特徴が現れる状態です。これは後天的な「病気」とは異なりますが、その特性から社会生活で困難を抱えたり、うつ病などの二次障害を引き起こしたりすることがあり、障害福祉サービスの対象となります。
- 自閉スペクトラム症(ASD):
- 対人関係の構築や、場の空気を読むことなどが苦手で、特定の物事に強いこだわりを持つといった特徴があります。
- 注意欠如・多動症(ADHD):
- 年齢に見合わない不注意さ(忘れ物が多い、集中力が続かない)や、多動性・衝動性(じっとしていられない、思いつきで行動する)が特徴です。
精神疾患の主な原因は3つに分類される
精神疾患は、単一の原因で発症するわけではありません。その原因は、大きく「心因性」「内因性」「外因性」の3つに分類され、これらが複雑に絡み合って発症すると考えられています。
心因性:ストレスなど心理的な要因
仕事上のプレッシャーや人間関係のトラブル、身近な人との死別、つらい出来事といった、心理的なストレスが主な原因となって発症するタイプです。適応障害や、PTSD(心的外傷後ストレス障害)などが、この心因性に分類されます。
内因性:脳の機能など体質的な要因
明確な外的ストレスが見当たらないにもかかわらず、脳内の神経伝達物質のバランスの乱れなど、その人が元々持っている体質的な要因が強く関わって発症するタイプです。統合失調症や、双極性障害、うつ病の一部は、この内因性に分類されると考えられています。
外因性:アルコールや薬物・頭部の外傷など
アルコールや薬物などの物質、あるいは頭部の外傷や、脳の病気(脳梗塞、脳腫瘍など)といった、脳に直接的な物理的ダメージが加わることが原因で発症するタイプです。アルコール依存症に伴う精神症状や、脳の損傷による高次脳機能障害などが、この外因性に分類されます。
精神疾患の主な治療方法
精神疾患は、決して「治らない病気」ではありません。適切な治療を根気強く続けることで、症状をコントロールし、その人らしい生活を送ることが十分に可能です。治療は、主に「休養」「薬物療法」「精神療法」を組み合わせて行われます。
休養
特にうつ病など、心身のエネルギーが枯渇している疾患では、何よりもまず「休む」ことが治療の第一歩です。ストレスの原因となっている環境(職場など)から離れ、心と体をゆっくりと休ませる時間を確保することが、回復の土台となります。
薬物療法と副作用への対処
薬物療法は、脳内の神経伝達物質のアンバランスを整えることで、つらい症状を和らげることを目的とします。抗うつ薬、抗不安薬、抗精神病薬、気分安定薬など、疾患や症状に合わせて様々な薬が用いられます。薬には、眠気や口の渇き、体重増加といった副作用が現れることもあります。しかし、自己判断で薬の量を減らしたり、中断したりすると、症状の再発や悪化につながる危険性があります。副作用がつらい場合は、必ず主治医に相談し、薬の種類の変更や、副作用を抑える薬の追加などを検討してもらいましょう。
精神療法(カウンセリングなど)
精神療法は、医師やカウンセラーなどの専門家との対話を通じて、ご自身の考え方や感情のパターンに気づき、問題解決のスキルを身につけていく治療法です。特に「認知行動療法(CBT)」は、多くの精神疾患に効果が実証されている代表的な精神療法です。これは、ご本人を苦しめている極端な考え方や思い込み(認知のゆがみ)を、より柔軟でバランスの取れたものに変えていくことで、つらい気分や問題行動を改善していくことを目指します。
ご家族や周囲の方ができること
ご家族や友人など、身近な人が精神疾患になったとき、どのように関わればよいか戸惑う方も多いでしょう。周囲の理解とサポートは、ご本人の回復にとって大きな力となります。
-
- 病気を正しく理解する:まずは、その病気がどのようなもので、どのような症状が現れるのかを正しく知ることが大切です。「怠けている」「気持ちが弱い」といった誤解や偏見を持たず、病気の症状として理解しましょう。
- 話をじっくり聴く:アドバイスや意見を言う前に、まずは本人のつらい気持ちを否定せずに受け止め、共感的に耳を傾けましょう。
- 安易に励まさない:特にうつ病の方に対して、「頑張れ」という言葉は、本人をさらに追い詰めてしまうことがあります。「ゆっくり休んでいいんだよ」と、安心できる言葉をかけましょう。
- 専門家への相談を勧める:本人が一人で抱え込んでいる場合は、「一緒に病院に行ってみようか」「相談窓口に電話してみようか」と、具体的な行動を後押ししてあげましょう。
精神疾患のある方が利用できる公的な支援制度
精神疾患の治療や、その後の社会復帰には、様々な公的な支援制度を利用することができます。一人で抱え込まず、これらの制度を積極的に活用しましょう。
生活や医療費を支える制度
治療中の経済的な不安を和らげるための制度です。
- 自立支援医療(精神通院医療):
- 精神疾患の治療のために、継続的に通院する際の医療費の自己負担額を、通常3割のところを1割に軽減できる制度です。薬局での薬代も対象となります。
- 傷病手当金:
- 会社の健康保険に加入している方が、病気やけがで休職し、給与が支払われない場合に、最長で通算1年6ヶ月間、給与のおおむね3分の2が支給されます。
- 障害年金:
- 病気や障害によって、生活や仕事が著しく制限される場合に受給できる公的な年金です。
- 精神障害者保健福祉手帳:
- 精神疾患により、長期にわたり日常生活や社会生活に制約がある場合に交付されます。税金の控除や公共料金の割引、障害者雇用枠での就職など、様々な福祉サービスを利用できるようになります。
社会復帰や就労をサポートする機関
症状が安定し、社会復帰や就労を考え始めた際には、専門の機関が力になってくれます。
- 精神科デイケア:
- 医療機関などで行われる、日帰りのリハビリテーションです。集団でのプログラムを通じて、生活リズムを整え、対人スキルを高め、社会復帰の準備をします。
- ハローワーク:
- 障害のある方向けの専門窓口があり、病状に理解のある求人を紹介してくれます。
- 地域障害者職業センター:
- ハローワークと連携し、より専門的な職業評価や、職業準備支援、ジョブコーチによる職場定着支援などを行います。
- 就労移行支援・就労継続支援事業所:
- 一般企業への就職を目指すための訓練を行う「就労移行支援」や、サポートのある環境で働く機会を提供する「就労継続支援」といった、障害福祉サービスがあります。
精神疾患と向き合いながら働きたいあなたへ|就労継続支援B型事業所オリーブ
精神疾患の治療を受けながら、あるいは回復の過程で、一般企業で働くことに不安や難しさを感じる方は少なくありません。「体調に波があって、毎日通う自信がない」「プレッシャーの少ない環境で、自分のペースで働きたい」と感じていませんか。
そんなあなたにとって、就労継続支援B型事業所オリーブは、心強い味方となることができます。
オリーブは、雇用契約を結ばず、あなたの体調や気持ちを最優先に考えながら、週に1日、1日2時間といったごく短い時間からでも利用できる福祉サービス事業所です。精神疾患への深い理解を持つスタッフが、あなたが安心して過ごせるよう、きめ細やかにサポートします。
まずはオリーブという安心できる環境で、軽作業などを通じて、生活リズムを整え、働くことの達成感や喜びを感じることから始めてみませんか。関西エリア(大阪、兵庫、京都、奈良)で、あなたらしい働き方の第一歩を踏み出したいとお考えなら、ぜひ一度、オリーブにご相談ください。
