お役立ち情報 その他(てんかん、気分変調症など) 手帳・経済支援 精神疾患 自立支援医療制度 障害年金 障害者手帳(精神・身体・療育)
大人にも起こるてんかんとは?症状・原因・発作の種類・治療法を解説
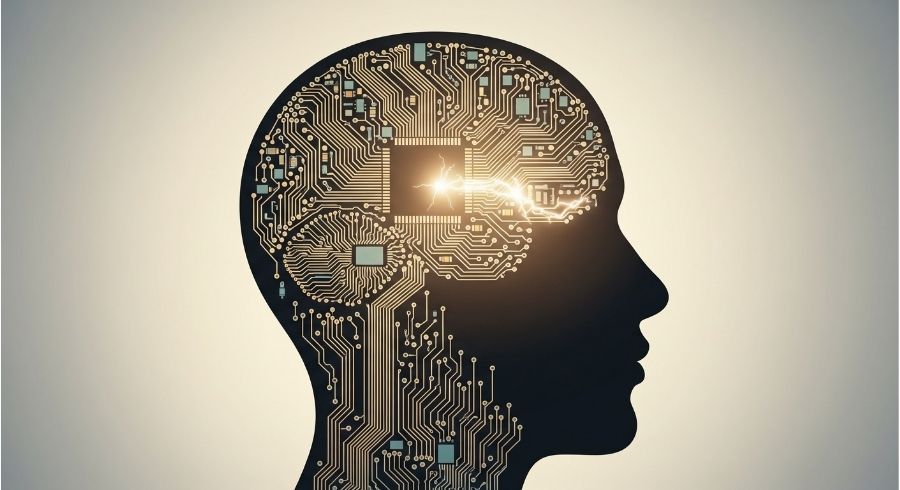
「てんかん」は子ども特有の病気と思われがちですが、実際にはあらゆる年齢で発症し、成人後に診断されることも決して珍しくありません。突然意識を失うような発作だけでなく、症状は多様なため、本人や周囲がてんかんだと気づかないケースもあります。
てんかんは、正しい知識を持って適切な治療を受ければ、多くの人が発作をコントロールし、自分らしい生活を送ることが可能な病気です。本記事では、大人のてんかんを中心に、症状や原因、仕事上の配慮や発作時の対応、利用できる福祉サービスまで詳しく解説します。
てんかんとは?脳神経の異常な興奮が原因
てんかんは、日本国内に約100万人の患者がいる身近な脳の慢性疾患です。その定義や原因について解説します。
てんかんの定義
てんかんとは、脳に生じた慢性的な異常により「てんかん発作」を繰り返す病気です。一度の発作で「てんかん」と診断されるわけではありません。一般的に、明らかな誘因がない「てんかん発作」が24時間以上の間隔をあけて2回以上繰り返された場合に、てんかんと診断されます。
脳の異常放電が起きる仕組み
私たちの脳は、無数の神経細胞(ニューロン)が電気信号をやり取りして機能しています。通常、この電気信号は規則正しく流れています。しかし、何らかの原因で神経細胞の一部が過剰に興奮し、電気信号が乱れる「異常放電」が発生することがあります。この異常放電が脳の正常な働きを一時的に妨げ、様々な症状を引き起こすのが「てんかん発作」です。
てんかん発作の原因
てんかんの原因は、特定できる「症候性てんかん」と、検査をしても原因不明な「特発性てんかん」に大別されます。成人後に発症するてんかんは、症候性てんかんの割合が高いのが特徴です。主な原因には以下のような脳の病気や外傷が挙げられます。
-
- 脳卒中(脳梗塞、脳出血など)
- 脳腫瘍
- 頭部外傷(交通事故や転落による脳の損傷)
- 脳炎・髄膜炎などの感染症
- アルツハイマー病などの変性疾患
- 先天的な脳形成異常
これらの要因で脳が損傷し、神経細胞のネットワークが乱れると、異常放電が起きやすくなると考えられています。
てんかん発作の症状と種類
てんかん発作の症状は多様です。脳の異常放電が始まる場所によって、主に「全般起始発作」と「焦点起始発作」に分類されます。
全般起始発作
脳全体がほぼ同時に興奮して起こる発作で、開始時から意識を失うことがほとんどです。
-
- 強直間代発作(きょうちょくかんだいほっさ): 突然意識を失い、全身の筋肉が硬直する「強直相」と、手足をリズミカルに曲げ伸ばしする「間代相」が見られます。発作後は意識がもうろうとします。
- 欠神発作(けっしんほっさ): 数秒〜数十秒間、突然動作が止まり、ボーッとする発作です。本人は発作中の記憶がありません。
- ミオクロニー発作: 意識は保たれたまま、手足の筋肉が一瞬「ピクッ」と収縮します。
焦点起始発作
脳の一部から異常放電が始まる発作です。症状は、異常放電が起こる脳の部位によって異なります。
-
- 焦点意識保持発作(旧:単純部分発作): 意識は保たれます。手足のつっぱりやけいれん、光が見える、吐き気がするなど様々です。
- 焦点意識減損発作(旧:複雑部分発作): 意識が低下し、反応が鈍くなります。口をもぐもぐさせる、歩き回るなどの無目的な行動が見られます。
- 焦点起始両側強直間代発作: 焦点起始発作から異常放電が脳全体に広がるタイプです。
てんかんの診断と治療
てんかんが疑われる場合、専門医による正確な診断と適切な治療が不可欠です。
診断方法
てんかんの診断は、主に問診、脳波検査、画像検査を組み合わせて行われます。
-
- 問診: 最も重要な情報です。発作の状況、症状、既往歴などを詳しく聞き取ります。発作の様子を撮影した動画は診断の大きな助けになります。
- 脳波検査: 頭皮に電極を貼り、脳の電気活動を記録します。てんかん特有の異常な脳波(てんかん性異常波)の検出が目的です。
- 画像検査(CT、MRI): 脳腫瘍や脳卒中の痕跡など、脳の構造的な異常の有無を調べます。特に大人のてんかんでは原因特定のために重要です。
治療方法
てんかん治療の目標は、発作を抑制し、患者が安心して社会生活を送れるようにすることです。
-
- 薬物療法: 治療の第一選択です。抗てんかん薬を適切に服用することで、約7割の人は発作を抑制できるとされています。自己判断での減薬や中断は重い発作を誘発する危険があるため、必ず医師の指示に従ってください。
- 外科治療: 薬で発作を抑制できない難治性てんかんの一部が対象です。異常放電の原因部位が特定でき、切除しても重い後遺症が残らない場合に検討されます。
- 食事療法: ケトン食療法などがありますが、主に小児の難治性てんかんで行われる治療法です。
てんかんと仕事|職場での伝え方と配慮
てんかんがあっても、多くの人が様々な職種で活躍しています。ここでは、仕事選びや職場でのコミュニケーションについて詳しく解説します。
仕事選びで考慮すべき点
発作が起きた際に本人や周囲に危険が及ぶ可能性のある職種は、法律や安全規定で就業が制限される場合があります。
-
- 自動車の運転を伴う業務(職業ドライバーなど)
- 高所での作業
- 危険な機械の操作
- プールの監視員など、他者の安全に直接関わる業務
これら以外の多くの職種では、問題なく働くことが可能です。自分の症状や発作の頻度を理解し、主治医とも相談しながら、安全に働ける環境を選ぶことが重要です。
職場に病状を伝えるメリット・デメリット
職場に病状を伝えるか(オープン就労)伝えないか(クローズ就労)は、大きな決断です。それぞれのメリット・デメリットを理解して判断しましょう。
-
- 発作時に適切な対応をしてもらえる安心感がある
- 通院や体調不良への配慮(休暇取得など)を得やすい
- 業務内容や量の調整など「合理的配慮」を求められる
- 障害者雇用枠での応募が可能になる
- 病気に対する偏見や誤解を受ける可能性がある
- 業務内容やキャリアパスで意図しない制限を受ける懸念
- プライベートな情報を開示することへの心理的負担
病状を伝える際のポイントと具体例
伝えることを決めた場合、正しい理解と協力を得るためには準備が大切です。信頼できる上司などに、以下の点を具体的に説明しましょう。
-
- 病名: 「てんかん」という病名
- 発作の症状と頻度: 「私の発作は、数分間ボーっとして反応がなくなるタイプで、頻度は年に1回あるかないかです」
- 発作の誘因: 「睡眠不足が続くと起きやすいので、生活リズムに気をつけています」
- 発作時の希望する対応: 「もし発作が起きたら、危険なものから遠ざけて、静かな場所で休ませてください。数分で収まります」
- 業務への影響: 「通常時の業務遂行に支障はありません。服薬で発作は安定してコントロールできています」
このように客観的な事実を伝えることで、相手の漠然とした不安を取り除き、具体的な協力をお願いしやすくなります。
病状を伝える際のポイントと具体例
伝えることを決めた場合、正しい理解と協力を得るためには準備が大切です。信頼できる上司などに、以下の点を具体的に説明しましょう。
-
- 病名: 「てんかん」という病名
- 発作の症状と頻度: 「私の発作は、数分間ボーっとして反応がなくなるタイプで、頻度は年に1回あるかないかです」
- 発作の誘因: 「睡眠不足が続くと起きやすいので、生活リズムに気をつけています」
- 発作時の希望する対応: 「もし発作が起きたら、危険なものから遠ざけて、静かな場所で休ませてください。数分で収まります」
- 業務への影響: 「通常時の業務遂行に支障はありません。服薬で発作は安定してコントロールできています」
このように客観的な事実を伝えることで、相手の漠然とした不安を取り除き、具体的な協力をお願いしやすくなります。
もし職場で発作が起きたら?周囲ができる対応
病状を伝える際のポイントと具体例
伝えることを決めた場合、正しい理解と協力を得るためには準備が大切です。信頼できる上司などに、以下の点を具体的に説明しましょう。
-
- 病名: 「てんかん」という病名
- 発作の症状と頻度: 「私の発作は、数分間ボーっとして反応がなくなるタイプで、頻度は年に1回あるかないかです」
- 発作の誘因: 「睡眠不足が続くと起きやすいので、生活リズムに気をつけています」
- 発作時の希望する対応: 「もし発作が起きたら、危険なものから遠ざけて、静かな場所で休ませてください。数分で収まります」
- 業務への影響: 「通常時の業務遂行に支障はありません。服薬で発作は安定してコントロールできています」
このように客観的な事実を伝えることで、相手の漠然とした不安を取り除き、具体的な協力をお願いしやすくなります。
もし職場で発作が起きたら?周囲ができる対応
てんかんのある人が職場で発作を起こした際、周囲の冷静で適切な対応が重要です。以下のポイントを参考にしてください。
発作時の基本的な対応
てんかん発作は、通常数分以内に自然に治まることが多く、救急搬送が必要なケースは限られます。以下の対応が基本です。
-
- 安全確保: 転倒によるケガや、周囲の物にぶつかる危険を避けるため、周囲の物をどける。必要であれば床に寝かせる。
- 身体を押さえない: けいれんしていても無理に身体を押さえつけない。
- 口に物を入れない: 舌を噛まないようにと口に物を入れるのは逆効果で危険。
- 経過観察: 発作の様子や時間を観察し、あとで本人や医療機関に伝えられるようにする。
- 衣服をゆるめる: 呼吸を助けるため、ネクタイや襟元をゆるめる。
発作後は、しばらく混乱したりぼんやりした状態が続くことがあります。声をかけて安心させ、必要に応じてそっと付き添いましょう。
発作後は、しばらく混乱したりぼんやりした状態が続くことがあります。声をかけて安心させ、必要に応じてそっと付き添いましょう。
救急車を呼ぶべき状況
以下のような場合は、速やかに救急車を呼んでください。
-
-
- 発作が5分以上続く(てんかん重積状態)
- 発作が繰り返し起きて、意識が戻らない
- 発作後に呼吸が苦しそう、顔色が悪い
- けがをして出血がある
-
- 水の中で発作が起きた(溺水の可能性)
てんかん発作に慣れていない場合は、迷わず119番通報して相談することが重要です。
てんかんのある人が利用できる福祉サービス
てんかんのある方が安心して暮らし、働くためには、福祉制度や支援を上手に活用することが大切です。
障害者手帳(精神障害者保健福祉手帳)
一定の条件を満たす場合、「精神障害者保健福祉手帳」の交付を受けることができます。等級(1~3級)に応じて、以下のような支援を受けられます。
-
- 税制上の優遇(所得税・住民税の控除など)
- 公共料金の割引(携帯電話、電車・バスなど)
- 就労支援サービスの利用(就労移行支援、就労継続支援など)
- 障害者雇用枠での就職活動
自立支援医療(精神通院医療)
てんかんで継続的に通院している場合、医療費の自己負担割合を軽減する「自立支援医療」の対象になります。申請により、通院治療にかかる医療費(診察、薬代など)が原則1割負担となります。
障害年金
発作による就労制限や日常生活への支障が大きい場合、障害年金を受給できる可能性があります。症状や生活状況に応じて、等級(1~3級)が決定されます。
その他の支援
自治体によっては、相談支援や生活支援などのサービスを受けられる場合もあります。地域の障害福祉窓口や保健所に相談してみましょう。
まとめ|てんかんと共に、自分らしく生きるために
てんかんは、正しい知識と適切な治療によって、十分にコントロールできる病気です。発作があるからといって、自分の可能性をあきらめる必要はありません。大切なのは、自分の症状を理解し、必要な配慮を得ながら、安心して過ごせる環境を整えることです。
周囲の理解と協力も、てんかんのある人にとって大きな支えとなります。誰もが自分らしく働き、生きることができる社会を目指して、てんかんへの正しい理解が広がることを願っています。
