お役立ち情報 不安障害(社会不安障害、パニック障害、強迫性障害、PTSD) 働き方の知識 就労移行支援 就労継続支援(A型・B型) 相談先
不安障害で仕事が怖い・続かないときの対処法は?無理なく働くポイントを解説
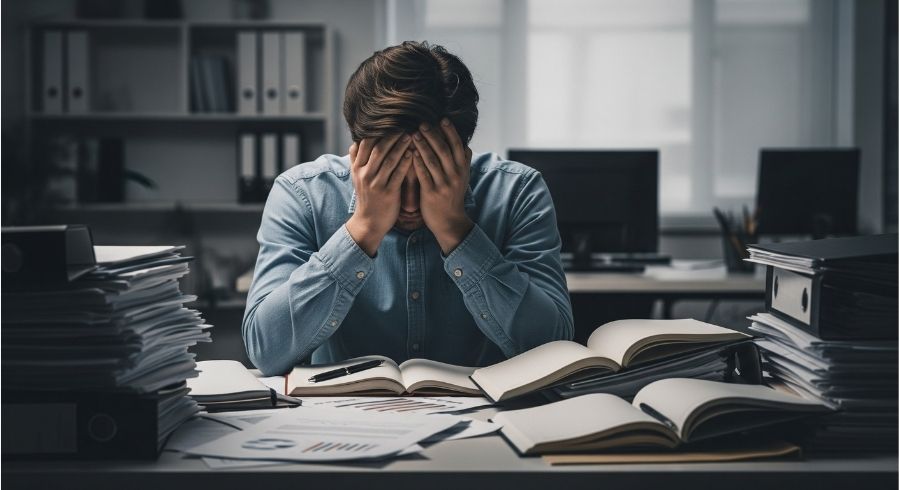
「朝、会社に行こうとすると、動悸や吐き気がして足がすくむ」「電話が鳴るだけで心臓が跳ね上がり、冷や汗が出る」「自分の仕事にミスがないか、何度確認しても安心できない」そんな強い不安から、仕事に行くのが怖い、仕事が長続きしないと悩んでいませんか?そのコントロールできないほどの恐怖心は、あなたの「気のせい」や「弱さ」が原因なのではなく、「不安障害」という治療可能な病気が背景にあるのかもしれません。
不安障害は、適切な治療と対処法を知ることで、症状を和らげ、ご自身に合った働き方を見つけることが可能です。この記事では、不安障害によって仕事が怖いと感じる原因から、具体的な対処法、休職という選択肢、そして無理なく働くための仕事探しのヒントまで、詳しく解説していきます。一人で抱え込まず、まずは解決への道筋を知ることから始めましょう。
仕事が怖いと感じる「不安障害」の主な種類と症状
「仕事が怖い」と感じる背景には、様々なタイプの不安障害が関係している可能性があります。ここでは、仕事の場面で特に困難を感じやすい代表的な不安障害を紹介します。
社交不安障害(SAD):人の視線や評価への強い恐怖
社交不安障害は、人から注目される場面や、他者から評価される状況に対して、過剰な不安や恐怖を感じる病気です。仕事には、こうした場面が数多く存在します。
仕事で困難を感じる場面の例:
- 会議や朝礼での発表
- 「うまく話せないのではないか」「変に思われるのではないか」という強い恐怖から、声が震えたり、頭が真っ白になったりする。
- 電話応対
- 相手の顔が見えない状況で、即座の対応を求められることに強いプレッシャーを感じる。
- 来客対応・名刺交換
- 初対面の人と話すことや、お茶を出す際に手が震えてしまうことへの恐怖から、来客対応を極力避けてしまう。
- 上司への報告・同僚との雑談
- 「こんなことを報告したら、能力が低いと思われるのではないか」と考え、コミュニケーションが取れず、孤立してしまう。
パニック障害:突然の発作と「また起きるのでは」という予期不安
パニック障害は、突然、理由もなく激しい動悸や息苦しさ、めまいなどのパニック発作に襲われる病気です。一度発作を経験すると、「またあの発作が起きたらどうしよう」という強い「予期不安」に悩まされるようになります。
仕事で困難を感じる場面の例:
- 通勤
- 満員電車やバス、渋滞中の車内など、「すぐに逃げ出せない」閉鎖的な空間で発作が起きやすい。そのため、公共交通機関を利用して通勤することが困難になる。
- エレベーターや会議室
- 職場内の閉鎖的な空間も恐怖の対象となりやすい。エレベーターに乗れなかったり、長時間の会議に出席できなかったりする。
- 予期不安による業務への支障
- 「いつ発作が起きるかわからない」という不安が常に頭から離れず、仕事に集中できない。
- 周囲の無理解
- 発作がないときは普段と変わらないため、症状のつらさが周囲に理解されにくく、「やる気がない」と誤解されてしまうことがある。
全般性不安障害(GAD):仕事や日常への過剰で慢性的な心配
全般性不安障害は、仕事、家庭、健康など、日常生活の様々な事柄に対して、過剰でコントロール不能な心配が慢性的に続く病気です。
仕事で困難を感じる場面の例:
- あらゆる業務への過剰な心配
- 「この仕事で失敗したらどうしよう」「締め切りに間に合わなかったらどうしよう」と、あらゆる可能性を考えて過度に心配し、なかなか仕事に着手できない。
- ミスへの極端な恐怖と確認行為
- 自分の仕事にミスがないか不安で、メールを送る前に何度も読み返したり、書類を何十回も確認したりするため、業務に非常に時間がかかってしまう。
- 常に緊張し、心身ともに疲弊
- 心配事が頭から離れないため、常に心身が緊張状態にある。その結果、慢性的な頭痛や肩こり、不眠、疲労感に悩まされ、仕事のパフォーマンスが低下する。
不安障害で仕事が怖い・続かないときの対処法
仕事への強い恐怖心や困難を乗り越えるためには、いくつかの対処法があります。一人で抱え込まず、専門家や周りの人の力を借りながら、一つずつ試していくことが大切です。
対処法1:まずは専門医による適切な治療を受ける
仕事への恐怖の根本原因である不安障害そのものを改善するためには、精神科や心療内科での専門的な治療が不可欠です。治療には、主に「薬物療法」と「精神療法」があります。
- 薬物療法
- SSRIなどの抗うつ薬や抗不安薬を用いて、不安や緊張を和らげ、心身のつらい症状をコントロールしやすくします。
- 精神療法(心理療法)
- 特に認知行動療法(CBT)は、不安障害に高い効果が証明されています。物事を過度に悲観的に捉えてしまう考え方の癖を見直したり、不安だからと避けている状況に少しずつ挑戦したり(エクスポージャー法)することで、不安に振り回されない心と行動を身につけていきます。
対処法2:生活習慣を整え、不安をコントロールする土台を作る
不安をコントロールするためには、心身の健康の土台となる生活習慣を整えることが非常に重要です。不規則な生活は、自律神経のバランスを乱し、不安を増強させます。
- 質の良い睡眠
- 睡眠不足は不安の大敵です。毎日決まった時間に寝て、決まった時間に起きることを心がけましょう。寝る前のスマートフォンやカフェインは避け、リラックスできる環境を整えましょう。
- バランスの取れた食事
- 1日3食、規則正しく食べることは、体内リズムを整え、精神の安定につながります。
- 適度な運動
- ウォーキングやジョギングなどの有酸素運動は、不安を軽減する効果があることが分かっています。無理のない範囲で、体を動かす習慣を取り入れましょう。
対処法3:職場に相談し、必要な配慮(合理的配慮)を求める
症状がつらい中で、これまで通りに働き続けるのは困難です。可能であれば、信頼できる上司や人事担当者、産業医などに相談し、無理なく働けるように環境を調整してもらう(合理的配慮を求める)ことも大切です。
合理的配慮の依頼例
- (社交不安障害の場合)
- 電話応対の業務を減らしてもらう、会議での発表は事前に資料を配布し、読み上げる形式にしてもらう。
- (パニック障害の場合)
- ラッシュ時を避けた時差出勤や、在宅勤務を許可してもらう。
- (共通)
- 業務量を一時的に減らしてもらう、休憩をこまめに取れるようにしてもらう、定期的な通院のための休暇を認めてもらう。
対処法4:緊張を和らげる自分なりのリラックス方法を見つける
仕事中に不安や緊張が高まってきたときに、自分でできるリラックス方法を知っておくと、大きな「お守り」になります。
- 腹式呼吸(深呼吸)
- ①椅子に座り、背筋を軽く伸ばす ②4秒かけて鼻から息を吸い、お腹を膨らませる ③8秒かけて口からゆっくりと息を吐き切り、お腹をへこませる。これを数回繰り返すと、心身がリラックスモードに切り替わります。
- 漸進的筋弛緩法
- 体の各パーツにぎゅーっと力を入れて、ストンと抜くことを繰り返す方法です。緊張と弛緩の感覚を味わうことで、体のこわばりをほぐします。
休職も大切な選択肢|無理せず治療に専念
どうしても仕事に行くのがつらい、症状が悪化して仕事にならないという場合は、無理して働き続けるのではなく、一時的に仕事を休んで治療に専念する「休職」も非常に重要な選択肢です。休職は「逃げ」や「負け」ではありません。回復し、また元気に働くための戦略的な「休息」です。
休職を考えるときは主治医に相談する
休職をしたいと思ったら、まずは主治医に相談しましょう。休職が必要だと判断されれば、会社に提出するための診断書を書いてもらえます。会社の人事制度や就業規則を確認し、上司や人事担当者に相談して、手続きを進めましょう。
休職中に利用できる経済的な支援制度
休職中の生活費が心配な方も多いと思いますが、健康保険に加入している会社員であれば、「傷病手当金」という制度を利用できる可能性があります。その他にも、治療費の負担を軽減する制度などがあります。
| 制度名称 | 制度の概要 |
|---|---|
| 傷病手当金 | 会社の健康保険の被保険者が、病気で連続4日以上働けず、給与が出ない場合に、給与のおおよそ2/3が最長で通算1年6ヶ月支給される。 |
| 自立支援医療制度 | 不安障害を含む精神疾患の通院治療にかかる医療費の自己負担が、原則1割に軽減される制度。 |
| 精神障害者保健福祉手帳 | 精神障害により、長期にわたり日常生活や社会生活に制約がある場合に交付される手帳。税金の控除や公共料金の割引などが受けられる。 |
| 障害年金 | 病気やケガで生活や仕事が制限される場合に支給される公的な年金。症状が重く、生活に大きな支障がある場合に支給対象となる可能性がある。 |
自分に合った仕事の探し方と相談できる支援機関
休職を経て復職する、あるいは新しい仕事を探す際には、これまでの経験を踏まえ、ご自身に合った働き方を見つけることが再発予防につながります。
自己分析で「不安のトリガー」と「安心できる環境」を考える
まずは、これまでの仕事経験を振り返り、自己分析を行うことが大切です。
-
- どんな業務や状況で、特に強い不安を感じましたか?(不安のトリガー)
- 逆に、比較的安心して、集中して取り組めた仕事はどんなものでしたか?
- 人間関係や職場環境で、何が一番ストレスでしたか?
- ご自分が仕事をする上で、譲れない条件は何ですか?(例:残業がない、在宅勤務が可能など)
ハローワークや就労支援機関などを活用する
自分に合った仕事探しや、働き方の相談を、一人で行う必要はありません。障害のある方の就労をサポートする専門機関を積極的に活用しましょう。
- ハローワーク(障害者専門窓口)
- 障害に関する知識を持つ専門の職員が、きめ細やかな就職支援を行ってくれます。
- 地域障害者職業センター
- 専門的な職業評価や職業準備支援など、より専門性の高いサポートを受けられます。
- 障害者就業・生活支援センター
- 就職の相談だけでなく、生活面での悩みも一体的に相談できる、地域に密着した身近な支援機関です。
- 就労移行支援事業所
- 一般企業への就職を目指す方が、最長2年間、職業訓練や職場探しなどのサポートを受けられる福祉サービスです。
- 就労継続支援事業所
- 現時点で一般企業で働くことが難しい方が、支援を受けながら、リハビリを兼ねて自分のペースで働くことができる福祉サービスです。
仕事への不安を抱えるあなたへ|就労継続支援B型事業所オリーブのご案内
「治療は続けているけれど、すぐに一般企業で働くのは怖い」「まずは働くことに慣れることから始めたい」「安心して通える場所で、仕事への自信を取り戻したい」そうした思いを抱えている方に、就労継続支援B型事業所オリーブという選択肢があります。
オリーブは、大阪、兵庫、京都、奈良の関西エリアで、不安障害などの障害のある方が、ご自身のペースで無理なく働ける場所を提供しています。一般就労のように高い成果を求められることはありません。まずは、安定して通所し、軽作業やデータ入力といったストレスの少ない仕事を通じて、働くことへの恐怖心を和らげ、生活リズムを整えることから始めます。
雇用契約を結ばないB型事業所なので、体調に合わせて「週に1日、1日1時間だけ」といった利用も可能です。経験豊富なスタッフが、あなたの不安な気持ちに常に寄り添い、一人ひとりの状態に合わせたサポートを行います。仕事は、フルタイムで働くことだけが全てではありません。あなたらしい働き方を見つけるための「リハビリの場」として、まずはオリーブを見学してみませんか。
