お役立ち情報 ジョブコーチ 就労支援サービス 就労移行支援 就労継続支援(A型・B型)
ジョブコーチ(職場適応援助者)とは?支援内容や種類・費用を解説
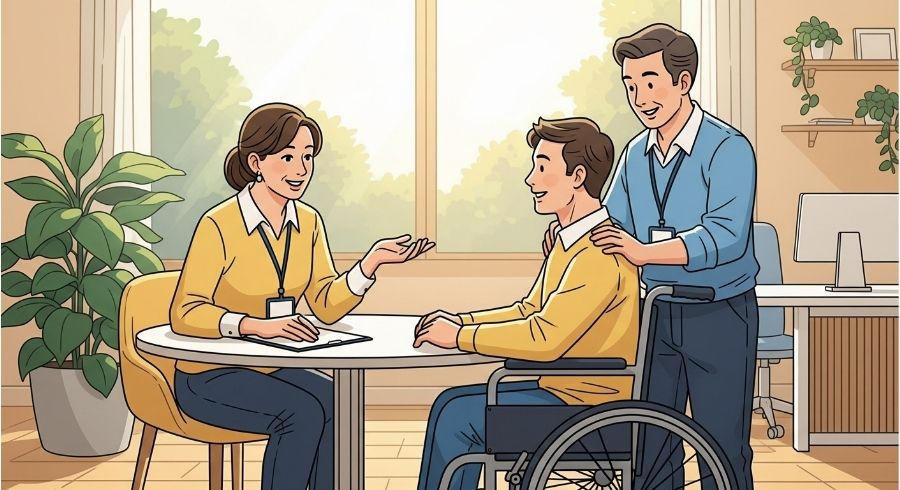
障害のある方が就職や転職をするとき、「新しい職場でうまくやっていけるだろうか」「仕事で分からないことがあったら、誰に聞けばいいんだろう」といった不安を感じるのは、ごく自然なことです。また、企業側も「どのように仕事を教えればよいか」「どんな配慮が必要なのだろう」と、戸惑うことがあるかもしれません。そんな、障害のあるご本人と企業の双方に寄り添い、職場への適応をサポートする専門家が「ジョブコーチ(職場適応援助者)」です。
この記事では、あなたの「職場での困った」を解決に導くジョブコーチについて、 具体的な支援内容から、3つの種類、利用方法や費用まで、分かりやすく解説します。さらに、ジョブコーチとよく似た他の就労支援サービスとの違いについてもご紹介します。一人で悩まず、専門家の力を借りることで、安心して働き続ける道が開けます。この記事が、あなたが自分らしく働き続けるための一助となれば幸いです。
ジョブコーチ(職場適応援助者)とは?職場定着をサポートする専門家
ジョブコーチとは、障害のある方が職場にスムーズに適応し、長く働き続けることができるように、専門的な支援を行う人のことです。正式名称を「職場適応援助者」と言い、厚生労働省が定める研修を修了した専門スタッフがその役割を担います。
ジョブコーチの最大の目的は、「職場定着」です。就職はゴールではなく、スタートです。実際に働き始めると、仕事の覚え方、同僚とのコミュニケーション、体調管理など、様々な壁にぶつかることがあります。ジョブコーチは、実際に職場を訪問し、障害のあるご本人と、上司や同僚といった企業側の両方に対して、それぞれの課題を解決するための具体的なアドバイスや働きかけを行います。ご本人と企業の間に立ち、円滑なコミュニケーションの「橋渡し役」を担う、心強いサポーターなのです。
ジョブコーチの支援内容|本人と企業の双方を支援
ジョブコーチの支援は、障害のある本人だけを対象にするものではありません。本人と企業、その両方に働きかけることで、障害のある方が働きやすい環境を職場全体で作り上げていくことを目指します。
障害のある本人への支援:仕事の進め方やコミュニケーションの助言
ご本人の課題に合わせて、マンツーマンで具体的な支援を行います。一人ひとりの特性や職場の状況を丁寧に分析し、オーダーメイドの支援計画を立ててくれるのが特徴です。
仕事の進め方に関する支援
-
- 複雑な作業を、一つひとつの簡単な工程に分解する(タスク分析)
- 写真や図を使った分かりやすい作業マニュアルを、会社と共同で作成する
- 優先順位のつけ方や、効率的な仕事の段取りについて助言する
対人関係・コミュニケーションに関する支援
-
- 上司への報告・連絡・相談のタイミングや方法を一緒に練習する
- 休憩時間や昼休みなどの同僚との過ごし方について助言する
- 自分の障害特性や、配慮してほしいことを上手に伝えるためのサポートを行う
健康管理や生活リズムに関する支援
-
- 安定して出勤するための、生活リズムの整え方について助言する
- 疲れやストレスのサインに早めに気づき、対処する方法を一緒に考える
具体的な支援事例(ケーススタディ)
例えば、発達障害(ASD)の特性があるAさんが、事務職として就職したケースを考えてみましょう。
【Aさんの課題】
-
- 集中力が高く丁寧な作業は得意だが、複数の口頭指示を一度に覚えるのが苦手で、指示が漏れてしまうことがある。
- 雑談が苦手で、休憩時間に同僚の輪に入れず、孤立感を感じている。
【ジョブコーチの支援】
-
- アセスメント(評価): ジョブコーチがAさんの職場を訪問し、実際の仕事の様子やコミュニケーションの取り方を観察します。
- 本人への支援: メモ帳を常に携帯し、指示を受けたら復唱して確認する練習を一緒に行います。休憩時間の過ごし方については、「無理に輪に入る必要はなく、読書など自分の好きなことをしてリラックスする時間として使って良い」と助言し、不安を軽減します。
- 企業への支援: Aさんの同意を得て、上司に「重要な指示や複数の指示がある場合は、口頭だけでなく、チャットや箇条書きのメモでも伝えてほしい」と、具体的な指示の出し方を提案します。
このような支援を通じて、Aさんの仕事上のミスが減り、精神的な負担も軽減され、安心して働き続けられるようになります。
企業への支援:障害特性に合わせた関わり方のアドバイス
ジョブコーチは、障害のある方を雇用する企業に対しても、専門的な立場から助言や情報提供を行います。
障害特性や配慮事項に関する情報提供
- ご本人の同意のもと、障害特性や、それによって生じる可能性のある困難について、上司や同僚に分かりやすく説明します。
仕事の教え方や関わり方に関する助言
- 「指示は具体的、かつ一つずつ出す」「曖昧な表現は避ける」など、本人が理解しやすい指示の出し方をアドバイスします。
職場環境の改善に関する提案
- 集中しやすいようにパーテーションを設置する、静かな席に配置するなど、物理的な環境調整を提案します。
社内の理解促進と支援体制構築
-
- 本人を日常的にサポートしてくれる職場の同僚(ナチュラルサポーター)の育成を支援します。
企業がジョブコーチ支援を利用するメリット
企業側にとっても、ジョブコーチの活用は大きなメリットがあります。人材の早期戦力化と定着率の向上: 専門家によるサポートで、障害のある従業員が早期に業務に適応し、離職を防ぐことができます。OJT(職場内訓練)の負担軽減: どのように仕事を教えればよいかという企業の負担が軽減され、効率的な人材育成が可能になります。職場全体の意識改革: 障害への理解が深まり、多様な人材が活躍できる職場環境(ダイバーシティ&インクルージョン)の推進につながります。助成金の活用: 訪問型・企業在籍型のジョブコーチ支援を利用する際に、一定の要件を満たせば「障害者雇用安定助成金(障害者職場適応援助コース)」の対象となる場合があります。
ジョブコーチを中心とした連携支援体制
ジョブコーチは一人で支援を完結させるのではなく、様々な立場の人々と連携する「チーム支援」の調整役を担います。安定した職場定着は、ご本人と企業を中心とした、多角的なサポートによって実現します。
-
- ご本人: 支援の主役です。自分の目標や課題について、ジョブコーチに主体的に相談することが大切です。
- 企業(上司・同僚): 最も身近な支援者です。ジョブコーチは、上司や同僚が本人の特性を理解し、日常的にサポートできる「ナチュラルサポーター」となれるよう働きかけます。
- 家族: 安定した職業生活の土台となる、生活面の重要なサポーターです。本人の同意のもと、ジョブコーチが家族と連携し、生活リズムの安定などに向けた助言を行うこともあります。
- 主治医: 本人の健康状態を医学的に把握する専門家です。本人の同意のもと、ジョブコーチが主治医と連携し、病状に配慮した働き方について情報を共有することがあります。
- 地域の支援機関(就労支援事業所など): 就職前から本人を支えてきた機関です。本人の得意なことや苦手なことなどの情報をジョブコーチと共有し、一貫したサポートを提供します。
ジョブコーチの3つの種類と特徴
ジョブコーチには、その所属先によって「配置型」「訪問型」「企業在籍型」の3つの種類があります。
| ジョブコーチの種類 | 所属先 | 特徴 |
|---|---|---|
| 配置型ジョブコーチ | 地域障害者職業センター | ・公的機関に所属するジョブコーチ ・地域のハローワークや支援機関との連携が強い ・支援の質のスタンダードとなる役割を担う |
| 訪問型ジョブコーチ | 就労支援事業所、社会福祉法人など | ・国からの認定を受けた民間のジョブコーチ ・普段から利用している事業所のスタッフが担当する場合もあり、安心感が得やすい |
| 企業在籍型ジョブコーチ | 障害者を雇用する企業 | ・障害のある方と同じ会社に所属するジョブコーチ ・日常的にきめ細やかな支援が受けられる ・障害者雇用に積極的な企業に配置されている |
ジョブコーチ支援の利用方法と具体的な流れ
実際にジョブコーチの支援を利用したい場合、どのように手続きを進めればよいのでしょうか。
利用の申し込み方法と支援計画の作成
-
- 相談: まずは、お近くの地域障害者職業センターに相談するのが基本です。ハローワークや、通っている就労支援事業所などを通じて相談することもできます。
- 支援計画の作成: 地域障害者職業センターの担当者が、本人、企業、そして場合によっては主治医や家族からも話を聞き、それぞれの課題やニーズを整理します。その上で、具体的な支援目標や支援内容、期間などを盛り込んだ「職場適応援助計画」を作成します。
段階的な支援の具体的な流れと期間
計画に基づき、ジョブコーチが職場を定期的に訪問し、支援を開始します。支援期間は一人ひとりの状況によりますが、通常1〜8ヶ月程度です。支援は、状況に合わせて徐々に頻度を減らしていく「フェイディング」という考え方で行われます。
-
- 支援導入期(開始~2ヶ月程度): ほぼ毎日~週に数回訪問します。本人への仕事の進め方の直接的な支援や、企業への関わり方のアドバイスが中心です。
- 支援移行期(3~5ヶ月程度): 訪問頻度を週に1回程度に減らしていきます。本人が主体的に行動できるよう促し、上司や同僚がサポート役を引き継げるように働きかけます。
- フォローアップ期(6ヶ月目以降): 月に1回程度の訪問や連絡に移行し、職場に定着できているかを確認します。問題が生じた場合は、再度集中的な支援を行うこともあります。
利用にかかる費用は原則無料
ジョブコーチによる支援は、国の障害者雇用施策の一環として行われています。そのため、障害のあるご本人や、支援を受ける企業が費用を負担することは、原則ありません。
ジョブコーチ以外の主な就労支援サービス
ジョブコーチは、主に就職後の「定着」を支えるサービスですが、それ以外にも障害のある方の「働く」を支える様々なサービスがあります。
就労定着支援(生活面のサポート)
就職後6ヶ月を経過した方を対象に、就労に伴う生活面の課題(体調管理、金銭管理など)について、最長3年間、定期的な面談などを通じてサポートしてくれる福祉サービスです。ジョブコーチが職場での業務遂行に重点を置くのに対し、こちらは生活全般の安定を支えることで、長く働き続けることを目指します。
障害者トライアル雇用(お試しの雇用)
企業が障害のある方を、原則3ヶ月間の有期雇用で雇い入れ、その間に適性や業務遂行能力を見極め、常用雇用への移行を目指す制度です。
就労移行支援・就労継続支援(就職準備や働く練習)
-
- 就労移行支援: 一般企業への就職を目指す方が、働くために必要な知識やスキルを身につけるための訓練を、最長2年間受けられる福祉サービスです。
- 就労継続支援: すぐに一般企業で働くのが難しい方が、支援を受けながら実際に働き、工賃を得ることができる福祉サービスです。A型(雇用型)とB型(非雇用型)があります。
就職前の準備や働く練習なら 就労継続支援B型事業所オリーブへ
ジョブコーチは、就職後のあなたを支える心強い味方です。しかし、「そもそも就職活動をする自信がない」「働くこと自体にブランクがあって不安だ」という方もいらっしゃるかもしれません。
本格的な就職を目指す前の、準備や練習の場として、私たち「就労継続支援B型事業所オリーブ」があります。オリーブは、大阪、兵庫、京都、奈良の関西エリアで、障害のある方が、ご自身のペースで「働く」ためのリハビリテーションを行う場所です。雇用契約を結ばないB型事業所なので、週1日・1日1時間といった短時間からスタートでき、体調に合わせて無理なく通うことができます。
データ入力や軽作業などを通じて、生活リズムを整え、集中力や持続力を養い、支援員との「報・連・相」を練習するなど、就職に必要な基礎的な力を、安心して身につけていくことができます。将来、一般企業で働き、ジョブコーチの支援を受けながら活躍するために。まずはその土台作りを、オリーブで始めてみませんか。ご見学やご相談は、いつでもお待ちしております。
