お役立ち情報 受診と診断 診断基準(DSM-5, ICD-10)
ICD-10とは?精神疾患の分類やDSMとの違いをわかりやすく解説
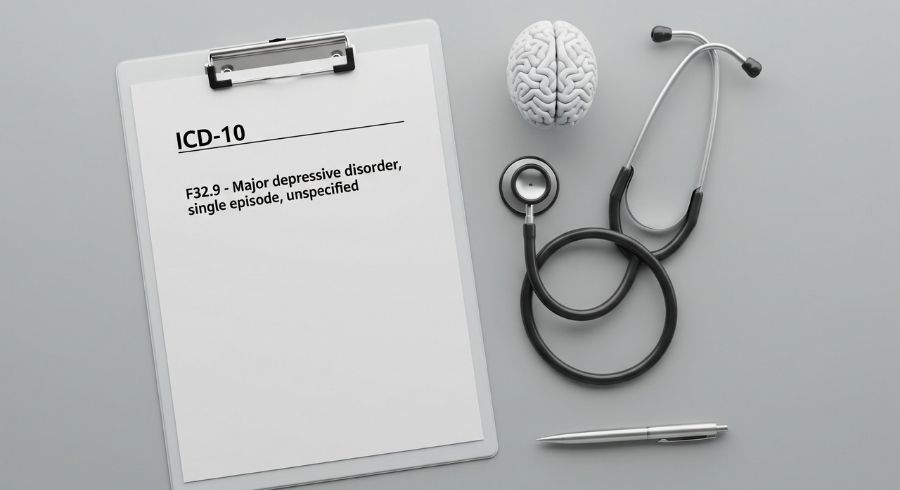
精神科や心療内科の診断書、あるいは障害福祉サービスの申請書類などで、「ICD-10」という言葉や、「F84.0」といった謎のコードを目にしたことはありませんか?「これはいったいどういう意味で、自分の生活にどう関係するのだろう?」と、不安や戸惑いを感じた方も多いのではないでしょうか。
この記事では、医療や福祉の現場で広く使われている国際的な疾病分類「ICD-10」について、その目的や、もう一つの有名な診断基準である「DSM-5」との違い、そして精神疾患がどのように分類されているのかを、分かりやすく解説します。公的な書類で使われる「ものさし」について正しく知ることは、ご自身の状況を客観的に理解し、必要な支援につながるための第一歩です。
ICD-10とは?WHOが定める国際的な疾病分類
ICD-10とは、WHO(世界保健機関)が作成した「国際疾病分類 第10版(International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems 10th Revision)」の略称です。その名の通り、ありとあらゆる病気やけが、死因などを、一定の基準に基づいて分類し、アルファベットと数字を組み合わせたコードを割り振ったものです。この国際的な分類があることで、国や地域、時代が異なっても、同じ基準で健康に関するデータを比較・分析することができます。ICDは、世界の健康状態をリアルタイムで把握し、感染症対策や生活習慣病予防など、公衆衛生を向上させるために不可欠な、世界共通の「ものさし」なのです。
ICD-10の主な用途:医療統計から福祉サービスの利用まで
ICD-10は、私たちの生活の様々な場面で、重要な役割を果たしています。
- 公衆衛生統計
- 国や地域の死亡率や、特定の病気の罹患率などを集計・分析するために使われます。例えば、ある地域で特定の感染症(例:A37 百日せき)の報告が増えれば、迅速な対策を講じることができます。また、がん(C00-D48)や生活習慣病(I10 高血圧性心疾患など)のデータを分析し、国の医療政策や予算配分を決める際の基礎資料にもなります。
- 医療機関での記録・管理
- 電子カルテの記録や、病院内での情報管理にICD-10のコードが用いられます。これにより、医療情報の標準化が進み、医療の質向上につながります。
- 診断書の作成と福祉サービスの利用
- 医師が発行する診断書には、ICD-10に基づいた病名とコードが記載されます。このコードは、障害者手帳や障害年金、自立支援医療といった各種の福祉サービスを申請する際の公的な証明として、非常に重要な意味を持ちます。
- 診療報酬(レセプト)
- 医療機関が、健康保険組合などに医療費を請求する際の明細書(レセプト)の作成にも、ICD-10のコードが使われます。正しいコードがなければ、医療費の請求ができないため、医療機関の運営においても必須のツールです。
ICD-10とDSM-5の違い
精神疾患の分野では、ICD-10のほかに、アメリカ精神医学会が作成した「DSM-5」という診断基準も広く用いられています。この二つは、どのような違いがあるのでしょうか。
ICD-10は「全疾患」を対象とする公衆衛生のための分類
ICD-10は、精神疾患だけでなく、感染症や新生物(がん)、循環器系の疾患、骨折などのケガまで、あらゆる傷病を網羅した、非常に包括的な分類体系です。その目的は、前述の通り、主に公衆衛生上の統計や、行政手続きのために用いられることです。世界中の誰もが使えるように、比較的簡潔な記述で定義されています。
DSM-5は「精神疾患」の臨床診断に特化したマニュアル
一方、DSM-5(精神疾患の診断・統計マニュアル 第5版)は、その名の通り「精神疾患」の診断に特化したマニュアルです。DSM-5の最大の特徴は、それぞれの疾患について、具体的な「操作的診断基準」が詳細に定められている点です。例えば、「A、B、Cの症状のうち、Aが5つ以上、Bが2つ以上存在し、それが6ヶ月以上持続している場合に診断する」といったように、非常に明確な基準が示されています。これにより、医師による診断のばらつきを減らし、診断の信頼性を高めることを目指しています。臨床現場の医師が、患者さん一人ひとりの状態をより正確に診断するための手引きとして、使いやすいように設計されているのが特徴です。
実際の医療現場では、医師はDSM-5の基準を用いて詳細な診断を行い、診断書などの公的な書類にはICD-10の病名とコードを記載する、という形で両者を併用するのが一般的です。
| ICD-10 | DSM-5 | |
|---|---|---|
| 作成機関 | 世界保健機関(WHO) | アメリカ精神医学会(APA) |
| 対象範囲 | 全ての傷病 | 精神疾患のみ |
| 主な使用目的 | 統計、行政手続き、保険請求 | 臨床現場での診断 |
| 特徴 | 包括的、公衆衛生志向 | 詳細な診断基準、研究志向 |
ICD-10の分類内容|精神疾患は「Fコード」
ICD-10では、全ての傷病がアルファベットと数字を組み合わせたコードで分類されています。その中で、「第5章:精神および行動の障害」に分類される疾患には、頭文字に「F」がつくコードが割り当てられています。ここでは、Fコードの主な分類を紹介します。
F00-F09:症状性を含む器質性精神障害
脳の損傷や機能不全、あるいは身体疾患が原因で二次的に引き起こされる精神障害のグループです。「器質性」とは、脳に物理的な原因があることを意味します。
- F00
- アルツハイマー病の認知症
- F01
- 血管性認知症
- F05
- せん妄(急性の意識の混濁や注意力の低下など)
- F06
- 脳の損傷などによる、その他の精神障害(器質性気分障害など)
F10-F19:精神作用物質による精神および行動の障害
アルコールや違法薬物、処方薬などの使用によって引き起こされる、依存症や中毒などの精神障害のグループです。
- F10
- アルコール使用による精神および行動の障害
- F17
- タバコ使用による精神および行動の障害
F20-F29:統合失調症、統合失調症型障害および妄想性障害
幻覚、妄想、まとまりのない思考や発言などを主な症状とする、精神病性の障害のグループです。
- F20
- 統合失調症
- F22
- 持続性妄想性障害
- F25
- 統合失調感情障害
F30-F39:気分[感情]障害(うつ病や双極性障害など)
気分の落ち込み(うつ状態)や高揚(躁状態)といった、気分の変動を主な特徴とする障害のグループです。
- F31
- 双極性感情障害(躁うつ病)
- F32
- うつ病エピソード
- F33
- 反復性うつ病性障害
F40-F48:神経症性障害、ストレス関連障害および身体表現性障害
過剰な恐怖や心配、それに関連した身体症状や行動上の問題が特徴となる障害のグループです。
- F40
- 恐怖症性不安障害(広場恐怖症、社交恐怖症など)
- F41
- その他の不安障害(パニック障害、全般性不安障害など)
- F42
- 強迫性障害
- F43
- 重度ストレスへの反応および適応障害
F50-F59:生理的障害および身体的要因に関連した行動症候群
食事や睡眠、性機能といった、生理的な機能に関連する障害のグループです。
- F50
- 摂食障害(神経性無食欲症、神経性大食症など)
- F51
- 非器質性睡眠障害(不眠症、過眠症など)
F60-F69:成人のパーソナリティおよび行動の障害
青年期またはそれ以前から認められる、深く根付いた持続的な行動パターンが、社会生活への不適応を引き起こしている状態です。
- F60
- 特異的パーソナリティ障害(妄想性、境界性など)
- F63
- 習慣および衝動の障害(病的賭博、放火癖など)
F70-F79:精神遅滞(知的障害)
発達期において、知的機能や適応機能の発現が妨げられた状態です。ICD-11では「知的能力障害群」という名称に変更されています。
F80-F89:心理的発達の障害(発達障害など)
中枢神経系の生物学的な成熟と密接に関連した機能の発達に、遅れや偏りが生じる障害のグループです。
- F80
- 会話および言語の特異的発達障害
- F81
- 学習能力の特異的発達障害(読字障害、書字障害など)
- F84
- 広汎性発達障害(自閉症、アスペルガー症候群など)
F90-F98:小児期および青年期に通常発症する行動および情緒の障害
主に小児期から青年期にかけて発症する障害のグループです。
- F90
- 多動性障害(ADHDなど)
:
- F94
- 小児期の社会機能の特異的障害(選択性かん黙など)
ICD-11への移行について
現在、WHOはICD-10を約30年ぶりに改訂した「ICD-11」を公表しており、世界的に移行が進められています。
ICD-10からの主な変更点
ICD-11では、最新の医学的知見に基づき、様々な変更が加えられています。精神疾患の領域では、DSM-5の分類とかなり近くなるよう調整されているのが大きな特徴です。
- 双極性障害の分類
- ICD-10では明確でなかったI型・II型の区別が、DSM-5と同様に導入されました。
- 統合失調症の亜型分類の廃止
- ICD-10にあった「妄想型」「破瓜型」といった亜型分類が廃止され、よりシンプルな診断体系になりました。
- 複雑性PTSDの追加
- 従来のPTSDに加え、長期的なトラウマ体験(児童虐待など)による、より複雑な症状を示す「複雑性PTSD」が新たに追加されました。
- 発達障害の分類変更
- ICD-10の「広汎性発達障害」が、DSM-5と同様に「自閉スペクトラム症」に名称変更・統合され、症状の多様性がより反映されるようになりました。
日本での本格的な導入はこれから
ICD-11は2022年1月に国際的に発効しましたが、日本で公式に導入されるには、日本語への翻訳や、関連する社会保障制度・法律の改定、医療機関のシステム更新など、様々な準備が必要です。そのため、医療現場や行政手続きで本格的に使われるようになるまでには、まだしばらく時間がかかると考えられています。
ICD-10の診断名と福祉サービスの関係
ICD-10の診断名は、ご自身やご家族が、障害者手帳の取得や、様々な福祉サービスを利用するために不可欠なものです。
診断名が福祉サービス利用の「鍵」となる
障害者手帳の申請や、障害年金の請求、自立支援医療の利用など、多くの公的な福祉サービスでは、申請の際に医師の診断書の提出が求められます。この診断書に記載されるICD-10コードが、あなたがそのサービスの対象となる障害の状態にあることを示す、公的な証明となります。例えば、「精神障害者保健福祉手帳」を申請する場合、診断書に記載されたFコードと症状の重さによって、手帳の等級(1級~3級)が判断されます。この等級によって、受けられるサービスの範囲や税金の控除額などが変わってきます。
「診断」がもたらすメリットと、向き合い方
病名が確定すること(診断)は、つらいことばかりではありません。
-
- ご自身の状態を客観的に理解できる:「自分の性格が悪いからだ」と責めるのではなく、「病気の症状なのだ」と客観的に捉え、適切な対処法を学ぶことができます。
- 周囲の理解を得やすくなる:ご家族や職場などに、ご自身の困難さを具体的に説明しやすくなります。
- 同じ悩みを持つ仲間とつながれる:同じ診断名を持つ人々の自助グループなどに参加し、経験を分かち合うことで、孤立感を和らげることができます。
- 必要な支援につながれる:前述の通り、福祉サービスを利用し、経済的な負担や生活上の困難を軽減することができます。
診断名は、あなたという人間を縛るレッテルではありません。それは、あなたが抱える困難さを社会が理解し、必要な支援を提供する上での「共通言語」であり、あなたの権利を守るための「鍵」なのです。
診断名に応じたサポートなら|就労継続支援B型事業所オリーブへ
この「鍵」を使うことで、これまで一人で抱えていた問題が、解決可能な課題へと変わっていくことがあります。就労継続支援B型事業所オリーブでは、医師の診断に基づき、障害のある方がその人らしいペースで働くためのサポートを提供しています。雇用契約を結ばないため、ノルマや時間に追われることなく、データ入力や軽作業などの仕事を通じて、働く自信と生活リズムを取り戻すことができます。
診断を、悲観的に捉えるのではなく、自分を知り、新しい一歩を踏み出すためのきっかけとしてみませんか。オリーブでは、専門の相談員がいつでもあなたのお話をお伺いします。
