お役立ち情報 受診と診断 診断基準(DSM-5, ICD-10)
DSM-5とは?精神疾患の診断で使われる分類や目的・ICDとの違いを解説
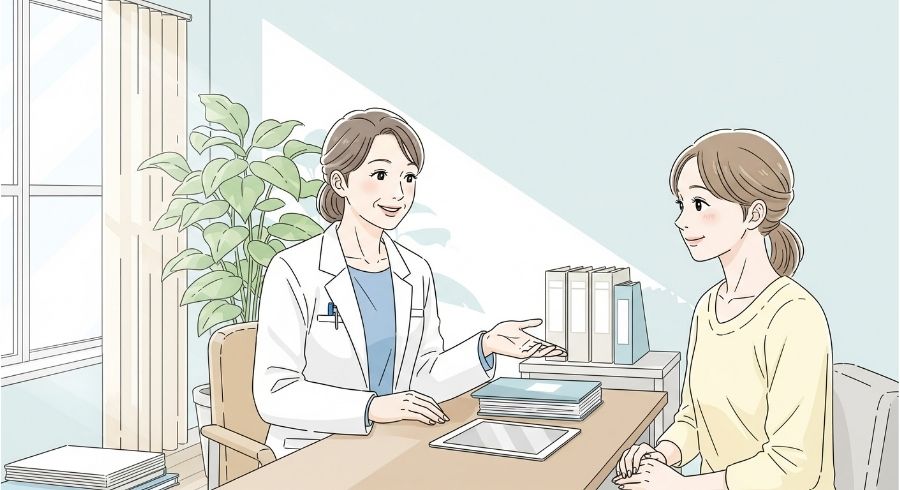
精神科や心療内科を受診したり、精神障害に関する情報を調べたりする中で、「DSM-5」という言葉を目にしたことがあるかもしれません。「自分や家族が抱える困難さの正体は何だろう?」「DSM-5とは一体何なのか?」「ICD-10という言葉も聞くが、何が違うのか?」など、様々な疑問が浮かぶことでしょう。
この記事では、精神疾患の診断において世界中で広く用いられている診断基準「DSM-5」について、その目的や、もう一つの国際的な分類である「ICD」との違い、そしてDSM-5で示されている主な精神疾患の分類について、分かりやすく解説します。専門家が用いる「共通のものさし」について知ることは、漠然とした不安を解消し、ご自身やご家族の状況を客観的に理解し、適切な支援へ繋がるための第一歩となります。
DSM-5とは 精神疾患の国際的な診断基準
DSM-5とは、精神疾患に関する診断基準・マニュアルの一つです。まずは、その基本的な役割と目的について見ていきましょう。
アメリカ精神医学会が作成した診断マニュアル
DSM-5は、アメリカ精神医学会(APA)が作成・発行している「精神疾患の診断・統計マニュアル 第5版(Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 5th Edition)」の略称です。1952年に初版が出版されて以来、精神医学の知見の蓄積とともに改訂が重ねられ、日本では2014年に最新版である第5版の日本語訳が出版されました。アメリカで作成されたマニュアルですが、精神科医療や臨床心理の現場では、世界中の専門家が診断の際に参照する、国際的な共通言語として広く用いられています。
DSM-IVからDSM-5への主な変更点
- 多軸診断の廃止
- DSM-IVで用いられていた、精神疾患、パーソナリティ障害、身体疾患などを異なる「軸」で評価する多軸診断システムが廃止され、よりシンプルな記述方法に整理されました。
- アスペルガー障害などの統合
- それまで「アスペルガー障害」「小児期崩壊性障害」などと別々に分類されていたものが、「自閉スペクトラム症(ASD)」という一つの診断名に統合されました。これは、症状の現れ方が明確に線引きできるものではなく、連続体(スペクトラム)として捉える方が実態に近いという考え方に基づいています。
- 新しい疾患概念の追加
- 「ためこみ症(ホーディング障害)」や「むちゃ食い症(過食性障害)」などが、独立した疾患単位として新たに追加されました。
診断の客観性と信頼性を高める目的
精神疾患の診断は、血液検査や画像検査のように、客観的な数値だけで判断することが困難です。そのため、かつては医師個人の経験や学派による考え方の違いから、同じ症状でも診断名が異なるという課題がありました。そこでDSMでは、各精神疾患について、どのような症状が、どれくらいの期間、どの程度存在すればその診断が下せるのか、という具体的な基準(操作的診断基準)を明確に定めています。これにより、診断のばらつきを減らし、客観性と信頼性を高めることがDSMの大きな目的です。医師が共通の基準を持つことで、より適切な治療方針を立てたり、研究の比較可能性を高めたり、必要な福祉的支援につなげたりすることが可能になるのです。
DSM-5とICD-10の違い
精神疾患の分類には、DSM-5のほかに、世界保健機関(WHO)が作成する「ICD」というもう一つの国際的な基準があります。この二つは、その目的と成り立ちが異なります。
DSM-5は精神疾患に特化した「診断マニュアル」
DSM-5は、その名の通り「精神疾患」の診断に特化したマニュアルです。それぞれの疾患について症状や経過、重症度などを細かく記述できるようになっており、主に臨床現場で医師が患者を診断する際に、より正確な判断を下すための手引きとして使いやすいよう設計されています。そのため、研究志向が強いという特徴もあります。
ICD-10は全ての傷病を網羅した「統計分類」
一方、ICD(疾病及び関連保健問題の国際統計分類)は、精神疾患だけでなく、感染症や新生物(がん)、骨折などのケガまで、あらゆる傷病を網羅した包括的な分類体系です。ICDの主な目的は、個々の臨床診断のためだけではなく、公衆衛生の観点から死因の統計を取ったり、医療費の保険請求(レセプト)を行ったり、公的な助成や福祉サービスを申請したりする際の行政手続きに用いることです。日本で障害者手帳や障害年金、自立支援医療などの申請書類に記載される病名は、このICDのコードが用いられます。
| DSM-5 | ICD-10 | |
|---|---|---|
| 作成機関 | アメリカ精神医学会(APA) | 世界保健機関(WHO) |
| 対象範囲 | 精神疾患のみ | 全ての傷病 |
| 主な使用目的 | 臨床現場での診断、研究 | 統計、行政手続き、保険請求 |
| 特徴 | 詳細な診断基準、研究志向 | 包括的、公衆衛生志向 |
臨床現場での併用と今後のICD-11への移行
実際の医療現場では、医師はDSM-5の基準を用いて詳細な診断評価を行い、診断書などの公的な書類にはICD-10の病名とコードを記載する、という形で両者を併用するのが一般的です。なお、WHOは既に新しい「ICD-11」を公表しており、日本でも順次移行が進められています。ICD-11はDSM-5の分類と整合性が高まるよう調整されており、国際的な診断基準の標準化が進んでいます。
DSM-5の主な分類
DSM-5では、数多くの精神疾患が、その特性によって22の大きなカテゴリーに分類されています。ここでは、その中から代表的なものをいくつか紹介します。
神経発達症群/神経発達障害群(発達障害)
発達の早期段階で発症し、脳機能の発達の偏りが原因で、個人的、社会的、学業的、職業的な機能に困難が生じる障害のグループです。
- 自閉スペクトラム症(ASD)
- 社会的コミュニケーションおよび対人関係の持続的な困難さと、限定された反復的な行動、興味、活動を特徴とします。
- 注意欠如・多動症(ADHD)
- 「不注意(集中困難、忘れっぽいなど)」と「多動性-衝動性(落ち着きがない、待てないなど)」を主な特徴とします。
- 知的発達症(知的障害)
- 全般的な知的機能(学習、問題解決など)と、日常生活や社会生活への適応機能の両方に制約がある状態です。
- 限局性学習症(SLD)
- 全般的な知的発達に遅れはないものの、「読む」「書く」「計算する」など特定の学習能力の習得と使用に著しい困難があります。
統合失調症スペクトラムおよび他の精神病性障害群
幻覚、妄想、まとまりのない思考や発言、ひどくまとまりのない異常な運動行動、意欲の欠如などの「陰性症状」のうち、一つ以上が認められる障害のグループです。
- 統合失調症
- 幻覚・妄想などの陽性症状や、感情の平板化・意欲減退といった陰性症状が6ヶ月以上持続し、学業や職業などの社会機能が著しく低下する状態です。
- 妄想性障害
- 「誰かに追跡されている」「配偶者が浮気をしている」といった、奇異ではない内容の妄想が1ヶ月以上持続する状態です。
双極性障害および関連障害群
気分の著しい高揚と活力に満ちた「躁状態」と、気分の落ち込みと活動性の低下を特徴とする「うつ状態」という、両極端な状態を繰り返す障害のグループです。
- 双極I型障害
- 社会生活に大きな支障をきたすほどの激しい「躁病エピソード」が少なくとも1回あることが特徴です。多くの場合、うつ病エピソードも経験します。
- 双極II型障害
- 入院するほどではない「軽躁病エピソード」と、生活への支障が大きい「うつ病エピソード」を繰り返すことが特徴です。
抑うつ障害群(うつ病など)
悲しみ、空虚感、易怒性(いかりっぽさ)といった抑うつ気分が持続し、思考や身体機能にも影響が及ぶ障害のグループです。
- うつ病(大うつ病性障害)
- ほとんど一日中続く抑うつ気分や、これまで楽しめていた活動への興味・喜びの著しい喪失といった症状が、2週間以上続く状態です。
- 持続性抑うつ障害
- より慢性的(成人で2年以上)に抑うつ気分が続く状態です。
- 月経前不快気分障害(PMDD)
- 多くの月経周期において、月経が始まる前の週に、著しい気分の落ち込みや不安、怒りっぽさなどが現れ、月経開始後には軽快する状態です。
不安症群/不安障害群(不安障害)
過剰な恐怖や心配、それに関連した回避行動が特徴となる障害のグループです。
- 社交不安障害(SAD)
- 他者から評価される可能性のある社交場面(人前で話す、食事をするなど)に対して、強い恐怖や不安を感じ、そうした状況を避けようとします。
- パニック障害
- 予期せぬパニック発作(突然の激しい動悸、息苦しさ、めまいなど)を繰り返し、また発作が起きるのではないかという強い予期不安や、発作に関連した行動の変化が生じる状態です。
- 全般不安障害(GAD)
- 仕事や健康、家庭など、日常生活における複数の出来事や活動について、制御することが難しい過剰な不安や心配が6ヶ月以上続く状態です。
診断基準の限界と自己診断の危険性
DSM-5は診断の信頼性を高める上で非常に有用ですが、万能ではありません。また、基準だけを頼りに自己判断することは大きなリスクを伴います。
DSM-5は「絶対」ではない
DSMは精神医学研究の進展を反映して定期的に改訂され、分類は変更され続けます。これは、現時点での科学的合意を示すものであり、絶対不変の真理ではないことを意味します。文化による症状の現れ方の違いや、正常な悲しみを病理化してしまうリスクなど、DSMの限界についても議論されています。
診断は必ず専門の医師が行うもの
精神疾患の診断は、DSM-5などの基準を参考にしつつも、生育歴、生活環境、ストレス要因、身体疾患の可能性なども含め、精神科や心療内科の専門医が総合的に判断して初めて下されます。例えば「気分が落ち込む」という一つの症状でも、うつ病、双極性障害、適応障害、あるいは甲状腺機能低下症といった身体疾患など、様々な可能性が考えられます。専門医は、こうした症状の似た他の疾患を除外する「鑑別診断」を行いますが、これは専門知識と豊富な経験がなければ不可能です。インターネット上の情報やセルフチェックは、あくまで医療機関に相談する「きっかけ」として捉え、それだけで結論を出さないようにしてください。誤った自己判断は、適切な治療の機会を逃したり、不必要な不安を招いたりする原因となります。
診断を、自分らしく働くための「鍵」に
医師による正式な診断は、適切な治療への第一歩であると同時に、あなたに合った働き方やサポートを見つけるための重要な手がかりです。診断を受け、自身の特性を客観的に理解することで、漠然とした「生きづらさ」の正体が明確になり、具体的な対策を立てられるようになります。診断は、あなたを縛るレッテルではなく、むしろ不要な自己否定から解放し、必要な支援を得るための「鍵」となり得るのです。この「鍵」を使うことで、障害者手帳の取得や、自立支援医療、障害年金といった様々な福祉サービスの利用につながり、経済的・心理的な負担を軽減できる可能性があります。
診断を受けた上で、「すぐに一般企業で働くのは不安」「まずは安心できる環境で働く練習をしたい」と感じている方もいるでしょう。
就労継続支援B型事業所オリーブでは、医師の診断に基づき、障害のある方がその人らしいペースで働くためのサポートを提供しています。雇用契約を結ばないため、ノルマや時間に追われることなく、データ入力や軽作業などの仕事を通じて、働く自信と生活リズムを取り戻すことができます。診断を悲観的に捉えるのではなく、自分を深く知り、新しい一歩を踏み出すためのきっかけとしてみませんか。オリーブでは、専門の相談員がいつでもあなたのお話をお伺いします。
