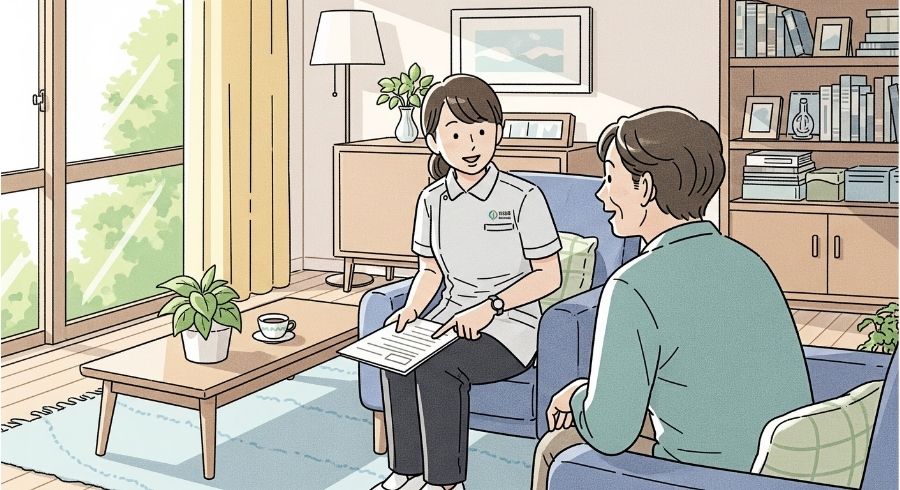
障害支援区分とは?障害福祉サービス利用のための認定制度
障害者総合支援法に基づくサービスの必要度を示す指標
障害支援区分とは、「その人が、どの程度の障害福祉サービスを必要としているか」を客観的に示すための指標です。 これは、障害のある方の多様な特性や心身の状態に応じ、適切な量のサービスを提供できるよう、「障害者総合支援法」という法律に基づいて定められた全国共通の基準です。 判定にあたっては、障害の種類や等級だけでなく、日常生活で「できること」「できないこと」、コミュニケーション能力、行動の状況、そして介護者や生活環境なども含めて、総合的に「サービスの必要度」が判断されます。
区分1から6までの6段階と非該当について
障害支援区分は、支援の必要性が低い「区分1」から、最も高い「区分6」までの6段階に分かれています。 数字が大きいほど、より多くの支援が必要な状態を示します。
- 区分1~6
- 障害福祉サービスのうち、特に身体介護などを必要とする「介護給付」の対象となります。
- 非該当
- 審査の結果、支援の必要性が比較的低いと判断された場合です。 「非該当」でも、就労訓練などを受ける「訓練等給付」は利用することが可能です。
支援の必要度:低い 区分1 < 区分2 < 区分3 < 区分4 < 区分5 < 区分6 高い
障害支援区分と障害者手帳の違い
障害支援区分と混同されがちなのが「障害者手帳」です。この二つは目的や根拠となる法律が異なる、別の制度です。
| 障害支援区分 | 障害者手帳 | |
|---|---|---|
| 目的 | 障害福祉サービスの必要度を判定するため | 障害があることを証明するため |
| 役割 | 利用できるサービスの種類や量を決める指標 | 税金の控除や各種割引などを受けるための証明書 |
| 根拠法 | 障害者総合支援法 | 身体障害者福祉法、精神保健福祉法、知的障害者福祉法 |
| 申請・認定 | 市区町村 | 都道府県・指定都市 など |
| 更新 | 原則3年ごとに必要 | 手帳の種類や障害の内容による(不要な場合も) |
障害者手帳を持つ方が、実際にホームヘルプなどのサービス利用を希望する際に、その必要度を判断するために申請するのが障害支援区分、という関係になります。
障害支援区分 認定手続きの流れを4ステップで解説
障害支援区分の認定を受けるための手続きは、主に4つのステップで進められます。
ステップ1:市区町村の窓口で相談・申請
まず、お住まいの市区町村の障害福祉担当窓口へ行き、障害福祉サービスの利用と障害支援区分の認定について相談し、申請を行います。 申請の際には、どのようなサービスを利用したいか、どんなことに困っているかを事前に整理しておくと、その後の手続きがスムーズに進みます。
【申請時に必要となる主なもの】
-
- 申請書(窓口で配布)
- 障害者手帳(所持している場合)
- マイナンバーが確認できる書類
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
ステップ2:認定調査員による聞き取り調査(アセスメント)
申請後、市区町村の認定調査員が自宅や入所施設などを訪問し、本人と家族などから心身の状況について聞き取り調査を行います。 この調査は「一次判定」の基礎となる重要なもので、全国共通の80項目の質問に沿って行われます。 質問内容は、移動や動作、身の回りの管理、コミュニケーション、行動上の課題など多岐にわたります。 ここで最も大切なのは、見栄を張らず、普段のありのままの状態を正確に伝えることです。 「いつもはできないけれど、今日は調子が良いからできる」と答えてしまうと、実態より低い区分に判定され、本当に必要な支援が受けられなくなる可能性があります。
ステップ3:主治医による医師意見書の作成
市区町村は、認定調査と並行して、申請者が指定した主治医に「医師意見書」の作成を依頼します。 意見書には、病名や障害の原因、現在の症状、治療内容、生活上の留意点などが記載され、審査会が医学的観点から支援の必要性を判断するための重要な資料となります。 申請者自身が書類を取り寄せる必要はなく、市区町村と主治医の間で直接やり取りされるのが一般的です。
ステップ4:審査会による判定と区分の決定
認定調査の結果と医師意見書などをもとに、障害支援区分の決定が行われます。 判定は、以下の2段階で行われます。
- 一次判定(コンピュータ判定)
- 認定調査の80項目の結果をコンピュータに入力し、どのくらいの支援が必要かを客観的なデータとして算出します。
- 二次判定(審査会による審査)
- 一次判定の結果に加え、認定調査の際の特記事項や医師意見書などを総合的に勘案し、保健・医療・福祉の専門家で構成される「市区町村審査会」で最終的な区分が判定されます。
こうして決定された区分は、市区町村から「障害福祉サービス受給者証」と共に本人に通知されます。
障害支援区分によって利用できる自立支援給付とは
障害支援区分の認定を受けると、「自立支援給付」と呼ばれる障害福祉サービスを利用できます。 自立支援給付は、「介護給付」と「訓練等給付」の2種類に大別されます。
介護の支援を受ける「介護給付」
日常生活上の身体介護や家事援助、移動支援などを中心としたサービスです。 原則として、障害支援区分1以上の方が必要なサービスに応じて利用できます。
- 居宅介護(ホームヘルプ)
- 自宅での入浴、排せつ、食事の介護や、調理、洗濯などの家事援助。
- 重度訪問介護
- 重度の肢体不自由などで常に介護が必要な方に、長時間の訪問介護を提供。
- 同行援護・行動援護
- 視覚障害のある方の外出支援(同行援護)や、知的・精神障害のある方の行動援護。
- 短期入所(ショートステイ)
- 介護者の不在時などに、短期間、施設に入所できる。
- 療養介護・生活介護
- 常に介護が必要な方に、日中、施設で身体介護や創作・生産活動の機会を提供。
- 施設入所支援
- 夜間や休日に、施設で身体介護や生活支援を提供。
就労などの訓練を受ける「訓練等給付」
自立した生活や就労を目指すための訓練が中心のサービスです。 原則として、障害支援区分の認定は不要です。
- 自立訓練(機能訓練・生活訓練)
- 身体機能や生活能力の維持・向上のための訓練。
- 共同生活援助(グループホーム)
- 地域で共同生活を送りながら、日常生活の援助を受ける。
- 就労移行支援
- 一般企業への就職を目指し、知識やスキルを身につける訓練を原則2年間利用できる。
- 就労継続支援(A型・B型)
- 一般企業での就労が難しい方が、サポートのある環境で働く。 A型は雇用契約を結び、B型は雇用契約を結ばずに自分のペースで働ける。
障害支援区分に関するよくある質問
認定調査ではどんなことを聞かれる?
認定調査は、全国共通の調査票に基づき、大きく分けて「移動や動作」「身の回りの世話」「意思決定」「行動障害」「特別な医療」など8つの分野、合計80項目について聞き取りが行われます。 「寝返りができますか」「衣服の着脱ができますか」といった具体的な質問を通し、支援の必要度が調査されます。
認定結果に有効期間はある?
はい、あります。 障害支援区分の有効期間は、原則として3年間です。 有効期間が終了する前に市区町村から更新の案内が届き、引き続きサービスを希望する場合は更新申請が必要です。 心身の状態が大きく変化した場合は、有効期間の途中でも区分の見直しを申請できます。
認定結果に納得できない場合はどうすればいい?
万が一、決定された区分に納得できない場合は、不服申し立て(審査請求)を行うことができます。審査請求は、通知を受け取った日の翌日から3か月以内に、都道府県に設置されている「障害者介護給付費等不服審査会」に対して行います。手続きが分からない場合は、まず市区町村の担当窓口に相談してみましょう。
サービスの利用にかかる費用は?
障害福祉サービスを利用した際の利用者負担は、原則としてサービス費用の1割です。ただし、世帯の所得に応じて月々の負担上限額が定められており、それを超える利用者負担は発生しません。
| 世帯の所得状況 | 負担上限月額 |
|---|---|
| 生活保護受給世帯 | 0円 |
| 市町村民税非課税世帯 | 0円 |
| 市町村民税課税世帯(所得割16万円未満) | 9,300円 |
| 上記以外(所得割16万円以上) | 37,200円 |
※食費や光熱費、日用品費などは別途実費負担となります。
就労継続支援B型事業所の利用に障害支援区分は必要?
結論から言うと、原則として、就労継続支援B型事業所を利用するために障害支援区分の認定は必要ありません。 就労継続支援B型は「訓練等給付」に分類されるため、区分認定が必須となる「介護給付」とは異なります。 障害者手帳の所持や医師の診断書などにより、市区町村がサービスの利用を認めれば、区分がなくても利用を開始できます。 ただし、B型事業所に通いながらホームヘルプなども利用したい場合は、そのサービスのために区分認定が必要になります。
障害福祉サービスの利用に関するご相談はオリーブまで
「障害支援区分の手続きは、なんだか複雑で難しそう…」
「自分がどのサービスを利用できるのか、どこに相談すればいいのか分からない」
障害福祉サービスの手続きは、少し複雑に感じられるかもしれません。 そんな時は、一人で悩まず、私たち就労継続支援B型事業所オリーブにお気軽にご相談ください。 オリーブは、障害のある方が安心して自分のペースで働ける場所であると同時に、福祉サービスに関する情報提供や利用に向けたサポートを行う、地域に開かれた相談窓口でもあります。 「B型事業所に通ってみたいけど、自分は利用できる?」「区分認定の申請を手伝ってほしい」など、どんな疑問でも構いません。 経験豊富なスタッフが、あなたの状況を丁寧にお伺いし、親身にサポートします。 特に、就労継続支援B型は障害支援区分の認定がなくても利用を開始できる、社会参加への第一歩として最適なサービスです。 まずはオリーブで、これからの働き方を一緒に考えてみませんか。ご連絡を心よりお待ちしております。
