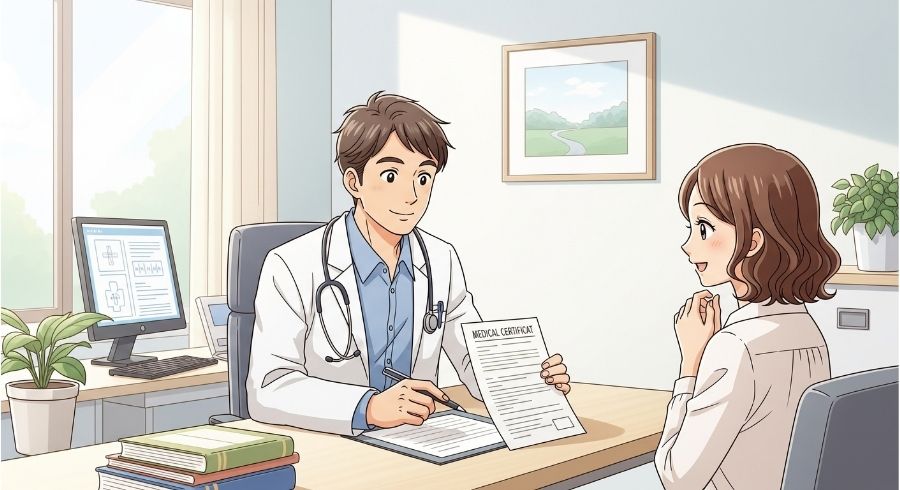
診断書とは?必要な場面と役割
病気やケガで会社を休むときや、公的な支援制度を申請するときに、「診断書を提出してください」と言われた経験はありませんか。「そもそも診断書とは何?」「どうやってもらうの?」「料金はいくらかかる?」など、いざ必要になると、分からないことばかりで戸惑ってしまう方も多いのではないでしょうか。診断書は、あなたの健康状態を公的に証明し、必要な休息やサポートを受けるために、非常に重要な役割を果たす書類です。この記事では、診断書とは何かという基本から、具体的なもらい方、料金の相場、そして特に重要となる休職や復職の際に会社へ提出する時のポイントまで、あなたが抱える診断書に関するあらゆる疑問に、分かりやすくお答えしていきます。正しい知識を身につけて、スムーズに手続きを進め、安心して治療や療養に専念しましょう。
病状や治療内容を証明する公的な書類
診断書とは、医師が患者の健康状態や病状、治療内容などについて、専門的な見地から診断した結果を記した公的な証明書です。医師法に基づき、診察した医師のみが発行できる、法的な効力を持つ文書です。そのため、客観的な事実に基づいて記載されており、患者本人の希望だけで内容を自由に変えることはできません。この「公的な証明力」があるからこそ、会社や学校、行政機関など、様々な場面で本人の状態を客観的に説明するための重要な根拠として用いられるのです。
会社への提出や各種手続きで必要になる
診断書は、主に以下のような場面で必要となります。
診断書が必要となる主なケース
会社・学校関連
-
- 病気やケガを理由に、会社を長期間休職・欠勤する場合
- 休職から復職(職場復帰)する場合
- 学校を長期間休む、または休学する場合
- 会社や学校の規定で、特定の感染症からの復帰時に提出を求められる場合
公的な手続き関連
-
- 傷病手当金や障害年金などの公的支援を申請する場合
- 生命保険の給付金を請求する場合
- 障害者手帳の申請・更新を行う場合
- 裁判などで、病気やケガの状態を証明する必要がある場合
このように、診断書は、あなたが正当な理由で休息をとったり、必要な経済的支援を受けたりするための、いわば「お守り」のような役割を果たしてくれます。
診断書のもらい方と作成にかかる期間
診断書が必要になった場合、どのように手続きを進めればよいのでしょうか。依頼から受け取りまでの流れを見ていきましょう。
まずは主治医に相談しよう
診断書を発行できるのは、あなたを実際に診察した医師だけです。診断書が必要になったら、まずはかかりつけの主治医に「〇〇の手続きで必要なので、診断書を作成してほしい」と、明確に依頼しましょう。その際、「誰に(提出先)」「何のために(目的)」「いつまでに(提出期限)」「どのような内容を(必要な記載項目)」を伝えると、医師もスムーズに必要な内容を記載することができます。提出先によっては、指定のフォーマットがある場合もあるため、事前に確認しておくとよいでしょう。
依頼から受け取りまでの日数
診断書の発行にかかる期間は、医療機関や診断書の内容によって様々です。比較的簡単な内容であれば、即日〜数日で発行されることが多いですが、詳細な検査結果や、複雑な内容を要する診断書の場合は、1週間〜2週間程度、あるいはそれ以上かかることもあります。提出期限がある場合は、日数に余裕を持って、早めに医師に依頼することが大切です。
診断書がもらえないケースもある?
基本的には、患者から依頼があれば、医師は診断書を作成する義務があります。しかし、以下のようなケースでは、発行を断られる可能性があります。
- 診察を受けていない
- 医師は、診察した事実に基づいてしか診断書を書けません。電話やメールだけで「診断書をください」と依頼しても、発行することはできません。
- 診断が確定していない
- 症状の原因を特定するための検査中など、まだ明確な診断が下せない段階では、診断書を作成できない場合があります。
- 虚偽の内容を依頼した場合
- 「本当は出社できるけれど、休みたいから診断書を書いてほしい」といった、事実に反する内容の依頼に、医師は絶対に応じません。
診断書の料金と記載内容
診断書の料金相場となぜ有料なのか
診断書の作成にかかる費用は、医療機関や記載内容の複雑さによって異なりますが、一般的に2,000円〜5,000円程度が相場です。中には、10,000円程度かかる場合もあります。これは、診断書の作成が、病気の治療そのものではない「私的文書の作成」にあたり、 健康保険の適用対象外 となるためです。費用は全額自己負担となります。料金は医療機関が自由に設定できるため、気になる場合は、依頼する際に受付などで事前に確認しておくと安心です。
診断書に書かれている主な項目
診断書のフォーマットは提出先によって様々ですが、一般的に以下のような項目が記載されます。
-
- 患者情報(氏名、生年月日、住所など)
- 診断名(例:「うつ病」「適応障害」など)
- 発病・初診年月日
- 症状の経過・治療内容
- 今後の見通し(治療に要する期間など)
- 医師の指示・意見(例:「〇ヶ月間の自宅療養を要す」「復職は可能だが、当面は時短勤務が望ましい」など)
- 作成日・医療機関名・医師名・押印
記載内容の希望は伝えられるか
診断書の内容は、医師が医学的所見に基づいて客観的に記載するため、患者の希望だけで事実と異なる内容に変えることはできません。しかし、「会社に、時短勤務や業務内容の配慮をお願いしたいので、その旨を先生の意見として書いてほしい」といった、治療や療養に必要な配慮に関する希望を伝えることは可能です。医師が必要だと判断すれば、その内容を「医師の意見」として診断書に盛り込んでくれる場合があります。まずは、自分の希望を率直に医師に相談してみることが大切です。
休職・復職で診断書を提出する際の注意点
心の不調などで、休職や復職をする際に、診断書は特に重要な役割を果たします。
休職時に診断書を提出する際のポイント
多くの会社の就業規則では、一定期間以上、病気で会社を休む場合に、診断書の提出が義務付けられています。これは、会社が従業員の健康状態を正確に把握し、正当な理由のある休みであることを確認するためです。診断書には、休養が必要な期間が明記されていることが重要です。提出を求められたら、以下の点に注意して速やかに提出しましょう。
- 提出先を確認する
- 直属の上司に渡すのか、人事部や総務部に直接提出するのか、会社のルールを確認しましょう。
- 提出前にコピーを取る
- 提出する前に、必ずコピーを取り、自分の手元に保管しておくことが大切です。後々の手続きで必要になる場合があります。
- 郵送の場合は送付状を添える
- 郵送で提出する場合は、簡単な送付状を添えるのがビジネスマナーです。簡易書留など、配達状況が追跡できる方法で送るとより安心です。
復職(職場復帰)の際に診断書が必要な場合
休職期間が終わり、職場に復帰する際にも、診断書の提出を求められることが一般的です。これは、「業務を遂行できる状態まで回復していること」を、医師の専門的な見地から証明してもらうためです。この診断書は、単に「復職可能」と書かれているだけでなく、「復職にあたり、どのような配慮が必要か(残業の制限、業務内容の調整など)」といった、具体的な意見が記載されていることが、スムーズな職場復帰と再発予防につながります。
休職中の生活を支える傷病手当金と医師の証明
休職中の生活を支える「傷病手当金」を申請する際にも、医師の証明が必要です。これは「診断書」という独立した書類ではなく、「傷病手当金支給申請書」という申請様式の中に、医師が記入する欄が設けられています。この申請書は、本人が記入するページと、会社(事業主)が証明するページ、そして医師が記入する「療養担当者記入用」ページで構成されています。医師は、診察した事実に基づき「労務不能と認めた期間」や症状の経過などを証明します。そのため、証明を希望する期間中に、定期的な受診が必要となります。通常、1ヶ月ごとに申請するため、その都度、医師に記入を依頼することになります。
診断書に関するよくある質問(Q&A)
- Q1. 診断書に有効期限はありますか?
- A1. 診断書そのものに、法律で定められた有効期限はありません。しかし、提出先の会社や機関によっては、「発行から3ヶ月以内のものを提出してください」といった、独自のルールを設けていることがほとんどです。これは、時間が経つと症状が変化する可能性があるため、「現在の状態」を証明する必要があるからです。
- Q2. 会社に提出する診断書の病名を知られたくないのですが…
- A2. デリケートな問題ですね。まず、会社には従業員の健康情報に関する守秘義務があります。しかし、どうしても病名を伏せたい場合は、医師に相談してみましょう。医師の判断で、具体的な病名ではなく「抑うつ状態」「自律神経系の不調により、〇ヶ月間の休養を要す」のように、症状や必要な対応を中心に記載してくれる場合があります。ただし、傷病手当金の申請など、病名の記載が必須の手続きもあるため、目的によって対応は異なります。
- Q3. 診断書を紛失した場合、再発行はできますか?
- A3. はい、可能です。診察の記録(カルテ)は法律で5年間の保存が義務付けられているため、その期間内であれば再発行してもらえます。ただし、再発行にも費用がかかるのが一般的です。また、手続きに時間がかかる場合もあるため、紛失しないよう大切に保管しましょう。
- Q4. オンライン診療でも診断書はもらえますか?
- A4. もらえる場合と、もらえない場合があります。オンライン診療は、対面診療と組み合わせて行われることが原則です。そのため、初診からオンライン診療のみで、休職を要するような診断書を発行することは難しいケースが多いです。かかりつけ医がオンライン診療を行っており、症状が安定している場合の、復職に関する診断書などは発行されやすい傾向にあります。対応は医療機関や症状によって異なるため、直接確認が必要です。
働き方や職場復帰に不安があれば就労継続支援B型事業所オリーブへ
診断書をもらって、無事に会社を休むことができた。あるいは、復職はしたけれど、以前のように働くことに不安を感じている。そんな悩みを抱えていませんか。休職や復職は、ゴールではありません。そこから、いかに自分に合ったペースで、無理なく社会とのつながりを続けていくかが、何よりも大切です。私たち「就労継続支援B型事業所オリーブ」 は、病気や障害と向き合いながら、 「これからの働き方」を考えたいと願うあなたのための場所です。オリーブは、大阪、兵庫、京都、奈良の関西エリアで、障害のある方の就労をサポートしています。
一般企業への復職に不安がある場合、まずはオリーブのようなB型事業所で、働くためのリハビリから始めてみませんか。雇用契約を結ばずに利用できるため、
- 週1日・数時間から、自分の体調に合わせてスタートできる
- 軽作業やPC作業を通じて、働くことへの自信を少しずつ取り戻せる
- 生活リズムを整え、安定して通う習慣を身につけられる
- 専門の支援員に、働き方や将来についての不安をいつでも相談できる といった、多くのメリットがあります。
診断書を手に、これからの働き方に迷ったら、ぜひ一度、オリーブにご相談ください。あなたの「次の一歩」を、一緒に考え、応援します。
