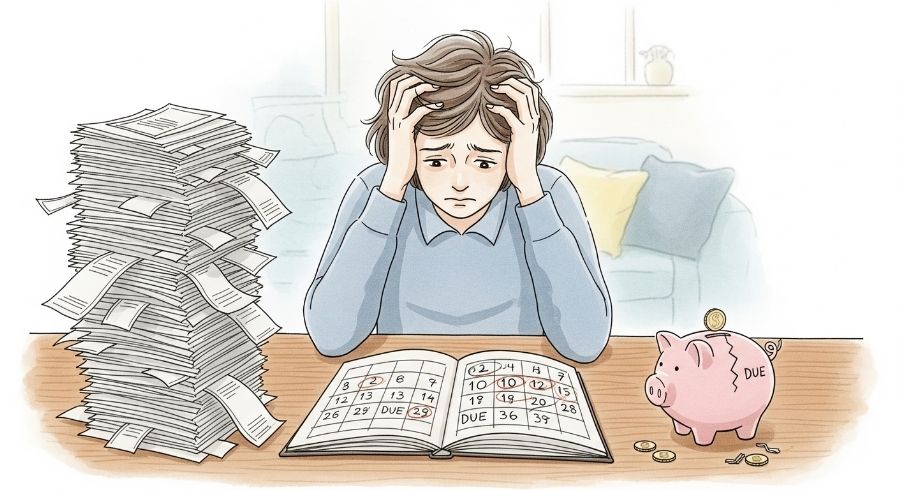
病気やケガで、長期的に会社を休まざるを得なくなったとき、最も大きな不安は、やはり「お金」のことではないでしょうか。「休んでいる間、お給料はもらえるの?」「ボーナスはどうなるの?」「社会保険料や税金はどうやって払えばいいの?」など、分からないことばかりで、安心して療養に専念できない、という方も少なくありません。
休職中の収入がゼロになってしまうと、生活が成り立たなくなってしまいます。しかし、日本の社会保障制度には、そんな時にあなたの生活を支えてくれる、心強い仕組みが用意されています。この記事では、休職中の給与やボーナスの基本的な考え方から、生活の大きな支えとなる「傷病手当金」制度、そして意外と見落としがちな社会保険料や税金の支払いについて、一つひとつ丁寧に解説していきます。お金の不安を正しく解消し、心穏やかに回復への道を歩むために、ぜひこの記事の情報を役立ててください。
休職中の給与やボーナスはもらえるの?
長期の休みに入るにあたり、まず気になるのが、会社からの給与やボーナスがどうなるか、という点です。基本的な考え方を理解しておきましょう。
原則として給与の支払いはない「ノーワーク・ノーペイの原則」
労働契約における大原則として、「ノーワーク・ノーペイの原則」というものがあります。これは文字通り、「働いていない(No Work)時間に対しては、会社は給与を支払う(No Pay)義務はない」という考え方です。従業員の自己都合(私傷病など)による休みである休職期間中は、労働の提供がないため、法律上、会社に給与を支払う義務はありません。そのため、ほとんどの会社では、休職期間中の給与は「無給」となります。
ただし、これはあくまで法律上の原則です。会社によっては、従業員を手厚くサポートするために、就業規則で「休職期間中の最初の〇ヶ月は、基本給の〇割を支給する」といった、独自の給与保障制度を設けている場合もあります。まずは、ご自身の会社の就業規則や賃金規程を必ず確認してみましょう。
休職中のボーナスや退職金の取り扱い
給与と同じく、ボーナス(賞与)についても、その支払いは法律で義務付けられているものではなく、会社の裁量に委ねられています。ボーナスは一般的に、「算定対象期間」における勤務実績や業績への貢献度に応じて支給額が決定されます。そのため、休職によって算定対象期間の全部または大半を休んでいた場合は、ボーナスが支給されないか、あるいは大幅に減額されることがほとんどです。
一方、退職金については、多くの場合、勤続年数に応じて算出されるため、休職期間も勤続年数に含まれるのが一般的です。ただし、これも会社の退職金規程によって異なるため、就業規則等で確認しておくことが重要です。
休職中の生活を支える傷病手当金とは
休職中は無給となるのが原則ですが、それでは生活が成り立ちません。そこで、会社員や公務員などが加入する健康保険から、休職中の生活を保障するために支給されるのが「傷病手当金」です。これは、すべての被保険者に与えられた正当な権利であり、休職中の生活を支える最も重要な制度です。
傷病手当金を受け取るための4つの条件
傷病手当金は、以下の4つの条件をすべて満たした場合に支給されます。
- 業務外の事由による病気やケガの療養のための休業であること
- 通勤中や業務上の災害は労災保険の対象となるため、私的な病気やケガが対象です。うつ病などの精神疾患による休職も、これに含まれます。
- 仕事に就くことができないこと
- 療養担当者(医師)が、「労務不能(働くことができない状態)」であると証明することが必要です。自己判断ではなく、医学的な判断に基づいている必要があります。
- 連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと
- 療養のために仕事を休み始めた日から、連続した3日間(これを「待期期間」と言います)が経過した後、4日目以降の休んだ日に対して支給されます。この待期期間には、有給休暇や土日・祝日も含まれます。例えば、金曜日から休み始めた場合、金・土・日の3日間が待期期間となり、翌月曜日(4日目)から支給対象となります。
- 休業した期間について給与の支払いがないこと
- 休職中に会社から給与が支払われている場合は、傷病手当金は支給されません。ただし、支払われた給与の日額が、傷病手当金の日額よりも少ない場合は、その差額が支給されます。
支給される金額と期間の目安
- 支給額
- 1日あたりの支給額は、「支給開始日以前の継続した12ヶ月間の各月の標準報酬月額を平均した額 ÷ 30日 × 2/3」で計算されます。おおよそ、月給の3分の2程度が支給される、とイメージしておくと良いでしょう。
- 支給期間
- 支給が開始された日から、通算して最長1年6ヶ月です。法改正により、途中で復職した期間はカウントされず、実際に休んだ日数を合計して1年6ヶ月分支給される「通算化」が実現し、より柔軟に利用できるようになりました。
傷病手当金の申請手続きと注意点
傷病手当金は、自動的に振り込まれるものではなく、自分で申請手続きを行う必要があります。
- 申請書の入手
- まずは、会社の担当者(人事・総務)や、ご自身が加入している健康保険組合(協会けんぽなど)のウェブサイトから、「傷病手当金支給申請書」を入手します。
- 申請書の作成
- 申請書は、本人記入欄、事業主記入欄、医師記入欄の3部構成が一般的です。
- 本人記入欄:氏名や振込先口座などを正確に記入します。
- 事業主記入欄:勤務状況や給与の支払い状況について、会社の担当者に記入を依頼します。早めに依頼しましょう。
- 医師記入欄:労務不能と認めた期間などについて、主治医に記入を依頼します。医師は診察した事実に基づいて記入するため、定期的な受診が不可欠です。
- 申請書の提出
- すべての項目を記入した申請書を、加入している健康保険組合に提出します。
通常、給与の締め日などに合わせて、1ヶ月ごとに申請するのが一般的です。申請から支給までには、健康保険組合での審査があるため、1〜2ヶ月程度かかる場合があります。その間の生活費については、あらかじめ貯蓄などで備えておくことが大切です。
休職期間中に支払いが必要な社会保険料や税金
休職中は収入が減る一方で、支払わなければならないお金もあります。特に、社会保険料と住民税は見落としがちなので、しっかりと確認しておきましょう。
社会保険料の支払いは継続して必要
休職中で給与が支払われていない期間も、会社に在籍している限り、健康保険料・厚生年金保険料・介護保険料(40歳以上)といった社会保険料は、毎月、全額支払う必要があります。通常は給与から天引きされますが、無給の場合は天引きできないため、会社が一旦立て替えて復職後に精算するか、会社から送られてくる納付書で毎月本人が振り込むことになります。支払い方法は必ず事前に会社の担当者と確認しておきましょう。
住民税の支払い方法と所得税の扱い
- 住民税
- 住民税は、前年の1年間の所得に対して課税される税金です。そのため、休職して今年の収入がなくても、前年に一定の収入があれば、支払い義務が発生します。支払い方法は、会社の担当者への確認が必須です。
- 所得税
- 所得税は、その年の所得に対して課税される税金です。休職中で給与収入がなければ、所得税はかかりません。また、傷病手当金は非課税所得ですので、所得税も住民税もかかりません。
焦らないで!休職期間中の過ごし方のヒント
お金の不安と並行して、「休職中、どう過ごせばいいのだろう」と悩む方も少なくありません。休職は、回復のための大切な時間です。時期に合わせて、焦らず過ごしましょう。
急性期:まずは休むことに専念する
休職に入ったばかりの時期は、とにかく心と体を休ませることが最優先です。「会社に迷惑をかけている」といった罪悪感は一旦手放し、医師の指示に従って、十分な睡眠と休息をとりましょう。好きな音楽を聴いたり、リラックスできる香りを試したりと、自分が心地よいと感じる環境を整えることが回復への近道です。
回復期:生活リズムを整え、軽い活動から始める
少し心身が回復してきたら、徐々に生活リズムを整えていきましょう。毎日決まった時間に起きて、太陽の光を浴びるだけでも効果的です。日中は、無理のない範囲で散歩に出かけたり、読書をしたり、簡単な家事をしたりと、少しずつ活動量を増やしていきます。この時期の「できた」という小さな達成感が、自信の回復に繋がります。
復職準備期:社会との接点を少しずつ持つ
体調が安定してきたら、復職に向けて心と頭の準備を始めます。図書館で過ごしたり、短時間カフェで読書をしたりと、家以外の場所で過ごす時間を増やしてみましょう。会社のウェブサイトをチェックしたり、関連するニュースを読んだりするのも良いでしょう。また、自治体や医療機関が運営する「リワークプログラム」を利用し、専門家の支援を受けながら通勤の練習や軽作業を行うのも、スムーズな復職への有効なステップです。
休職に関するよくある質問(Q&A)
- Q1. 有給休暇が残っています。先に使った方がいいですか?
- A1. 傷病手当金の待期期間(最初の連続3日間)は給与が支払われないため、この期間に有給休暇を充てることで、収入の空白期間をなくすことができます。待期期間が明けた4日目以降は、傷病手当金が支給されるため、有給休暇を使うか、傷病手当金に切り替えるかを選択できます。
- Q2. アルバイトやパートでも傷病手当金はもらえますか?
- A2. はい、もらえます。雇用形態にかかわらず、会社の健康保険に被保険者として加入していれば、傷病手当金の対象となります。
- Q3. 休職期間満了で退職することになりました。傷病手当金はもうもらえませんか?
- A3. 一定の条件を満たせば、退職後も継続して傷病手当金を受給できる場合があります。主な条件は以下の2つです。
-
- 健康保険の被保険者期間が、退職日まで継続して1年以上あること。
- 退職日に、傷病手当金を受給しているか、受給できる状態(労務不能)であること。
退職後の生活を支える重要な制度ですので、該当する場合は必ず保険者に確認しましょう。
休職後の働き方に不安があれば就労継続支援B型事業所オリーブへ
休職を経験したことで、「元の職場に戻って、また同じように働けるだろうか」「これを機に、もっと自分に合った、心身に負担の少ない働き方を見つけたい」
そんな風に、休職後のキャリアに不安や迷いを感じている方もいらっしゃるかもしれません。その不安は、あなたの心と体が発している、大切なサインです。無理に元の働き方に戻ろうとせず、一度立ち止まって、これからの働き方をじっくりと考えてみませんか。
私たち「就労継続支援B型事業所オリーブ」は、休職を経験された方などが、安心して社会復帰への新たな一歩を踏み出すためのお手伝いをしています。オリーブは、大阪、兵庫、京都、奈良の関西エリアで、障害のある方の就労をサポートする福祉サービス事業所です。
一般企業への復職に高いハードルを感じる場合、まずはオリーブのようなB型事業所で、働くためのリハビリから始めてみる、という選択肢があります。雇用契約を結ばずに利用できるため、
-
- 週1日・1日1時間から、自分の体調に合わせてスタートできる
- 軽作業やPC作業などを通じて、生活リズムと働く自信を少しずつ取り戻せる
- 支援員に、働き方の不安や悩みをいつでも相談できる
といった、今のあなたに必要な、安心できる環境で、次のステップへの準備を整えることができます。
休職は、人生の終わりではなく、新しい働き方を見つけるための始まりです。あなたの「次の一歩」を、私たちと一緒に探してみませんか。
