認知行動療法(CBT)とは?その効果や自分でできる方法・病院での費用をわかりやすく解説
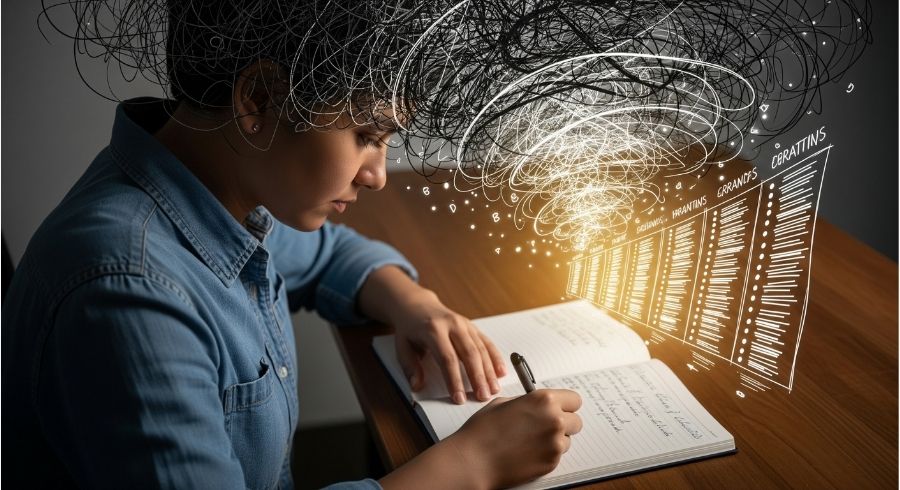
「どうして自分は、いつも物事を悪く考えてしまうのだろう…」「また失敗するんじゃないかと不安で、新しいことに挑戦できない」と感じて、生きづらさを抱えていませんか。そのネガティブな思考の連鎖は、あなたの性格だけのせいではないかもしれません。実は、私たちの「考え方のクセ」は、トレーニングによって変えていくことができます。そのための有力なアプローチの一つが、今回ご紹介する「認知行動療法(Cognitive Behavior Therapy: CBT)」です。
認知行動療法は、うつ病や不安障害など、様々な心の不調に対する効果が科学的に証明されている心理療法です。この記事では、認知行動療法の基本的な仕組みから、期待できる効果、さらには自分一人で取り組める具体的な方法まで、専門的な知識がない方にも分かりやすく解説します。この記事を読めば、つらい気持ちを軽くし、自分らしく生きるためのヒントが見つかるはずです。
認知行動療法(CBT)とは?
認知行動療法は、カウンセリングを通じて、自分の考え方や行動のパターンを見直し、より現実的でバランスの取れたものに変えていくことで、心のストレスを軽減していく心理療法です。薬物療法のように薬の力に頼るのではなく、自分自身の力で問題解決能力を高めていくことを目指します。
考え方の癖(認知)に働きかけてストレスを軽くする心理療法
認知行動療法の根幹には、「人の感情は、出来事そのものではなく、その出来事をどう受け取るか(認知)によって決まる」という考え方があります。例えば、「コップに半分の水」という同じ出来事でも、「もう半分しかない」と捉えてがっかりする(認知)人もいれば、「まだ半分もある」と捉えて安心する(認知)人もいます。つらい気持ちになりやすい人は、物事を悲観的・否定的に捉える「認知のゆがみ」を持っていることが多いと言われています。認知行動療法では、この自分を苦しめている「認知のゆがみ」に気づき、それをより柔軟で現実的なものに変えていく練習をします。
あなたを苦しめる「認知のゆがみ」10のパターン
認知のゆがみとは、現実を極端に、あるいは否定的に解釈してしまう、無意識の思考パターンのことです。ここでは代表的な10パターンをご紹介します。自分に当てはまるものがないか、チェックしてみましょう。
- 全か無か思考(白黒思考)
- 物事を白か黒か、0か100かで判断する。「少しでもミスをしたら、すべてが失敗だ」
- 過度の一般化
- 一つの悪い出来事をもって、「いつもこうだ」「今後もずっとこうなる」と結論づける。「一度断られたから、私は誰からも好かれないんだ」
- 心のフィルター(選択的抽出)
- 良いことには目を向けず、悪い部分だけを拾い上げて、全体の印象を悪くする。「褒められた点もあったのに、一つの注意点ばかりが気になる」
- マイナス化思考
- 良い出来事が起きても「これは例外」「まぐれだ」と過小評価し、肯定的な経験を無視する。
- 結論の飛躍
- 根拠がないのに、悲観的な結論に飛びつく。「心の読みすぎ(あの人は私のことを馬鹿にしているに違いない)」「先読みの誤り(この挑戦は絶対に失敗する)」など。
- 拡大解釈と過小評価
- 自分の失敗や欠点は過大に考え、長所や成功は過小に評価する。「私のミスは致命的だが、私の成功は誰にでもできることだ」
- 感情的決めつけ
- 自分の感情を、現実の証明だと信じ込む。「こんなに不安なのだから、きっと悪いことが起こるに違いない」
- 「~すべき」思考
- 「~すべきだ」「~してはならない」という厳しいルールを自分や他人に課し、それが守れないと罪悪感を感じたり、他人に失望したりする。
- レッテル貼り
- 一つのミスから、自分自身や他者に対して「私はダメ人間だ」「彼は使えない奴だ」といった否定的なレッテルを貼る。
- 個人化(自己関連づけ)
- 何か悪いことが起きたとき、自分に責任がないことまで「自分のせいだ」と思い込む。「会議の雰囲気が悪いのは、私がつまらない発言をしたせいだ」
「認知療法」と「行動療法」の組み合わせ
認知行動療法(CBT)は、その名の通り、「認知療法」と「行動療法」という2つのアプローチを統合したものです。
- 認知療法
- 上記のような「認知のゆがみ」に焦点を当て、それを修正していくアプローチです。
- 行動療法
- 考え方を変えるだけでなく、「実際に行動を変えてみることで、気分や考え方に良い変化をもたらそう」というアプローチです。
例えば、不安で外出できない人に対し、「まずは5分だけ散歩してみる」といった達成可能な小さな目標を設定し実行します。そして、「やってみたら、意外と大丈夫だった」という成功体験を重ねることで自信を取り戻し、「外出は怖いものだ」という認知を少しずつ変えていくのです。
悩みの原因となる「自動思考」と「スキーマ」
認知行動療法では、自分を苦しめる考えを、表面的な「自動思考」と、より根深い「スキーマ」の2つの層に分けて理解します。
- 自動思考
- ある状況で、瞬間的にパッと頭に浮かぶ考えやイメージのことです。例:「会議で意見を言えなかった」→(自動思考)「自分はなんてダメな人間なんだ」
- スキーマ
- 自動思考の奥にある、その人の中核的な信念や価値観です。主に幼少期の経験から形成され、「自分は無価値だ」「完璧でなければならない」といった、その人にとっての「根本的なルール」のようなものです。
CBTでは、まず具体的な場面での「自動思考」に気づく練習から始め、必要に応じて、その根っこにある「スキーマ」にも働きかけていきます。
認知行動療法(CBT)で期待できる効果
認知行動療法は、その効果が多くの研究で科学的に証明されており、うつ病や不安障害など、様々な心の悩みに有効とされています。
- つらい気持ちやストレスが軽減される: うつ病やパニック障害、社交不安障害、強迫性障害、PTSDなどに特に効果が高いとされています。思考パターンを客観視し、バランスの取れた考え方ができるようになることで、過度な不安や落ち込みから抜け出しやすくなります。
- 問題解決能力が高まる: 自分の自動思考に「本当にそうか?」と問いかけるスキルが身につき、物事を多角的に捉えられるようになります。感情に振り回されず、冷静で建設的な問題解決ができるようになります。
- 対人関係の改善にもつながる: 「相手はきっとこう思っているはずだ」というネガティブな思い込み(認知のゆがみ)に気づき、修正する習慣をつけることで、不要な誤解や対立を避け、より円滑な人間関係を築けるようになります。
自分でできる認知行動療法の代表的な方法
認知行動療法は専門家と行うのが基本ですが、そのエッセンスを自分一人で実践できるテクニックがあります。
思考のクセを見直す「コラム法」
コラム法は、頭の中の思考を紙に書き出して「見える化」し、客観的に眺め、よりバランスの取れた考え方を見つけるためのテクニックです。静かな環境でノートとペンを用意し、7つの列からなる表を書いて実践します。
【7つのコラム法の進め方】
- コラム1(出来事)
- 気分が動揺した時の具体的な状況を客観的に書きます。(例:職場で上司に挨拶したが、そっけない態度だった)
- コラム2(感情)
- その時の感情と、その強さ(0~100%)を書きます。(例:不安 80%、悲しい 70%)
- コラム3(自動思考)
- 瞬時に頭に浮かんだ考えをそのまま書きます。(例:「私は上司に嫌われているんだ」)
- コラム4(根拠)
- 自動思考を裏付ける事実を挙げます。(例:上司が目を合わせてくれなかった)
- コラム5(反証)
- 自動思考と矛盾する事実や、他の可能性を挙げます(最も重要)。(例:上司は他の人ともあまり話しておらず、疲れているように見えた)
- コラム6(適応的思考)
- 根拠と反証を踏まえ、より現実的でバランスの取れた考え方を導き出します。(例:そっけない態度だったが、嫌われていると決まったわけではない。疲れていただけかもしれない)
- コラム7(感情の変化)
- 新しい考えに至った後の感情の強さを再度採点します。(例:不安 30%、悲しい 20%)
行動を変えて気分を上げる「行動活性化」
コラム法と並行して行いたいのが「行動活性化」です。これは、気分が落ち込んでいる時こそ、あえて少しだけ活動してみることで、気分の改善や意欲の向上を目指す方法です。大切なのは、ハードルの低い「簡単な行動」から始めることです。
-
- 行動リストの作成: 「5分間散歩する」「好きな音楽を1曲聴く」「洗い物をする」など、少し頑張ればできそうな行動のリストを事前に作っておきます。
- 計画と実行: 気分が落ち込んだ時に、そのリストから一つ選んで実行します。
- 記録: 行動後の気分や達成感を簡単にメモします。「やってみたら少し気分が晴れた」という小さな成功体験が、次の行動への意欲につながります。
病院やクリニックで認知行動療法を受ける場合
セルフケアでうまくいかない場合や、症状が重い場合は、専門家のサポートを受けることが大切です。
どこで受けられる?費用は?
認知行動療法は、精神科や心療内科のある医療機関や、民間のカウンセリングルームなどで受けられます。医療機関では、薬物療法と並行して行われたり、保険が適用されたりする場合があります。
- 保険適用の場合
- うつ病や不安障害など特定の疾患と診断されれば、医療機関でのCBTに健康保険が適用されます。3割負担で1回3,000円~5,000円程度が目安です。
- 保険適用外(自費)の場合
- カウンセリングルームなどでは全額自己負担となり、1回5,000円~15,000円程度が相場です。
精神疾患で通院中の方は、医療費の自己負担が原則1割になる「自立支援医療(精神通院医療)」制度を利用できる場合があるので、市区町村の窓口にご相談ください。
治療の流れと注意点
治療は通常、1回30分~50分の面接を週1回~2週に1回のペースで、合計12回~20回ほど継続します。カウンセラーとの話し合いを通じて自分の問題点を整理し、コラム法などの技法を学び、日常生活で実践する「ホームワーク」を通じて定着させていくのが基本的な流れです。ただし、CBTは万能ではなく、効果の出方には個人差があります。また、自分のつらい部分と向き合う作業が必要になるため、信頼できる専門家と、相性の良い治療者を見つけることが非常に重要です。
CBTとあわせて安心できる環境で働く練習を 就労継続支援B型事業所オリーブ
認知行動療法は、自分の考え方のクセに気づき、それを修正していくための強力なツールです。しかし、学んだことを実践し、身につけるには「練習」が不可欠です。そして、その練習の場が過度なストレスに満ちた環境であれば、せっかくの学びも活かすことが難しくなってしまいます。
もしあなたが、心の不調を抱えながら、働くことに不安を感じているなら、「就労継続支援B型事業所オリーブ」で、CBTの実践と働く練習を両立させてみませんか。オリーブは、障害や心身の不調のある方が、安心して自分のペースで働ける場所です。ストレスの少ない穏やかな環境は、CBTで学んだ新しい考え方や行動を、安心して試すことができる「実践の場」となります。あなたの心身の状態に合わせて、「今日は簡単な作業にしよう」「コラム法を試したいから少し休憩しよう」といった働き方も可能です。悩みや不安について経験豊富な支援員に相談することもできます。
認知行動療法で心のセルフケアを学びながら、オリーブという安心できる環境で働く練習を重ねる。その二つの両立が、あなたの自信と、未来への希望を育む大きな力となります。まずは見学から、お気軽にお問い合わせください。
