大人向け|ASD(自閉スペクトラム症)とは?特徴・原因・診断・サポートを解説
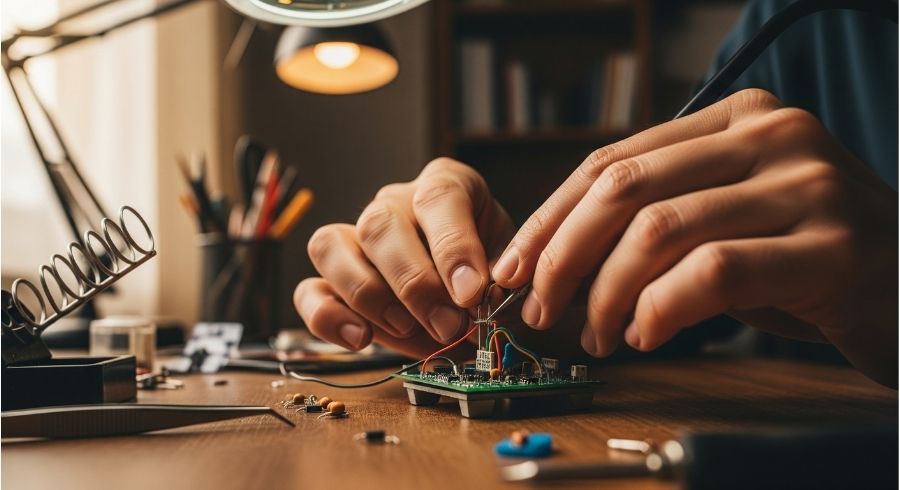
「もしかして自分はASD(自閉スペクトラム症)かもしれない」「家族や同僚の言動がASDの特性に似ている気がする」と感じて、情報を探している方へ。この記事では、大人のASD(自閉スペクトラム症)について、その基本的な知識から、具体的な特徴、仕事での困りごと、そして利用できるサポートまでを網羅的に解説します。ASDは、決して特別なことではありません。生まれ持った脳の特性であり、その特性を正しく理解し、環境を整えることで、困難を軽減し、むしろ強みとして活かすことも可能です。この記事を読めば、ASDへの理解が深まり、ご自身や周りの方が自分らしく、安心して社会生活を送るための具体的なヒントが見つかるはずです。就労に関する悩みをお持ちの方には、就労継続支援B型事業所という選択肢についてもご紹介しますので、ぜひ最後までご覧ください。
ASD(自閉スペクトラム症)とは
ASD(自閉スペクトラム症)の定義
ASD(自閉スペクトラム症)は、生まれつきの脳機能の発達のかたよりが原因で起こる発達障害の一つです。英語では「Autism Spectrum Disorder」と表記され、その頭文字をとって「ASD」と呼ばれています。かつては「自閉症」「アスペルガー症候群」「特定不能の広汎性発達障害」など、いくつかの異なる診断名で呼ばれていました。しかし、2013年にアメリカ精神医学会が発行した診断基準「DSM-5」から、これらの特徴を連続体(スペクトラム)として捉える「自閉スペクトラム症」という診断名に統合されました。
ASDの主な特徴は、「対人関係や社会的コミュニケーションの困難」と「限定された興味やこだわり、感覚の偏り」です。これらの特性は、その人の性格やわがまま、努力不足が原因なのではなく、脳の機能的な特性によるものだと理解することが重要です。
ASD(自閉スペクトラム症)の原因
ASDの明確な原因は、現在の医学ではまだ特定されていません。しかし、多くの研究から、親の育て方やしつけ、愛情不足などが原因ではないことがわかっています。現在、最も有力とされているのは、特定の遺伝子だけでなく、複数の遺伝的な要因が複雑に絡み合って、脳機能の発達に偏りが生じるという「多因子遺伝」の考え方です。ASDの特性は生まれつきのものであり、後天的な要因で発症するものではありません。子どもの頃には特性が目立たず、学校生活や社会に出てから、環境とのミスマッチによって困難が表面化し、大人になってから診断を受ける「大人の発達障害」として注目されるケースが増えています。
「スペクトラム」の概念
「スペクトラム」とは、「連続体」という意味の言葉です。ASDの特性の現れ方は、まるで虹の色が赤から紫までくっきりと分かれているわけではなく、少しずつグラデーションで変化していくように、一人ひとり異なり、その濃淡も様々です。例えば、ある人は対人関係の困難さが強く現れる一方で、こだわりはそれほど強くないかもしれません。また、別のある人は、特定の分野に強いこだわりと才能を発揮する一方で、コミュニケーションは比較的スムーズにとれるかもしれません。
このように、ASDと定型発達(発達障害ではない人)との間に明確な境界線を引くことは難しく、特性の現れ方には個人差が大きいのが特徴です。そのため、「自閉スペクトラム症」という名前が使われています。
ASD(自閉スペクトラム症)の主な特性と困りごと
ASDの特性は、大きく分けて2つのカテゴリーに分類されます。これらの特性によって、日常生活や仕事の場面で様々な困りごとが生じることがあります。
対人関係・社会性における困難さ
多くのASD当事者が困難を感じるのが、他者とのコミュニケーションや社会的なやりとりです。
- 相手の気持ちを察するのが苦手
- 表情や声のトーン、身振りなど、言葉以外の非言語的なサインを読み取ることが難しく、相手が怒っているのか、悲しんでいるのかが分からないことがあります。
- 言葉の裏の意味を理解するのが難しい
- 「適当にお願いします」といった曖昧な指示や、皮肉・冗談などを文字通りに受け取ってしまい、混乱することがあります。
- 一方的に話してしまう
- 自分の興味があることについて、相手の関心や状況を考えずに話し続けてしまう傾向があります。会話のキャッチボールが苦手で、話の終わり方が分からないこともあります。
- 視線を合わせるのが苦手
- 人と目を合わせることに強い苦痛や緊張を感じるため、無意識に視線をそらしてしまい、「話を聞いていない」「失礼だ」と誤解されることがあります。
- 集団行動が苦手
- 学校のクラスや職場のチームなど、集団の暗黙のルールや場の空気を読むことが難しく、孤立感を感じたり、集団の中でどう振る舞えば良いか分からなくなったりします。
こだわりの強さと柔軟性の乏しさ
もう一つの大きな特徴は、特定の物事に対する強いこだわりや、決まった手順を好む傾向です。
- 常同行動・反復行動
- 特定の手順やルールに強くこだわり、毎日同じ時間に同じ道を通り、同じ食事をとるなど、決まったパターンを繰り返すことで安心感を得ます。
- 急な変更や予定外の出来事への抵抗
- いつもと違うことが起こると、強い不安やパニックに陥ることがあります。例えば、電車の遅延や、急な仕事の依頼などに対応するのが非常に困難です。
- 興味の範囲が限定的
- 自分の興味がある特定の分野(例:電車、アニメ、歴史など)に対して、驚異的な集中力と知識を発揮します。その一方で、興味のないことには全く関心を示さないことがあります。
- 感覚の過敏さ、または鈍麻さ
- 特定の感覚が非常に敏感(感覚過敏)、または鈍感(感覚鈍麻)なことがあります。
- 感覚過敏の例:特定の音(救急車のサイレンなど)が耐えられないほど大きく聞こえる、蛍光灯の光が眩しすぎる、特定の素材の服が肌に触れると痛みを感じる、など。
- 感覚鈍麻の例:暑さや寒さ、痛みを感じにくく、怪我や体調不良に気づきにくい。
ASD(自閉スペクトラム症)とADHD(注意欠如・多動症)の関係性
ASDとADHD(注意欠如・多動症)は、どちらも発達障害に分類されますが、異なる特性を持つ障害です。しかし、ASDとADHDの特性を併せ持つ(併存する)ケースは少なくありません。例えば、「計画通りに進めたい(ASD特性)のに、不注意でミスをしてしまう(ADHD特性)」といった、一見矛盾した行動が見られることがあります。
ASD(自閉スペクトラム症)の診断と「治療」
「自分はASDかもしれない」と感じたら、どこに相談し、どのようなプロセスで診断されるのでしょうか。
ASD(自閉スペクトラム症)の診断方法
ASDの診断は、精神科や心療内科、発達障害者支援センターなどの専門機関で行われます。血液検査や脳の画像検査のように、客観的な数値で判断できるものではなく、医師による問診や心理検査などを通じて総合的に行われます。
- 問診(インテーク面接)
- 現在の困りごとや、子どもの頃の様子(生育歴)について詳しく話を聞きます。
- 心理検査
- 知能検査(WAIS-IVなど)や、発達特性を評価する質問紙(AQなど)を用いて、認知機能の得意・不得意や、ASD特性の傾向を客観的に評価します。
- 総合的な診断
- これらの情報を総合的に判断し、アメリカ精神医学会の診断基準「DSM-5」などに基づいて、医師が最終的な診断を下します。
ASD(自閉スペクトラム症)における「治療」の考え方
ASDは生まれつきの脳機能の特性であるため、薬を飲んだり手術をしたりして特性そのものをなくす「根本治療」は存在しません。ASDにおける「治療」とは、主に二次障害の予防・治療と、特性との付き合い方を学ぶことを指します。
- 二次障害の予防・治療
- ASDの特性によって、周りから理解されずに叱責されたりする経験が続くと、うつ病や不安障害といった「二次障害」を発症することがあります。こうした症状を和らげるために、薬物療法(抗うつ薬など)や精神療法が行われることがあります。
- 特性との付き合い方を学ぶ
- カウンセリングや認知行動療法(CBT)、SST(ソーシャルスキルトレーニング)などを通じて、自分の特性を理解し、対人関係のスキルやストレスへの対処法を学びます。また、過ごしやすいように環境を調整することも重要です。
ASD(自閉スペクトラム症)の特性理解と仕事での活かし方
ASDの特性は、しばしば「苦手なこと」として捉えられがちですが、視点を変えれば唯一無二の「強み」にもなり得ます。
「社会モデル」の考え方
障害の捉え方には、「個人モデル」と「社会モデル」という2つの考え方があります。
- 個人モデル
- 障害は個人の心身機能の問題であり、本人が努力で克服すべきもの、という考え方。
- 社会モデル
- 障害は個人の問題ではなく、社会にある障壁(バリア)との相互作用によって生み出されるもの、という考え方。
ASDも同様に、本人の特性と、周囲の環境とのミスマッチによって「生きづらさ」が生じます。逆に言えば、環境を調整し、特性に合った場所を選ぶことで、困難を大幅に減らすことができるのです。
得意な部分を活かす(リフレーミング)
ASDの特性を、ポジティブな側面から捉え直す「リフレーミング」は、自己肯定感を高め、強みを活かす上で非常に有効です。
| ASDの特性(一見ネガティブな側面) | リフレーミング(ポジティブな側面) |
|---|---|
| こだわりが強い、融通が利かない | 探求心が強く、専門性が高い。最後まで粘り強くやり遂げる。 |
| 興味の範囲が限定的 | 特定の分野で、専門家レベルの知識と集中力を発揮できる。 |
| 空気が読めない、正直すぎる | 裏表がなく誠実。嘘がつけないため信頼できる。 |
| 感覚が過敏 | 細かい違いや変化によく気づく。品質管理などで力を発揮する。 |
| ルールや手順に忠実 | 決められたことを正確に、着実に実行できる。ミスが少ない。 |
ASD(自閉スペクトラム症)と仕事
ASDの特性を理解した上で、どのような仕事が向いていて、どのような配慮が必要なのでしょうか。
得意・苦手な仕事の傾向
ASDの人が能力を発揮しやすい仕事と、困難を感じやすい仕事の一般的な傾向は以下の通りです。
- 得意・向いているとされる仕事の例
- ルールや手順が明確で、一人で黙々と取り組める、正確性や論理性が求められる仕事。
- 具体的な職種:プログラマー、システムエンジニア、Webデザイナー、テスター、データ入力、経理、校正・校閲、研究者、職人、工場でのライン作業、倉庫でのピッキングなど。
- 苦手・困難を感じやすいとされる仕事の例
- 臨機応変な対応、マルチタスク、曖昧な指示、複雑な人間関係や感情労働が求められる仕事。
- 具体的な職種:接客・営業職、管理職、受付、秘書、緊急対応が求められる仕事など。
職場での環境調整とサポート(合理的配慮)
ASDの人が職場で能力を発揮するためには、環境調整が不可欠です。障害者雇用促進法では、事業主に対し、障害のある従業員からの申し出に応じて、過重な負担にならない範囲で必要な配慮を行うこと(合理的配慮)を義務付けています。
- 業務の指示に関する配慮
- 口頭だけでなく、メモやメールなど視覚的な情報で指示を出す。具体的・客観的な言葉で伝える。一度に多くの指示を出さず、一つずつ伝える。
- 職場環境に関する配慮
- パーテーションで区切られた静かな席を用意する。サングラスやイヤーマフの使用を許可する。
- 業務遂行に関する配慮
- 業務マニュアルを作成・整備する。急な業務変更を減らし、見通しを持てるようにスケジュールを共有する。
ASD(自閉スペクトラム症)に関する支援機関の活用
ASDに関する悩みや困りごとは、一人で抱え込む必要はありません。相談から診断、就労まで、様々な段階でサポートしてくれる専門機関が存在します。
- 発達障害者支援センター
- 発達障害のある人やその家族からの様々な相談に応じ、助言や情報提供、関係機関との連携を行う専門機関です。
- 障害者就業・生活支援センター(なかぽつ)
- 障害のある人の「働きたい」と「安定した生活を送りたい」を一体的に支援する機関です。
- ハローワーク(公共職業安定所)
- 障害のある方向けの専門の相談窓口が設置されており、障害者雇用の求人紹介などの支援を受けられます。
- 就労移行支援事業所
- 一般企業への就職を目指す障害のある人に対し、働くために必要な知識やスキルを身につけるための訓練や、就職活動のサポートなどを行う福祉サービスです。
- 就労継続支援(A型・B型)
- 一般企業で働くことが現時点では難しい人に対し、支援を受けながら働く場を提供する福祉サービスです。A型は雇用契約を結び、B型は雇用契約を結ばずに自分のペースで働きます。
ASD(自閉スペクトラム症)の方の就労は就労継続支援B型事業所オリーブへ
「すぐに一般企業で働くのは不安」「まずは自分のペースで働ける場所から始めたい」。もし、あなたがそのようにお考えなら、就労継続支援B型事業所という選択肢を検討してみてはいかがでしょうか。就労継続支援B型事業所は、雇用契約を結ばないため、週1日や1日数時間といった短時間からでも利用でき、自分の体調やペースに合わせて無理なく働くことに慣れていくことができる場所です。
私たち「就労継続支援B型事業所オリーブ」は、関西(大阪、兵庫、京都、奈良)を中心に、一人ひとりの特性や「やりたい」という気持ちに寄り添ったサポートを提供しています。PCスキルから軽作業まで、多様な仕事内容を用意しており、専門知識を持った支援員が丁寧にサポートする、安心して過ごせる温かい雰囲気の事業所です。「どんな場所か見てみたい」「まずは話だけでも聞いてみたい」という方も大歓迎です。見学や相談は随時受け付けておりますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。あなたの「働きたい」気持ちを、オリーブが全力でサポートします。
