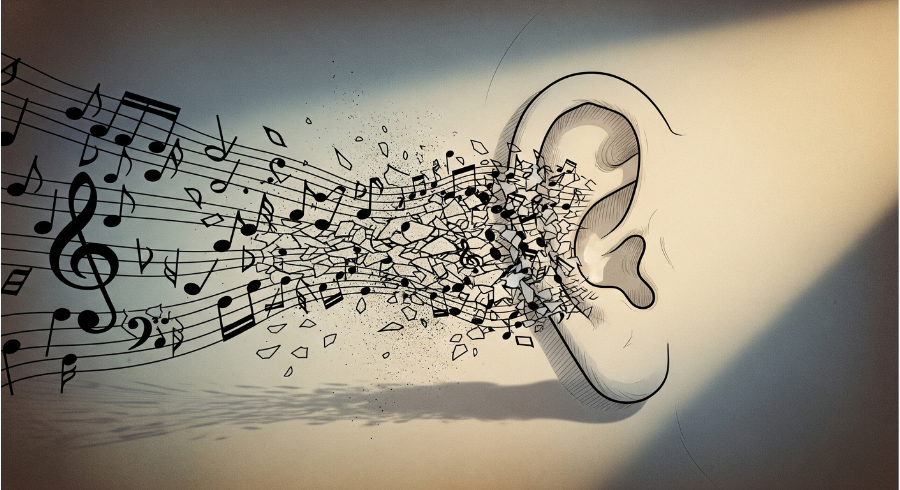
「ある朝、目覚めたら片方の耳が聞こえなくなっていた」
「電話の相手の声が、急に遠く感じるようになった」
このような経験に心当たりがあれば、それは「突発性難聴」かもしれません。突発性難聴は、何の前触れもなく、ある日突然、耳の聞こえが悪くなる病気です。特に働き盛りの世代に多く発症し、明確な原因がまだ解明されていないため、発症したご本人やご家族は大きな不安を感じることでしょう。
この記事では、突発性難聴の主な症状や現在考えられている原因、そして聴力回復の鍵を握る「早期治療」の重要性について、信頼できる情報に基づいて分かりやすく解説します。また、治療後も難聴や耳鳴りなどの後遺症が残った場合に、仕事でどのような困難が生じるのか、そしてその壁を乗り越えるために利用できる相談先や公的な支援制度についても詳しくご紹介します。突然の耳の不調に悩んでいる方、そしてそのご家族が、正しい知識を得て次の一歩を踏み出すための一助となれば幸いです。
突発性難聴とは?
ある日突然、耳が聞こえにくくなる原因不明の病気
突発性難聴は、その名の通り「突発的に」聞こえが悪くなる病気で、「いつ発症したか」を明確に特定できるほど突然に症状が現れるのが最大の特徴です。多くは片方の耳に起こりますが、ごくまれに両耳に発症することもあります。この病気は、音を感じ取る内耳や、そこから脳へ音の信号を伝える神経に障害が起きる「感音難聴」の一種です。年間におよそ3万人から4万人が発症していると推定されており、決して珍しい病気ではありません。特に40代から60代の働き盛りの世代に多いとされていますが、年齢や性別を問わず誰にでも起こり得ます。2024年現在も発症の明確な原因は解明されておらず、予防することが難しい病気です。そのため、症状に気づいたら「少し様子を見よう」と自己判断せず、速やかに耳鼻咽喉科の専門医を受診することが極めて重要です。
主な初期症状(難聴・耳鳴り・めまいなど)
突発性難聴では、難聴の程度や付随する症状に個人差がありますが、主に「難聴」「耳鳴り」「めまい」の3つが代表的な症状です。これらの症状が突然現れた場合は、突発性難聴を強く疑う必要があります。
難聴
病気の中核をなす症状です。聞こえ方は人によって様々で、以下のような症状がみられます。
- 片方の耳が完全に聞こえなくなる、または著しく聞こえにくくなる
- 音がこもって聞こえる、水中にいるような感じがする
- 耳に膜が張ったような感覚(耳閉感)がある
- 音が割れたり、異常に響いたりして聞こえる
- 電話や会話の声が聞き取りにくい
耳鳴り
難聴とほぼ同時に、多くの患者さん(約9割)に耳鳴りの症状が現れます。これも突発性難聴の大きな特徴の一つです。
- 「キーン」「ジー」といった金属音や電子音のような高音
- 「ボー」「ゴー」といった低い音
- 発症してから耳鳴りが途切れることなく続いている
めまい
約3割から4割の患者さんに、めまいの症状が見られます。難聴や耳鳴りに加え、めまいを伴う場合は、症状が重い傾向にあるとされています。
- 自分や周囲がぐるぐる回るような、激しい回転性のめまい
- 体がフワフワと浮くような、地に足がつかない感覚の浮動性めまい
- 強い吐き気や嘔吐を伴うこともある
これらの症状は、日常生活に大きな支障をきたすだけでなく、精神的な苦痛の原因にもなります。
突発性難聴の原因と診断
はっきりとした原因は不明 ストレスも一因か
突然の聴力低下という不安な症状に加え、原因が特定できないことも突発性難聴のつらい点です。現在、明確な原因は解明されていませんが、いくつかの仮説が有力視されています。
- ウイルス感染説
- 風邪やおたふくかぜなどを引き起こすウイルスが内耳に感染し、炎症を起こして神経細胞にダメージを与えるという説です。全身症状はなくても、ウイルスが内耳にだけ潜伏・再活性化するという考え方です。
- 内耳循環障害説
- 音を感じ取る器官である「蝸牛(かぎゅう)」は、非常に細い血管から栄養や酸素を受け取っています。この血管が血栓で詰まったり、痙攣(けいれん)を起こしたりして血流が悪化し、内耳の機能が障害されるという説です。
また、これらが直接的な原因でなくとも、過労や睡眠不足、強い精神的ストレスが発症の引き金(誘因)になることが多いと指摘されています。ストレスにより自律神経のバランスが乱れ、内耳の血流が悪化することが影響すると考えられており、実際に多くの患者さんが発症前に強いストレスや疲労を自覚しています。
突発性難聴の診断基準と検査
突発性難聴の診断は、症状の問診と聴力検査を基本とし、似た症状を持つ他の病気の可能性を一つひとつ除外していくことで確定します。厚生労働省の研究班が定めた診断基準があり、主に以下の3つの要件を満たす場合に診断されます。
診断の3つの要件
- 突然の発症:いつ、何をしている時に聞こえなくなったか、明確に説明できるほど突然に起こる。
- 高度な感音難聴:聴力検査で、特定のパターンを示す感音難聴が確認される。
- 原因が不明であること:問診や検査によって、他の病気(メニエール病や聴神経腫瘍など)が原因ではないと判断される。
鑑別診断のための主な検査
「突然の難聴」を引き起こす病気は他にもあるため、それらと見分ける「鑑別診断」が非常に重要です。
- 純音聴力検査
- 様々な高さの音(周波数)をどれだけ小さな音まで聞き取れるかを測定する、最も基本的な聴力検査です。難聴の種類や程度を調べます。
- 語音聴力検査
- 「ア」「キ」などの単音や単語が、どれだけ正確に聞き取れるかを測定します。言葉の聞き取り能力を評価し、日常生活での不自由さを把握するのに役立ちます。
- 画像検査(MRI、CT)
- 聴神経腫瘍など、脳や耳の奥に器質的な異常がないかを確認するために行われます。特にMRI検査は、聴神経や内耳の状態を詳しく調べるのに有用です。
以下に、鑑別が必要となる代表的な病気を示します。
| 鑑別が必要な主な病気 | 特徴 |
|---|---|
| メニエール病 | 難聴、耳鳴り、めまい発作を何度も繰り返すのが特徴。突発性難聴は原則として繰り返さない。 |
| 聴神経腫瘍 | 脳の腫瘍が聴神経を圧迫して難聴を引き起こす。通常はゆっくり進行するが、まれに突然発症することも。MRI検査で診断される。 |
| 急性低音障害型感音難聴 | 低音域の聞こえだけが悪くなる病気。ストレスや疲労が誘因とされ、比較的治りやすく、繰り返すことがある。 |
| 外リンパ瘻 | くしゃみや鼻を強くかむ、頭部外傷などをきっかけに内耳に穴が開き、リンパ液が漏れる病気。めまいや難聴を引き起こす。 |
これらの検査を経て、他の病気の可能性がすべて否定された場合に、最終的に突発性難聴と診断されます。
突発性難聴の治し方・主な治療法
早期発見・早期治療が何よりも重要
突発性難聴の治療は、まさに「時間との勝負」です。治療開始のタイミングが、その後の聴力の回復を大きく左右します。症状に気づいたら、迷わず、できるだけ早く耳鼻咽喉科を受診してください。内耳で音を感じ取る有毛細胞は非常にデリケートで、一度ダメージを受けると再生しにくい性質を持っています。治療の開始が遅れるほど、この細胞が回復不可能なダメージを負い、聴力が戻る可能性が低くなってしまいます。治療開始の目安として、発症から遅くとも1週間以内、可能であれば48時間以内が強く推奨されます。治療開始が2週間以上遅れると、聴力回復の可能性は著しく低くなることが知られています。「そのうち治るだろう」という自己判断が、回復の機会を逃すことに直結しかねません。
薬物療法が治療の中心
突発性難聴の治療は、心身の安静を基本とし、薬物療法が中心となります。原因が特定できていないため、現時点で有効性が期待される複数の治療法を組み合わせて行います。
ステロイド薬
内耳の炎症を鎮め、神経の腫れを引かせる目的で、副腎皮質ステロイド薬が治療の第一選択薬として用いられます。炎症によるダメージを最小限に食い止める効果が期待されます。投与方法は、難聴の重症度や患者さんの基礎疾患などを考慮し、点滴での大量投与(主に入院)や、内服(主に通院)が選択されます。
その他の薬物療法
ステロイド薬の効果を補助する目的で、以下の薬が併用されることがあります。
- 血管拡張薬
- 内耳の血流を改善し、神経細胞に酸素や栄養を供給しやすくします。
- ビタミンB12製剤
- 末梢神経の働きを助け、傷ついた神経の修復を促す効果が期待されます。
- 代謝促進薬
- 細胞のエネルギー代謝を活性化させ、内耳機能の回復をサポートします。
薬物療法以外の治療法
上記の薬物療法で十分な効果が得られない場合などに、以下の治療法が検討されることがあります。
- 高気圧酸素療法
- 専用の治療装置内で高濃度の酸素を吸入し、血液中に溶け込む酸素の量を増やして内耳の隅々まで供給する治療法です。細胞の活性化と回復を促します。
- 星状神経節ブロック
- 首にある交感神経の集まり(星状神経節)に局所麻酔薬を注射し、頭部や頸部の血管の緊張を和らげて血流を改善する治療法です。
治療中は、薬の効果を最大限に引き出すためにも、ストレスや過労を避けて十分な睡眠をとり、心身を安静に保つことが不可欠です。
治療期間と回復の見込み
治療期間は、入院の場合で1週間から10日程度が一般的です。通院の場合も、同様の期間、薬の内服などを続けることになります。気になる回復の見込みですが、残念ながら誰もが完全に治癒するわけではありません。一般的に、「およそ3分の1が完全に治る、3分の1はある程度改善するが後遺症が残る、残りの3分の1は改善が見られない」という「3分の1ルール」が知られています。回復の度合いは、発症時の難聴の程度、めまいの有無、治療開始までの期間、年齢などによって左右されます。一般的に、難聴の程度が軽いほど、めまいがないほど、そして治療開始が早いほど、回復しやすい傾向にあります。突発性難聴は一度かかると再発はしないとされていますが、治療後も難聴や耳鳴りなどが後遺症として残るケースは少なくありません。その場合は、後遺症と上手に付き合っていくことが次のステップとなります。
仕事への影響と利用できる相談先
突発性難聴による仕事での困りごと
突発性難聴の後遺症は、外見からは分かりにくいため「見えない障害」とも言われます。そのため、職場で必要な配慮を得られず、一人で悩みを抱え込んでしまう方も少なくありません。難聴や耳鳴りは、仕事の様々な場面で困難を引き起こす可能性があります。
コミュニケーションに関する困りごと
-
- 電話応対が難しく、相手の声が聞き取れない、または聞き間違える。
- 会議やミーティングで、複数人が同時に話すと内容を正確に把握できない。
- 騒がしい場所(オフィス、工場、店舗など)での会話が聞き取りにくい。
- オンライン会議で、音声の質が悪いと内容が理解できない。
- 何度も聞き返すことに罪悪感を覚え、分かったふりをしてしまう。
- 自分の声の大きさを調整できず、不必要に大声になったり、逆に小さすぎたりする。
業務遂行に関する困りごと
-
- 常時続く耳鳴りによって、業務への集中力が低下する。
- めまいの後遺症により、通勤や長時間の立ち仕事、高所作業、車両の運転などが困難になる。
- 機械の異音や警告音など、音で異常を検知する業務に対応できない。
- 聞き間違いによる業務上のミスが増え、自信を喪失してしまう。
- 緊急時の構内放送やアラームが聞こえず、安全確保に不安がある。
精神的な負担
-
- 周囲に症状を理解してもらえず、「怠けている」「無視された」などと誤解される。
- コミュニケーションの機会が減り、職場内で孤立感や疎外感を覚える。
- 将来への不安から、うつ状態になることもある。
頼りになる相談先・支援機関
仕事に関する悩みを一人で抱え込む必要はありません。状況に応じて、様々な相談先や支援制度を積極的に活用しましょう。
会社の上司・人事部・産業医
まずは、職場で現状を伝え、必要な配慮を求めることが第一歩です。自分の症状や、仕事で具体的にどのようなことに困っているのかを整理して伝えましょう。
相談できる配慮の例:
-
- 電話応対の免除、メールやチャットでの連絡への切り替え
- 会議での座席配慮(聞こえる耳側で発言してもらう、スピーカーの近くなど)
- 議事録や要点のメモによる情報保障
- 騒音の少ない部署や座席への異動
- 定期的な通院のための休暇取得の許可
身体障害者手帳の取得と関連サービス
難聴の程度によっては、身体障害者手帳(聴覚障害)を取得できる場合があります。手帳を取得することで、様々な福祉サービスや支援制度を利用できるようになります。
- 障害者手帳の等級(目安)
- 両耳の聴力レベルが70dB以上、または片耳の聴力レベルが90dB以上かつもう片方の耳の聴力レベルが50dB以上の場合、6級に該当する可能性があります。 ※等級は細かく規定されています。申請については、まず主治医に相談し、お住まいの市区町村の障害福祉担当窓口にお問い合わせください。
- 手帳取得の主なメリット
-
- 障害者雇用枠での就職・転職活動が可能になる
- 補聴器の購入費用や修理費用の助成
- 所得税・住民税の障害者控除
- 公共交通機関や公共施設の利用料金割引 など
公的な就労支援機関
現在の職場での課題解決や、転職を考える際に利用できる専門機関です。
| 支援機関 | 主な役割・相談できること |
|---|---|
| ハローワーク(障害者専門窓口) | 障害者手帳の有無にかかわらず相談可能。障害に関する専門知識を持つ相談員が、個々の状況に合わせた求人の紹介や就職活動全般をサポートします。 |
| 障害者就業・生活支援センター(なかぽつ) | 就職活動の支援から職場定着まで、仕事に関する支援と、金銭管理や健康管理といった生活面の課題を一体的にサポートしてくれる身近な相談機関です。 |
| 地域障害者職業センター | 職業能力の評価、リハビリテーション計画の作成、職場復帰に向けた支援(リワーク支援)など、より専門的で個別性の高い支援を提供しています。 |
後遺症と付き合いながら働くなら 就労継続支援B型事業所オリーブへ
突発性難聴の治療後も、難聴や耳鳴りといった後遺症によって、以前と同じように働くことが難しいと感じる場合があります。特に、騒がしい職場環境や、頻繁な電話応対・会議が求められる仕事では、心身ともに疲弊してしまうかもしれません。
「一般企業で働き続けるのはつらい」
「まずは体調を整え、自分のペースで働ける場所から再スタートしたい」
もしあなたがそのように感じているなら、「就労継続支援B型事業所」という選択肢を検討してみてはいかがでしょうか。
就労継続支援B型事業所は、障害や病気のある方が、雇用契約を結ばずに、ご自身の体調やペースに合わせて軽作業などを行いながら工賃(給料)を得られる福祉サービスです。私たち「就労継続支援B型事業所オリーブ」は、関西圏(大阪、兵庫、京都、奈良)に事業所を展開し、聴覚障害のある方も安心して活動できる環境を整えています。
オリーブでは、スタッフが聴覚障害への理解を深めており、筆談やチャットツールの活用、視覚的な指示など、一人ひとりの状況に合わせたコミュニケーション方法を一緒に考え、実践しています。作業内容も、データ入力や軽作業、PCスキルを活かせる業務など、比較的静かな環境で集中できるものが中心です。
週1日、1日数時間といった短時間の利用から始めることができ、ご自身の体調に合わせて無理なく通所することが可能です。経験豊富な支援員が、仕事の悩みはもちろん、日常生活での不安についても親身に相談に応じます。オリーブは、あなたが安心して過ごせる居場所であり、社会との繋がりを感じながら、ご自身のペースで次のステップを目指すための場所です。
見学やご相談は随時受け付けております。聴覚に後遺症を抱えながら働くことへの不安を、まずはお気軽にお聞かせください。
