知的障害(知的発達症)とは?原因や特徴・利用できる福祉サービスや支援機関を解説
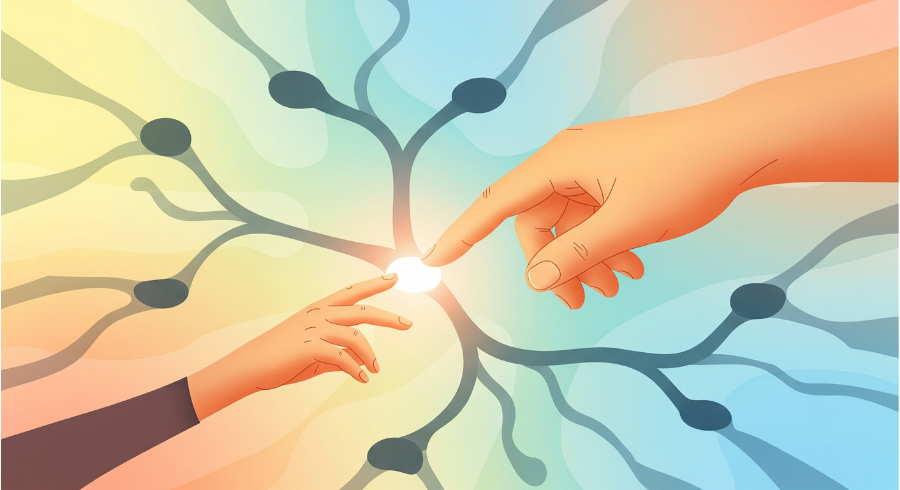
「知的障害」という言葉について、なんとなく知ってはいるけれど、具体的にどのような障害なのか、どんな特徴があるのか、詳しくご存じない方も多いかもしれません。知的障害は、その方の個性や可能性を正しく理解し、適切なサポートにつなげることが、共生社会の実現には不可欠です。知的障害は、決して特別なものではなく、その背景には様々な原因や、一人ひとり異なる豊かな個性があります。
この記事では、知的障害(知的発達症)の基本的な定義から、その原因や種類、特徴、そして利用できる福祉サービスや就職をサポートする支援機関まで、網羅的に、そして分かりやすく解説していきます。ご本人やご家族、支援者の方が、正しい知識を得て、より良い未来を築くための一助となれば幸いです。
知的障害(知的発達症)とは?
発達期までに生じた知的機能と思考・判断などにおける困難さ
知的障害とは、おおむね18歳頃までの「発達期」に、何らかの原因で知的機能の発達に遅れが生じ、その結果、日常生活や社会生活を送る上での適応機能にも、持続的な支援が必要な状態を指します。
ここでのポイントは、単に「知能指数(IQ)が低い」ことだけを指すのではなく、以下の2つの側面で、実質的な支援が必要な状態であるという点です。
- 知的機能の困難さ
- 学習、理解、思考、判断、計画といった、物事を学ぶ、考える、問題を解決するといった全般的な精神機能に、明らかな制限があること。
- 適応機能の困難さ
- 年齢相応の、自立した社会生活を送るために必要なスキル(コミュニケーション、身の回りの管理、対人関係など)に、明らかな制限があること。
医療の診断基準(DSM-5など)では、「知的発達症(Intellectual Developmental Disorder: IDD)」という名称が用いられていますが、日本の福祉制度では、一般的に「知的障害」という言葉が使われています。
軽度知的障害と境界知能(グレーゾーン)
知的障害は、その程度によっていくつかの段階に分けられますが、知的障害のある方全体の約85%は「軽度」に分類されると言われています。軽度知的障害のある方は、日常生活での身の回りのことは、ほとんど自立して行うことができます。小学校高学年程度の読み書きや計算能力を持ち、日常会話でのコミュニケーションも問題なく行える場合が多いため、一見しただけでは障害があるとは分かりにくいのが特徴です。そのため、周囲から「少し変わっている人」「仕事の覚えが悪い人」といった誤解を受け、生きづらさを感じているケースも少なくありません。
しかし、抽象的な概念の理解(例:「多様性」「経済」など)、複雑な事務手続き、金銭管理、対人関係での臨機応変な対応などには困難を抱えることがあり、社会生活を送る上では、個々の状況に応じたサポートが必要となります。
また、知能指数(IQ)が70~84の範囲にあたり、療育手帳の取得には至らないものの、生活面や学習面で困難さを抱える「境界知能(グレーゾーン)」の方々もいます。境界知能は障害ではないとされますが、軽度知的障害と同様に、周囲の理解や支援が必要な状態です。
知的障害(知的発達症)の原因と併存症
知的障害の主な原因
知的障害の原因は特定できないことも多いですが、主に知的機能の発達に影響が及ぶ時期によって、以下の3つに大別されます。
- 出生前要因
- 胎児期に、染色体異常(ダウン症候群など)や、先天的な代謝異常、母親の感染症(風疹など)、アルコール・薬物の影響などによって、脳の発達に影響が出る場合。
- 周産期要因
- 出産の際に、低酸素状態や、超低出生体重児、仮死状態などで脳にダメージが及ぶ場合。
- 出生後要因
- 乳幼児期に、髄膜炎や脳炎といった感染症、頭部の外傷、てんかん、栄養失調などによって、脳の発達が妨げられる場合。
知的障害は遺伝する?
「知的障害は遺伝するのではないか」という不安を持つ方もいるかもしれません。原因の一つにダウン症候群などの「染色体異常」や遺伝子の病気があるのは事実です。このような特定の遺伝性疾患が原因で知的障害が起こる場合、その疾患自体が遺伝することはあります。しかし、知的障害のある方の原因の30〜50%は特定が困難であり、知的障害そのものが親から子へ単純に遺伝するというわけではありません。
知的障害に多い併存症
知的障害のある方は、他の心身の障害や病気を併せ持つ(併存する)ことが少なくありません。
- てんかん
- 脳性まひ
- 発達障害(自閉スペクトラム症(ASD)、注意欠如・多動症(ADHD)など)
- 精神疾患(うつ病、不安障害など)
- 視覚や聴覚の障害
これらの併存症がある場合、それぞれの障害の特性を考慮した、よりきめ細やかなサポートが必要となります。
知的障害(知的発達症)の種類と特徴
知的障害の種類(分類)
福祉制度においては、一般的に知能指数(IQ)と日常生活能力の水準を基に、以下のように分類されます。
- 軽度
- IQがおおむね51〜70程度
- 中等度
- IQがおおむね36〜50程度
- 重度
- IQがおおむね21〜35程度
- 最重度
- IQがおおむね20以下
ただし、これはあくまで行政上の分類であり、一人ひとりの個性や能力をIQだけで測れるものではありません。
知的障害の主な特徴
知的障害の特性は、日常生活の様々な場面での「適応機能」の困難さとして現れます。
概念的スキル(考える力)の困難さ
- 言葉の理解や表現、読み書き、計算といった学習面での困難。
- 時間やお金の概念、優先順位、目標設定といった抽象的な事柄の理解が難しい。
(例)「だいたい」「適当に」といった曖昧な指示を理解するのが苦手。
社会的スキル(人と関わる力)の困難さ
- 相手の気持ちを察したり、場の空気を読んだりすることが苦手。
- 年齢相応の対人関係を築くのが難しい(一方的に話してしまう、距離感が近すぎるなど)。
- 社会のルールやマナーの理解に時間がかかり、善意から行ったことが裏目に出ることも。
実用的スキル(生活する力)の困難さ
- 食事や着替え、入浴といった、身の回りの管理(セルフケア)。
- 金銭管理や、公共交通機関の利用、スケジュール管理など、日常生活を営む上での実践的なスキル。
(例)電車の乗り換えなど、複数の手順が重なると混乱しやすい。
これらの困難さの程度は、一人ひとり大きく異なります。
家族や周囲の人ができること
知的障害のある方が安心して力を発揮するためには、家族や周囲の人の理解と適切な関わりが欠かせません。
- 具体的・肯定的な言葉で伝える
- 「あれやっといて」ではなく「テーブルの上を布で拭いてください」のように、指示は具体的に。できた時は「きれいになったね、ありがとう」と具体的に褒めることが自信につながります。
- 見通しを立てやすくする
- 言葉だけでなく、絵や写真、スケジュール表などを使って、その日の予定や作業の手順を「見える化」すると、安心して行動しやすくなります。
- 本人のペースを尊重する
- 急かしたり、一度に多くのことを求めたりせず、本人が理解し、納得して取り組めるペースを大切にしましょう。
- 失敗を責めずに、やり方を一緒に考える
- 失敗した時に責めるのではなく、「どうして難しかったかな?」「次はこうしてみようか」と、次に繋がる方法を一緒に考える姿勢が重要です。
知的障害のある方が利用できる福祉サービス
療育手帳(愛の手帳)
療育手帳は、知的障害があると判定された方に交付される障害者手帳です。この手帳を持つことで、様々な福祉サービスや支援、割引制度などを利用できるようになります。手帳の名称は自治体によって異なり、東京都では「愛の手帳」と呼ばれています。障害の程度によって区分が分かれており、受けられるサービスの内容が変わる場合があります。
各種相談機関
- 知的障害者更生相談所
- 各都道府県・指定都市に設置されている18歳以上の方を対象とした専門の相談機関です。療育手帳の判定のほか、福祉サービスや就労に関する専門的な助言を行っています。
- 発達障害者支援センター
- 発達障害のある方やその家族からの様々な相談に応じ、助言や情報提供、関係機関との連携を行います。
- 相談支援事業所
- 福祉サービスを利用する際に必要な「サービス等利用計画」の作成を支援してくれる、身近なパートナーです。どのサービスをどう利用すれば良いか分からない時に、一緒に考えてくれます。
成年後見制度
成年後見制度は、知的障害などの理由により、判断能力が不十分な方々を、法律的に保護し、支援するための制度です。家庭裁判所によって選ばれた成年後見人(親族、弁護士、社会福祉士など)が、本人の代わりに財産管理や、介護サービスの利用契約などを行うことで、本人の権利を守ります。
就職の際に使える支援機関
ハローワーク
全国のハローワークには、障害のある方の就職を専門にサポートする窓口が設置されています。専門の職員や相談員が、個々の障害特性や能力に合わせた職業相談や、求人の紹介、就職後のフォローアップなどを行っています。
障害者就業・生活支援センター(なかぽつ)
「なかぽつ」などの愛称で呼ばれる、地域に根差した支援機関です。仕事に関する「就業支援」と、日常生活に関する「生活支援」を一体的に行い、就職から職場定着まで、きめ細やかなサポートを提供してくれます。
就労移行支援事業所
一般企業への就職を目指す障害のある方を対象に、最長2年間、職業訓練や、ビジネスマナー、コミュニケーションスキルの向上、就職活動のサポートなどを行う福祉サービス事業所です。
自分に合った仕事探しなら就労継続支援B型事業所オリーブへ
知的障害のある方が、いきなり一般企業で働くことには、不安や難しさを感じることもあるでしょう。「自分のペースで、できることから始めたい」「仕事のスキルを、ゆっくり着実に身につけたい」――。そんな風に考えているあなたに、就労継続支援B型事業所オリーブという選択肢があります。
オリーブは、雇用契約を結ばず、一人ひとりの特性や能力、体調に合わせて、無理のないペースで働ける場所です。
- 分かりやすい作業内容
- 軽作業などを中心に、手順が明確で、自分のペースで集中して取り組める仕事をご用意しています。これは、見通しを立てることが得意ではない特性を持つ方でも、安心して作業できるよう配慮したものです。
- 丁寧なサポート
- 経験豊富なスタッフが、一人ひとりの隣で、根気強く、そして分かりやすく仕事の進め方をお教えします。曖昧な指示ではなく、「具体的」に伝えることを大切にしています。
- 安心できる居場所
- 同じような仲間と共に、コミュニケーションを学びながら、安心して過ごせる居場所を提供します。
まずはオリーブで、働くことの楽しさや、誰かの役に立つ喜びを感じながら、社会参加への自信をつけていきませんか。関西エリア(大阪、兵庫、京都、奈良)で、あなたらしい働き方の第一歩を踏み出したいとお考えなら、ぜひ一度、オリーブにご相談ください。
