知的障害(知的発達症)のある方の仕事とは?障害者雇用や利用できる就労支援を解説
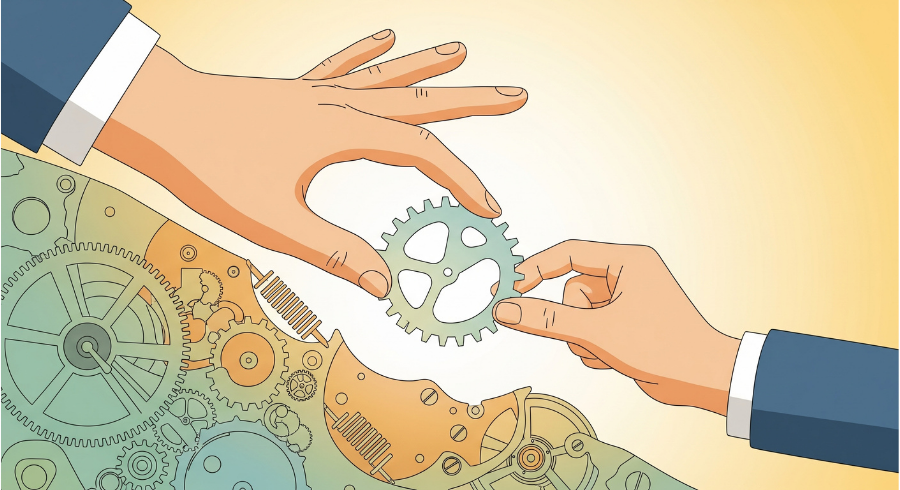
「働いて、自分の力で収入を得たい」「社会の一員として、やりがいを感じたい」知的障害(知的発達症)のある方も、そうした働くことへの強い願いを持っています。一人ひとりに個性や得意なことがあるように、知的障害のある方も、その特性に合った仕事や環境を見つけることで、能力を存分に発揮し、充実した職業生活を送ることが可能です。
しかし、仕事を探す上で、「どんな仕事が向いているのだろう?」「職場で困ったときはどうすればいい?」「誰に相談すればいいの?」といった、様々な不安や疑問に直面するかもしれません。
この記事では、知的障害のある方に向いている仕事の例や、安心して働くための選択肢である「障害者雇用」、そして仕事探しから就職後の定着までを支えてくれる専門の支援機関について、分かりやすく解説していきます。あなたらしい働き方を見つけるための、確かな一歩としてお役立てください。
知的障害(知的発達症)のある方の仕事や働き方
仕事に活かせる「強み」とは?
知的障害のある方は、困難さだけでなく、仕事において大きな強みとなる特性を多く持っています。これらの強みを理解し、活かせる仕事を選ぶことが、充実した職業生活への鍵となります。
- 素直さ・真面目さ
- 教えられたことやルールを素直に受け止め、真面目に守ろうとします。そのため、一度覚えた手順や決まり事を、正確に守り続けることができます。これは、品質管理や安全確保が重要な職場において、非常に高く評価される資質です。
- 集中力・持続力
- 興味を持ったことや、自分に合っていると感じる作業に対して、驚くほどの集中力を発揮します。特に、手順が決まっている定型的な作業では、長時間にわたって集中を持続させ、黙々と取り組み続けることができます。
- 純粋さ・ひたむきさ
- 損得勘定なく、目の前の仕事にひたむきに取り組む姿勢は、職場の同僚に良い影響を与え、チームの雰囲気を和ませることもあります。その純粋な頑張りが、周囲の働く意欲を引き出すきっかけになることも少なくありません。
これらの強みは、後述する「定型的な業務」において、存分に発揮される可能性があります。
どのような職業・働き方があるの?
知的障害のある方は、特に、手順が明確で、繰り返し行う定型的な業務において、その強みを発揮することが多いと言われています。具体的には、以下のような仕事で多くの方が活躍しています。
- 製造・軽作業
- 工場のラインでの部品の組み立て、完成品の検品、商品のラベル貼り、お菓子の箱詰めなど、マニュアルに沿ってコツコツと進める作業。
- 物流・倉庫作業
- ECサイトの倉庫などでの商品の仕分け(ピッキング)、在庫数の確認、ダンボールへの梱包、発送伝票の貼り付けなど。
- 清掃業務
- オフィスビルや商業施設、ホテルなどの共用部や客室の清掃。決められた範囲を、決められた手順で綺麗にすることに達成感を感じる方が多いです。
- 農業・園芸
- 野菜や花の栽培・水やり、収穫、選別、袋詰め、直売所での販売など、自然の中で体を動かす仕事。
- 事務補助
- 企業内での書類の仕分けやファイリング、郵便物の発送準備、簡単なデータ入力、シュレッダー作業、会議室の準備など、オフィスワーカーを支える業務。
- 飲食・サービス業
- レストランやカフェのキッチンでの皿洗いや調理補助、スーパーマーケットでの商品の品出しやバックヤードでの作業など。
これらの仕事はほんの一例です。大切なのは、ご本人の「好き」という気持ちや、「これならできそう」という得意なこと、そして「静かな環境が良い」「一人で黙々と作業したい」といった希望する働き方や環境を見つけ、それに合った仕事を選ぶことです。
障害者雇用のメリットと注意点
障害のある方が一般企業で働く際、「障害者雇用」という働き方を選択できます。これは、「障害者雇用促進法」に基づいて、企業が障害のある方を雇用するための特別な採用枠のことです。
障害者雇用のメリット
最大のメリットは、障害特性への理解と「合理的配慮」を得やすいことです。企業側は障害があることを理解した上で採用するため、業務内容の調整や分かりやすい指示方法、相談しやすい環境の整備など、その人が能力を発揮して、長く働き続けられるよう配慮してくれることが期待できます。
障害者雇用の注意点(デメリット)
一方で、いくつかの注意点も存在します。
- 求人数の限り:一般雇用の求人と比較すると、求人の絶対数は少なくなります。
- 職種の偏り:求人が特定の職種(軽作業や事務補助など)に偏る傾向があります。
- 給与水準:業務内容が限定されることなどから、給与水準が一般雇用の同職種より低い場合があります。
これらの注意点を理解した上で、それでも「安心して長く働ける環境」を最優先に考えるのであれば、合理的配慮を受けられる障害者雇用は非常に有効な選択肢と言えるでしょう。
知的障害(知的発達症)の方が仕事で困ることと合理的配慮
仕事で直面しやすい困難
知的障害の特性により、仕事の場面で、ご本人が意図せず困難に直面することがあります。
- 抽象的な指示の理解
- 「これ、いい感じにやっといて」と言われても、「いい感じ」の基準が分からず混乱してしまう。
- 計画的な行動
- 複数の仕事を一度に頼まれると、優先順位がつけられず、パニックになってしまう。
- 暗黙のルールの理解
- 挨拶や報告・連絡・相談(報連相)のタイミングなど、職場の暗黙のルールが分からないことがある。
- 環境の変化への対応
- 急な業務内容の変更や、部署の異動など、予期せぬ変化に対応するのが難しい。
職場で受けられる合理的配慮の例
上記のような困難を解消するために、企業は「合理的配慮」を提供します。これは法律で定められた企業の義務であり、働きやすさを支える重要な要素です。
採用選考における配慮
-
- 面接時間を通常より長く設定する。
- 質問は一つずつ、分かりやすい言葉で伝える。
- 必要に応じて、支援機関の担当者の同席を認める。
業務内容・指示に関する配慮
-
- 写真や図、動画などを用いた、視覚的に分かりやすいマニュアルを作成する。
- 指示は一度に一つに絞り、「〇〇が終わったら報告してください」と具体的に伝える。
- 業務のチェックリストを用意し、一つずつ確認しながら進められるようにする。
環境に関する配慮
-
- 騒音や人の出入りが少ない、集中しやすい作業場所を用意する。
- パーテーションを設置して、視覚的な刺激を減らす。
- 困った時にすぐに質問できる担当者(メンター)を決め、定期的な面談の時間を設ける。
これらの配慮は一例です。大切なのは、本人と企業、そして支援機関が連携し、その人に合った働きやすい環境を一緒に作っていくことです。
知的障害(知的発達症)の方の就職活動と支援機関
仕事探しの具体的な進め方
自分に合った仕事を見つけるためには、準備と計画が大切です。以下のステップで進めてみましょう。
-
- 自己分析(自分のことを知る):まずは自分を知ることから始めます。「何が好きか、嫌いか」「どんな作業が得意か、苦手か」などを、家族や支援者と一緒に書き出してみましょう。この時、厚生労働省が作成した「就労パスポート」というツールを活用するのも有効です。自分の情報や希望する配慮などを整理し、支援機関や企業に的確に伝えるのに役立ちます。
-
- 情報収集と相談:自己分析ができたら、ハローワークや後述する支援機関に相談に行きます。自分の希望を伝え、どんな求人があるか、どんなサポートが受けられるかといった情報を集めます。
-
- 応募書類の準備:支援者と相談しながら、履歴書や職務経歴書を作成します。得意なことや、真面目さ、継続力といった長所を具体的にアピールしましょう。必要な配慮についても、この段階で整理しておくと面接で伝えやすくなります。
-
- 面接対策:支援機関では、模擬面接を行ってくれます。「あなたの長所を教えてください」「どんな仕事をしてみたいですか?」といったよくある質問に対し、自信を持って答えられるよう、繰り返し練習しましょう。
-
- 体験と実習:興味のある仕事が見つかったら、就労移行支援事業所などを通じて職場見学や職場体験実習に参加します。実際に仕事を体験することで、自分に合っているかどうかを確かめることができ、就職後のミスマッチを防ぎます。
-
- トライアル雇用の活用:就職前に、企業と本人のミスマッチをなくすための「障害者トライアル雇用」という制度があります。これは、ハローワークなどの紹介により、原則3ヶ月間、企業で試行的に働くことができる制度です。実際に働きながら仕事内容や職場環境を確認できるため、安心して本採用に進むことができます。企業側にも助成金が出るメリットがあり、多くの企業で活用されています。
相談できる専門の支援機関
知的障害のある方が、自分に合った仕事を見つけ、働き続けるためには、専門の支援機関のサポートが不可欠です。
- ハローワーク
- 障害のある方向けの専門窓口が設置されており、求人の紹介や、面接の練習など、就職活動全般をサポートしてくれます。
- 地域障害者職業センター
- より専門的な支援を行う機関です。職業能力の評価のほか、「ジョブコーチ支援」では、支援員が職場を訪問し、本人への業務指導と、企業側(上司や同僚)への関わり方に関する助言の両方を行い、スムーズな職場適応を支援します。
- 障害者就業・生活支援センター(なかぽつ)
- 仕事(就業)だけでなく、金銭管理(給与の使い方)や健康管理(通院の仕方)、休日の過ごし方といった、日々の暮らし(生活)についても一体的に相談できるのが大きな特徴です。
- 就労移行支援事業所
- 一般企業への就職を目指す障害のある方を対象に、最長2年間、就職に必要な知識やスキルのトレーニングを行う福祉サービス事業所です。
就職後のキャリアと職場定着
就職はゴールではなく、新たなスタートです。長く働き続けるためには、就職後のサポート(職場定着支援)が非常に重要になります。就労移行支援事業所やなかぽつは、就職後も定期的に本人や企業と面談を行い、悩み相談や環境調整のサポートを続けてくれます。
また、同じ職場で経験を積むことで、任される仕事の範囲が広がったり、後輩に簡単な作業を教える役割を担ったりと、キャリアアップしていくことも十分に可能です。地道な努力と継続が、自信とさらなる成長につながります。
自分に合った仕事探しなら就労継続支援B型事業所オリーブへ
- 「いきなり一般企業で働くのは、まだ不安が大きい」
- 「まずは、安心できる環境で、働くことに慣れることから始めたい」
- 「自分のペースで、できることを少しずつ増やしていきたい」
もしあなたがそのように感じているなら、就労継続支援B型事業所オリーブという選択肢があります。
オリーブは、雇用契約を結ばず、一人ひとりの特性や能力、体調に合わせて、無理のないペースで働ける場所です。知的障害の特性に深い理解を持つスタッフが、あなたが安心して、そして楽しく仕事に取り組めるよう、きめ細やかにサポートします。
オリーブでの活動を通じて、まずは「決まった時間に、決まった場所へ通う」という基本的な労働習慣を身につけることができます。また、軽作業を通じて集中力や持続力を養い、仲間やスタッフとのコミュニケーションを通じて社会性を育むことも可能です。
ここで自信をつけ、基本的なスキルを身につけることが、将来、就労移行支援を利用したり、障害者雇用枠で一般就労を目指したりする上での、大きな土台となります。関西エリア(大阪、兵庫、京都、奈良)で、あなたらしい働き方の第一歩を踏み出したいとお考えなら、ぜひ一度、オリーブにご相談ください。
